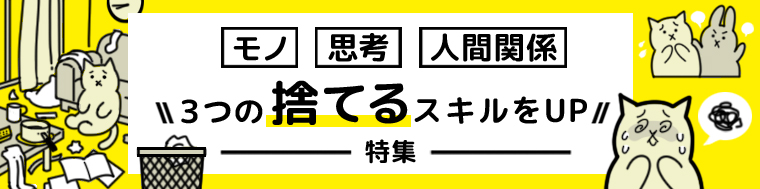部屋を整理すると人生が劇的に変わる⁉ その一歩目は客観的な視点で「捨てる」「捨てない」をジャッジ!
公開日:2021/3/5
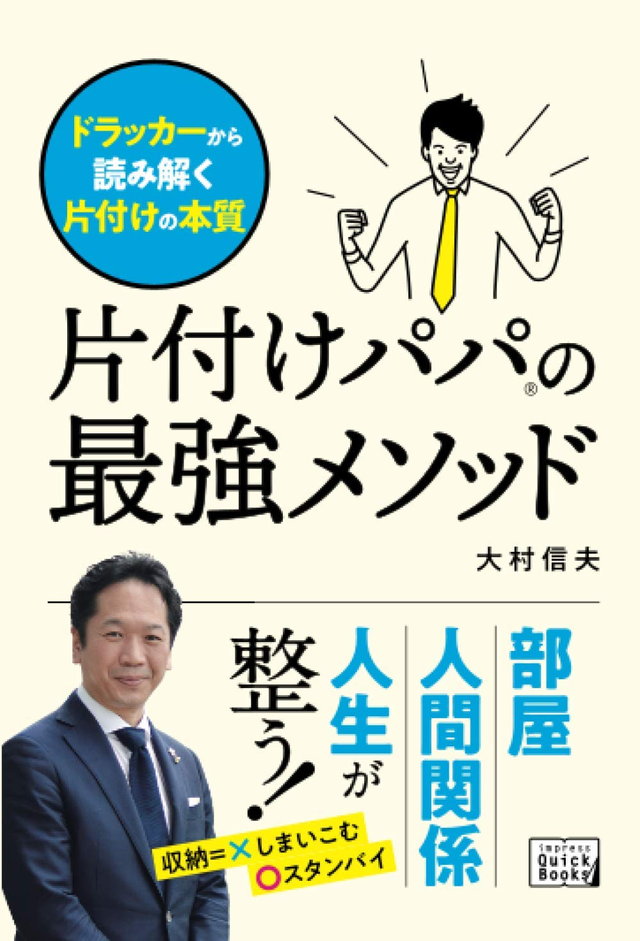
誰が言ったか知らないが、昔から“部屋の乱れは心の乱れ”とよく聞く。日常を振り返ってみるとたしかに、忙しくてヘトヘトだと洋服を脱ぎっぱなしにしたり、掃除するのも億劫になるときもあったりするので、あながち間違いではないと気が付く。
それでも、重い腰を上げて「片付け」に目覚めると人生すらも劇的に変化するという。書籍『片付けパパの最強メソッド ドラッカーから読み解く片付けの本質』(大村信夫/インプレス)は、会社員でありながら片付けのメソッドを広く伝える「片付けパパ」として活躍する著者が、その秘けつを丁寧に伝えてくれる一冊。
本書より、誰もが実践したくなる片付けるための「整理」「収納」「維持」の秘けつを紹介していこう。
全部のモノを引っ張り出して要不要を「整理」してみる
部屋の整理は、片付けの第一歩だ。最初に取り掛かるべきなのは、片付けたい部屋のモノを「全て出す」ということだ。棚や引き出しに入っているモノまで、とにかく一カ所へ集めてみると「片付けたい場所にあるモノの全体量」をみきわめることができる。
いったん全てのモノを出したあとは、それぞれ「必要」か「不要」かを仕分けていく。ただ、すぐにでも思い浮かびそうな「使える・使えない」「使っている・使えない」といった基準で判断してしまうと、ともすれば「これから使うかも……」と迷いが生じかねない。そのため、例えば「1年以内に使ったか、使わなかったか」など、客観的な基準を加えて判断するのがよいという。
そして、不要なモノは「ゴミに出す」というのが手軽な方法だが、最近では、フリマアプリやシェアリングサービスに出品して、収入に結びつけるという選択肢もある。
「収納」のコツは「動作・行動動線」を意識すること
続いては、いったん「整理」しながら必要だと判断したモノを収納する手順だ。初めに取り掛かりたいのは、収納スペースの「適正量」を決めること。例えば、タンスの引き出しには「洋服を◯枚まで」など、自分なりに基準を設ける。数字だけではなく、収納スペースに合わせて「入らなくなったら手放す」という基準でもよい。
また、日常生活で使いやすかったり、取り出しやすかったりと生活の「動作・行動動線」を考えた位置に収納するも大切で、使用頻度別に収納スペースを工夫するのも選択肢としてある。
さらに、本書では「グルーピング」と呼ばれる方法も紹介している。これは、複数のモノを作業の流れごとに収納するやり方だ。例えば、宅配便を出す場合には「メジャー、ガムテープ、配送伝票、ペン」と、必要なモノが色々とある。毎回、別々の場所から取り出すのは面倒なので、一カ所にまとめておくのも効率的だ。
整理・収納の先では「維持」を習慣化するのが大切
モノを整理して、収納場所もバッチリ決めた。ただ、一時的に部屋がすっきりしたとしても、その状態を「維持」するのはなかなか難しい。部屋ごとひっくり返すほどの大掃除をしてみたものの、また散らかってしまうといった経験も、多かれ少なかれあるはずだ。
整頓された部屋を維持するための秘けつは「考えなくてもできる状態になる(習慣化する)」ことだ。ただ、それほど難しいことではない。単純に「使ったら戻す」「増えたら減らす」と、意識するだけでよい。モノを購入するときも、自分にとって「本当に欲しいモノかどうか」「(家に)持ち込んでいいかどうか」と、ひと呼吸おいて考えてみるのが大切だ。
また、部屋が散らかる行動習慣も見つめ直す必要がある。なかでも、無意識にやってしまうのが「置く」という習慣だ。例えば、郵便受けから取り出したどこかのダイレクトメールを、とりあえず机の上に置いてしまう人もいるかもしれないが、すでにその時点で家は少しずつ散らかっていく。
外からモノを持ち込むときは「要る or 要らない」を前もって判断しておいて、要らないモノはとにかくゴミ箱へ入れるように心がけておこう。
本書には、一人ひとりが「人生という大きな器を整えて充実した日々を過ごすための一歩を踏み出していただく」という著者の思いが込められている。その内容をたよりに、散らかった部屋を整頓してみれば、心機一転で毎日の生活へ打ち込めるようになるはずだ。
文=カネコシュウヘイ