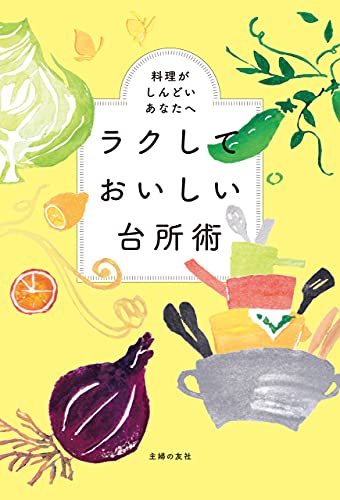人気料理研究家がふだんのごはん作りでやっているラクする手抜き法
公開日:2021/6/30
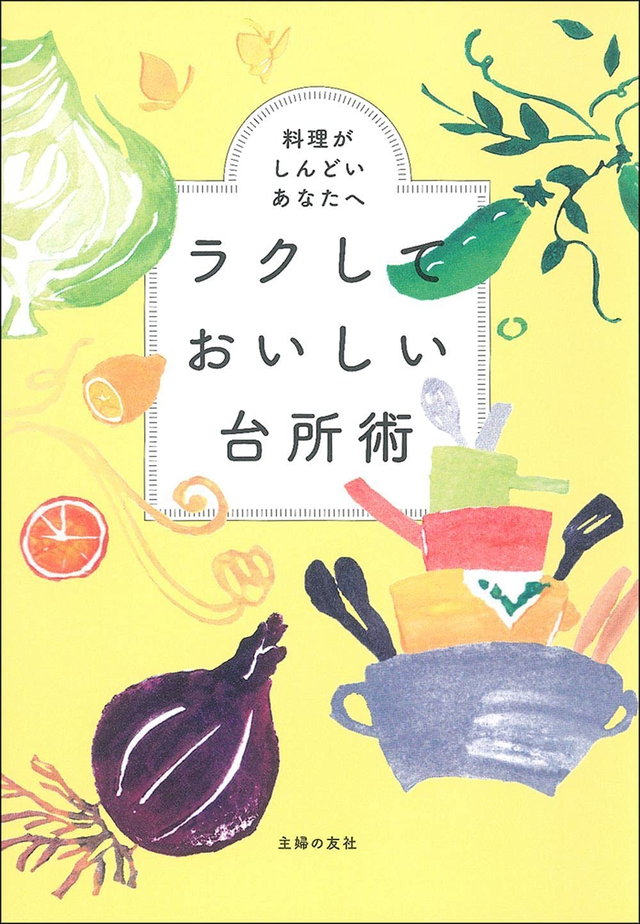
外食がままならない今、自炊の機会が増え、一日中食べることの心配をしているような気がする。自分のカラダや家族の健康のことを考えると、美味しくて栄養のある「ちゃんとした食事」をとりたいし、作りたい。それなのに、日々忙しくて料理に手が回らなかったり、そもそも料理が苦手だったり、ひとり暮らしでごはん作りのモチベーションが低かったり。理想と現実のギャップに「料理ってしんどいな」「大切なことなのにちゃんとできないなんてダメだ」とストレスを抱えがちだ。
そんな人はぜひとも『料理がしんどいあなたへ ラクしておいしい台所術』(主婦の友社:編/主婦の友社)を読んでほしい。心のおもりから少し解放されるに違いない。
料理のプロというと、いとも簡単に料理をしていると思ってしまうが、実はプライベートのごはん作りでは私たち同様に「ラクができて」「面倒くさくなくて」「頑張らなくていい」方法を試行錯誤していたことがわかり、ほっとする。本書は、7名の料理研究家が毎日のごはん作りで大切にしている考え方や、賢い手抜き方法が紹介されている。プロならではの視点によるそれらは、取り入れたいものばかりだ。
瀬尾幸子さんは、「家で食べるごはんは簡単に作れて、飽きないことが大切」だから「“繰り返し作れるもの、しょっちゅう作っておいしく食べられるもの”をいくつか知っておくだけでいい」という。その上で材料の組み合わせを変えたり、旬の素材に変えたりすれば、味わいも変化がつき、自然とレパートリーが増えて、結果的に飽きないことにつながるのだとか。シンプルな料理を調味料で「味変」させることは渡辺麻紀さんもおすすめする。
確かに、飽きないごはんを作るのに日々レシピ検索をする、という作業はとても疲れることかもしれない。作りやすさはどうか、冷蔵庫にある材料でできるか、好きな味だろうか、とあれこれ考えながらチャレンジし続けるよりも、自信のある作り方に少し変化をつけることのほうがずっとラクだし、続けられそうだ。
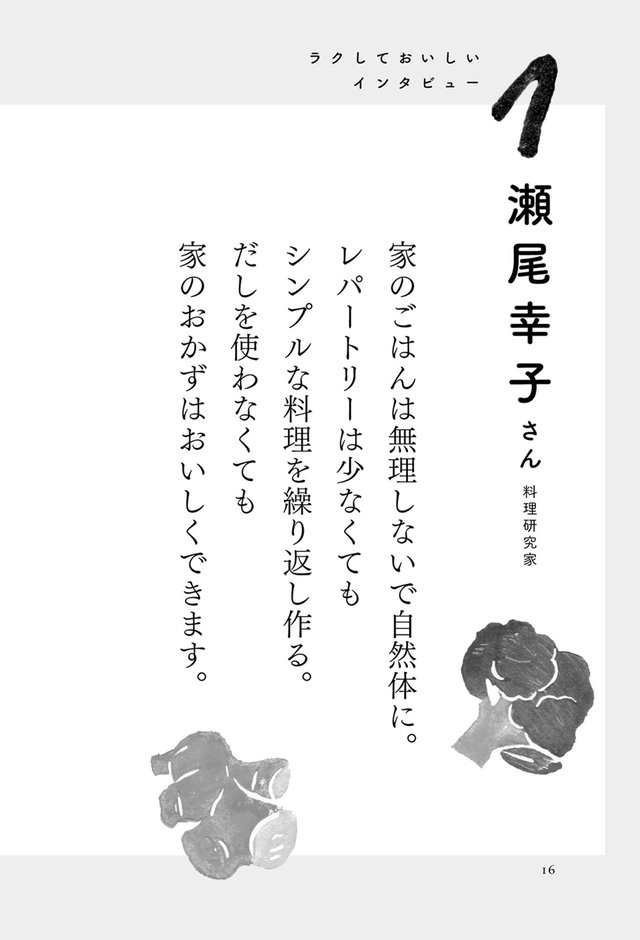
道具を上手に使うことも複数の方が提案している。脇雅世さんがフル活用するのは話題の調理家電「低温調理器」。使い慣れない道具だとかえって面倒とか、最新すぎて使いこなせないかも、と不安がよぎる。でも、食材と調味料をいれた耐熱袋を湯の中につけて、低温調理器をセットして待つだけ。温度と時間を設定すれば、料理スキルは関係なくだれでも、同じように作ることができるのが低温調理器の良いところ。
意外にも、ぶりの煮物やえびチリなど、魚介類の料理と相性がよいそうで、魚の煮物はどうも仕上がりがかたくなってしまう、という悩みも低温調理器ならふっくらやわらかくできる。煮汁も魚にまとわせる程度でよく、少ない調味料でも浸透圧の関係でしっかり味はしみこんでくれる。ほったらかしにできるので寝ている間に調理ができたり、長時間キッチンに立つことがつらくなるシニア世代にも向いている。
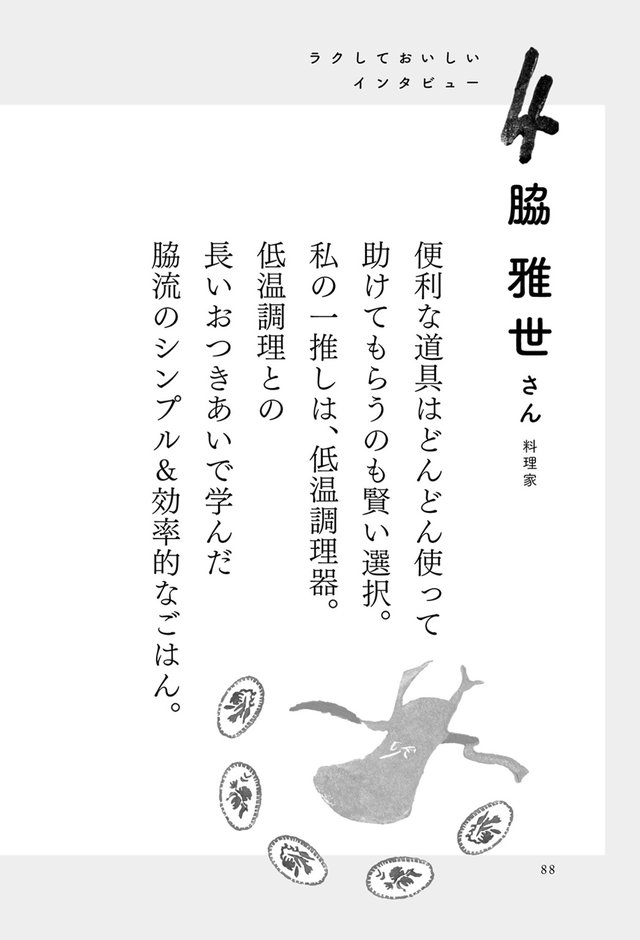
「パフォーマンスがいい食材」を選ぶとよいと言うのは小田真規子さん。
①栄養価が高い(ビタミン類、ミネラル、食物繊維などが豊富)
②調理がラク(皮をむかない、生でも食べられるなど)
③見栄えがする(ゆでて盛り付ければ格好がつくなど手をかけた感じがでるもの)
④買い物がラク(荷物が重くならないもの)
⑤日持ちがする(冷蔵庫で3日~4日は持つもの)
これら5項目をチェックし野菜を選ぶと、栄養価がアップするだけでなく、いつもと同じ料理でも見違えたり、手をかけた雰囲気になったりと、料理のモチベーションアップにもつながるそう。具体的にはパプリカ、ブロッコリー、スナップえんどう、ルッコラ、かぼちゃ(カット)、紫玉ねぎ、トマト、ミニトマトなど。
たとえば、しょうが焼きのつけ合わせを、重量のあるキャベツを買ってきて千切りするのでなく、軽いサラダ菜やルッコラにすれば、切る手間も省け栄養価もアップ。肉の場合は、鶏手羽元、手羽先などの骨つき肉やかたまり肉は、切ったり成形することなく、そのまま煮物やスープ、揚げ物にできるので、簡単で盛り付けの見栄えも良い高パフォーマンス食材だ。
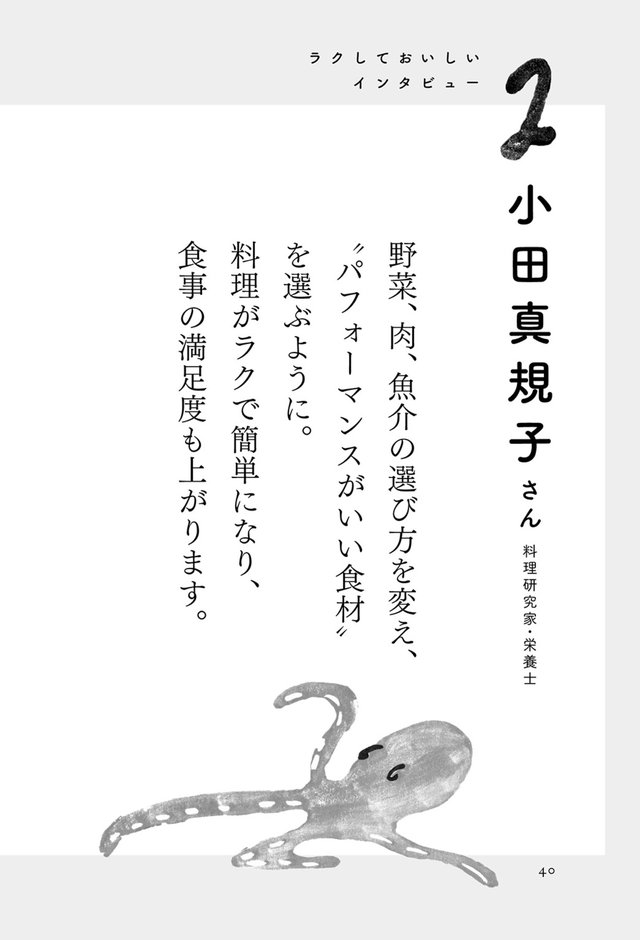
こんなふうに、献立の考え方や食材選び、便利な調理家電の活用のちょっとしたコツを知ると「料理ってこんな感じでいいのか」と、肩の力が抜けてくる。本書には、ほかにもたくさんのコツが詰まっているので、気になったものを試してみると、料理のしんどさを軽くしてくれる自分にあう方法があるはずだ。