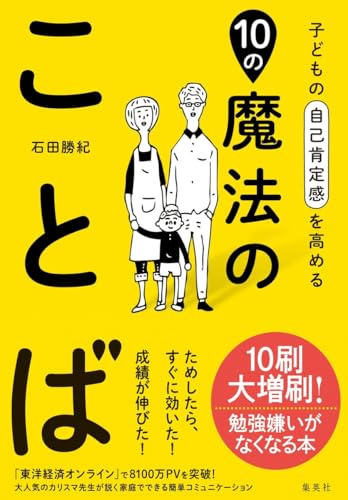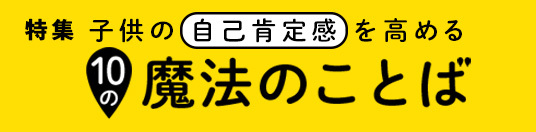「さっさと料理作れよ」「ちゃんと掃除しろよ」と言われたら… 大人だってカチンとくる言葉を子どもにも使っていませんか?/子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば⑤
更新日:2020/11/18
「早くしなさい!」「ちゃんとしなさい! 」「勉強しなさい!」子どもに向かって、毎日こんな言葉をかけてはいませんか? 実は、子どもの自己肯定感をつぶす大きな原因になっているかもしれません。親が使う言葉を変えると、子どもの自己肯定感は高まり、学力も伸びるといいます。ためしたら「すぐに効いた」「成績が伸びた」と話題の書籍から、子どもたちの自信を回復させる「魔法のことば」の一部をご紹介します。
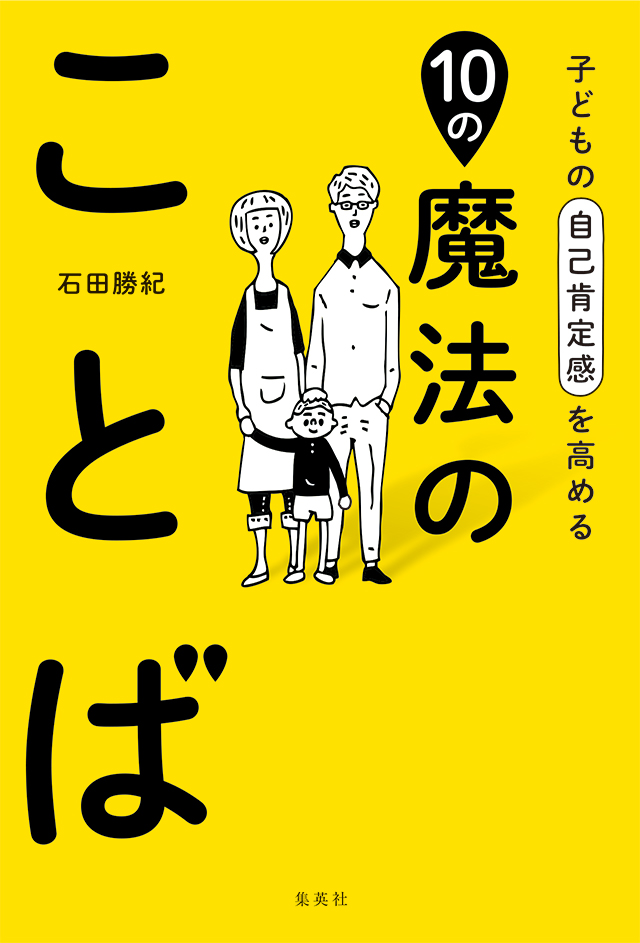
ためしに心の中で、自分に呪いの言葉をかけてみると…
もしあなたが、夫やパートナーからこんなことを言われたらどう感じるでしょうか? 想像(妄想)してみてください。
「さっさと料理作れよ」
「ちゃんと掃除しろよ」
「なんで毎日洗濯しないんだよ。するだろう、普通は」
「テレビばっかり見てないで、早く食器洗えよ」
何だか上から目線で偉そうに、ときにイライラしながら言われたとしたら? 気持ちよく家事や仕事をこなせますか?
「さっさと作ってるでしょう!」
「ちゃんとってどんな? やってるわよ」
「普通? 私には私のペースがあるのよ」
「うるさいな、このドラマを見終わったらお茶碗洗うつもりでいたのよ!」
こんなふうにカチンときませんか。やる気は削がれるし、とてもじゃないですが、いい気分ではいられないですね。
子どもたちだって、いっしょです。
上から目線の命令口調で次々と呪いの言葉をかけられた子どもたちは、カチンときてるのです。
ぜひ、ためしに上記のような擬似体験を心の中でやってみてください。
ネガティブな言葉がいかに威力があるか? 子どもたちの気持ちがちょっと、いやけっこうわかるはずです。
「今日のごはん、おいしかったよ」
「毎日、掃除してくれてありがとうね」
「いつもふかふかのバスタオルでうれしい」
呪いの言葉とは逆に、ねぎらいや感謝の言葉をかけられたら、親でも子でも夫でも妻でも、うれしいものです。
「さあ、明日もがんばろう!」と、気分上々となり、心は自然と前を向いていきます。
子どもの自己肯定感と学力を上げるためには、心がプラスで満たされていることが不可欠です。なぜなら人は心が満たされると、やりたくなかったことも「やってもいいかも」と、いい意味での「心変わり」という寛容さが出てくるのです。
言葉の力は、マイナスにもプラスにも平等に発揮されるということです。
呪いの言葉をやめるだけで、自己肯定感は上がっていきます
親が言葉の習慣を変えるだけで、子どもの学力が上がるという現実を何度も目の当たりにしてきました。
言葉で人は変われるのです。
いや、それ以上かもしれません。言葉がその人やその人の人生を作っていくのだということを、教育の現場や講演活動を通して気づかされました。
子どもはたいへん素直です。親の言葉を疑いもなく、心で受け取り、吸収します。
少し前のことですが、塾のひとりの生徒が「私は勉強ができないから」と頻繁に言い出すようになり、その言葉を追いかけるように成績が落ちていったことがありました。
心配になって、生徒のお母さんと面談したときに「うちの子は私に似て本当は勉強が苦手だから」と何度も繰り返すのを聞いて、愕然としたことを覚えています。
お母さんの「本当は勉強が苦手」という言葉が、いつの間にか子どもに刷り込まれ、その通りに現実が作られていったのです。
まさに呪いの言葉ではありませんか?
「繰り返された言葉は、その通りに実現される」
言葉は繰り返されることによって、強力な暗示となり、人間の振る舞いや考え方、果ては容姿や雰囲気にまで影響を与えます。
こう考えると、言葉とは自分そのものなのかもしれません。
コーチングの世界に「オートクライン」という用語がありますが、これは「自分が発した言葉を聞くことによる自分自身に与える影響」のことを言います。
親が子どもに言葉をかけるとき、親(本人)もまた自らが発した言葉を耳と脳で再確認し、影響を受けていることになります。
だとすると、繰り返し子どもにかけているネガティブな言葉は、もれなく親自身の体内にも入り込んで、意図しない負のメッセージを親本人にもちゃんと伝えているのです。
「みんなからバカにされるわよ」と言えば、子どももあなたも不安になる。
「そんなこともできないの?」と言えば、子どももあなたも無能になる。
「悪い子だね」と言えば、子どももあなたも悪い人になる。
親子ともどもダメになっていくという一石二鳥のマイナス版のようなものです。
「子どもを呪わば穴ふたつ」と肝に銘じて、まずは呪いの言葉をやめてみましょう。
そして、ネガティブな言葉をなるべく使わないよう意識してみてください。
呪いの言葉をやめれば、呪いはとたんに解けるものです。