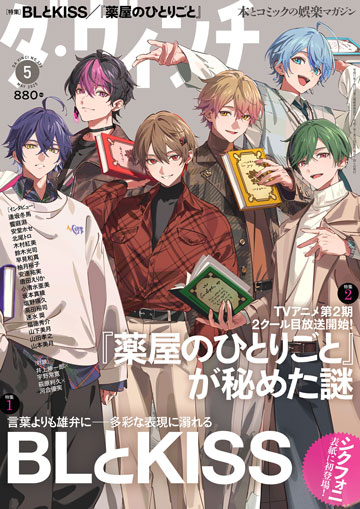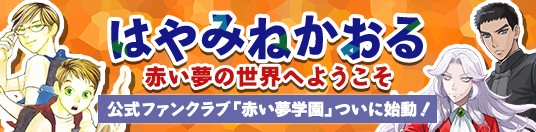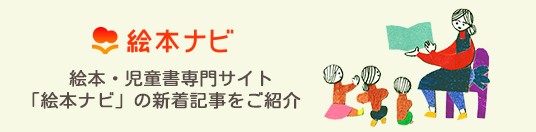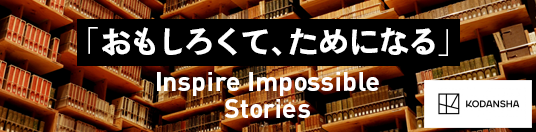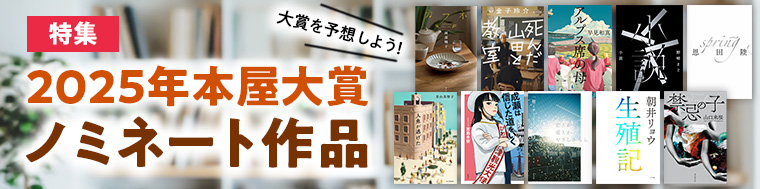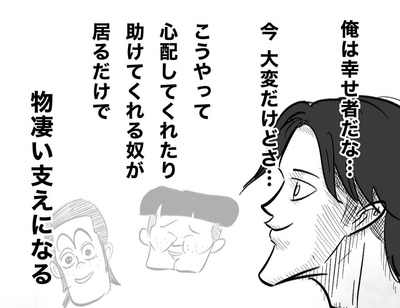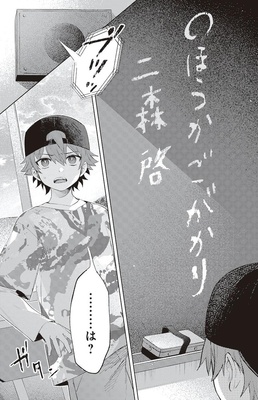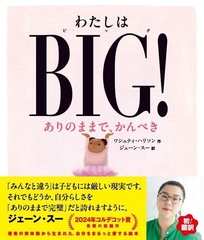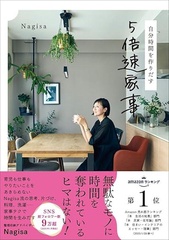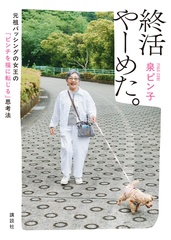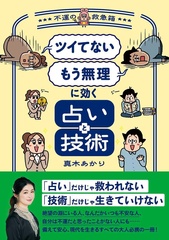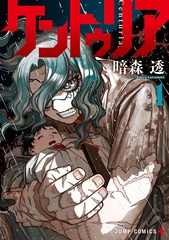小ロットの冊子やカタログの製本のお悩みを解決!三共グラフィックがポイントをお教えします!
![]() 三共グラフィック株式会社
三共グラフィック株式会社
公開日:2025/4/2
無線綴じとは?アジロ綴じとは?実は両者には違いがあります。
製本をする上での選び方や、注意点などのポイントを分かりやすくご説明します。

前回では、無線綴じとアジロ綴じの主な違いなどをお話しいたしました。
今回は無線綴じとアジロ綴じの選び方のポイントをご紹介します。
無線綴じとアジロ綴じの選び方のポイント無線綴じとアジロ綴じのどちらを選ぶかの判断材料となるポイントは、用紙の厚さや用紙の種類になります。
使用する用紙が厚く、コシの強いコート紙などの場合、本を開いた時に背部分の接着層に負荷がかかり、背割れが起こりやすくなります。背割れが起きてしまうと、無線綴じの場合、ページが1枚ずつ抜け落ちバラバラになってしまいます。アジロ綴じは、ページ同士が接着されてつながっているため、簡単にバラバラになることがありません。厚めの用紙やコシのある用紙を使用する場合は、アジロ綴じが適しているといえます。
薄い用紙を使用し、折り数が多くなると、中折の浮きが出やすくなるため糊の浸透が不十分になる可能性があります。アジロ綴じの場合、この中折の浮きが生じたまま糊を押し込むと内部まで糊が浸透しないため紙抜けのリスクが高まります。しかし、折丁の背の部分をまとめて糊で固める無線綴じであれば、そのリスクを軽減できますので、薄い紙を使用し、折り数が多くなる場合は無線綴じが適しているといえます。
デザインの注意点とチェックポイント無線綴じやアジロ綴じの印刷物を作成する場合、デザイン上で注意するポイントがいくつかあります。
背部分を糊で固める製本の仕組み上、ページの開きがあまり良くありません。そのため、ノド側に文字や写真・図柄などがあると見えづらく、読みづらいものになってしまいます。文字や写真・図柄などの配置には十分な配慮が必要です。見やすさを考えるとノド側の余白は10mm以上持たせておくのがお薦めです。また見開きで写真等を使用する場合、絵柄を合わせるためにミーリング等の調整も必要になります。
本を開いた際の外側、製本の際に断裁面になる部分を小口と呼びます。断ち落としまで絵柄がある場合、小口に“白”が出ないように絵柄を伸ばすことやデザインにズレが生じないように注意が必要です。
また、本文を表紙でくるんで製本するため、本文の厚み分だけ背ができます。使用する用紙やページ数によって背幅が変わるため、背幅をしっかりと考慮しデザインすることも必要です。
三共グラフィックの印刷と製本三共グラフィックでは、印刷から製本まで一貫して進行・品質管理することで、高品質な印刷物を納めます。70年を越える経験で培ったノウハウと細部にわたる“こだわり”の印刷と小ロットにも対応でき、新素材PO糊(ポリオレフィン糊)を使用した製本は、従来のEVA糊を使用したものより耐久性があり、開広性も良い高品質なものになります。また、通常難しいとされてきた2mm以下の薄物でも1mm以上あれば製本が可能なのも大きな特徴です。オフセット印刷+折り加工+製本を一貫した管理体制の中でお客様の期待を超える製品を実現しています。
三共グラフィックでは、高品質な印刷・製本サービスを提供しています。お客様のニーズに応じた見積もりを得るために、お気軽にお問合せください!必要な情報をご提供いただければ、迅速に正確な見積もりと適切な提案をさせていただきます!