アウティングで失われた命・事件を風化させない。地域、大学、社会は10年経った今、どう変わったか?様々な視点で綴る次世代へのメッセージ『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』発売
![]() 株式会社サウザンブックス社
株式会社サウザンブックス社
更新日:2025/8/4
株式会社サウザンブックス社
~ クラウドファンディングで250万円以上の寄付を集め、ついに書籍化。8月24日(日)から発売開始。~
世界中の価値ある本や一般読者からの希望タイトルをクラウドファンディングで出版する株式会社サウザンブックス社(東京都渋谷区、代表取締役:古賀一孝)は、2015年にアウティングがきっかけとなり失った命・事件を風化させないことを目指した書籍『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』を2025年8月24日(日)に発売します。
http://thousandsofbooks.jp/project/outing/
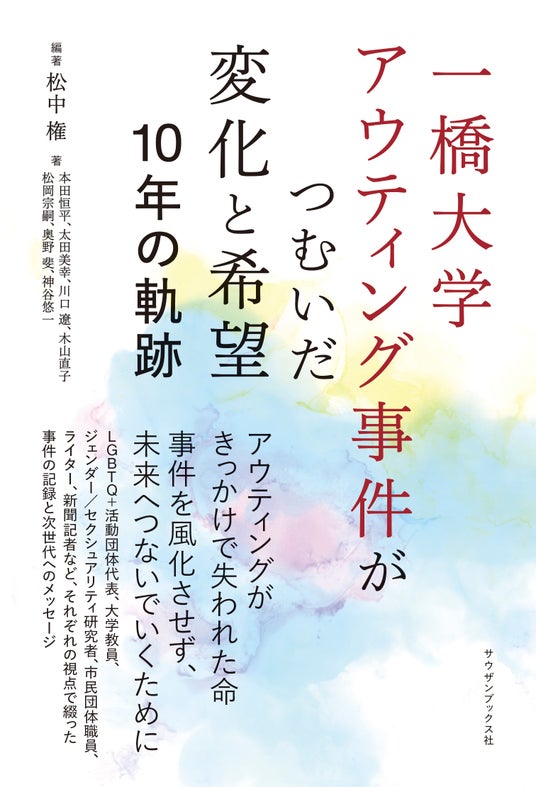
命が失われた「一橋大学アウティング事件」の風化防止へ
2015年6月、一橋大学法科大学院に通うひとりの男子学生が、同級生が参加するLINEグループにて、ゲイであることを本人の同意なく暴露(アウティング)されました。男子学生は心身の不調を訴え、大学のハラスメント相談室、担当教授、保健センターに助けを求めましたが、結果的に状況の改善がなく、同年8月24日に校舎から転落。
男子学生の命が失われてから、2025年で10年。現在では改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)でアウティングを防ぐ義務が企業に課されるなど、社会的にもプライバシーや人権への配慮が広がっています。しかし、当時は当たり前ではなく、現在の日常においてもアウティングの危険性が潜んでいます。本事件を風化させず関係者の声を形にして世の中に広く伝えるために、本書籍を出版します。
市から国へ、社会を動かすきっかけに。~日本で初めてアウティングの違法性について言及した判決とその後~
男子学生が亡くなった翌年、遺された両親は同級生と大学を相手に損害賠償を求めて提訴。遺族の請求が東京地裁・高裁ともに棄却されましたが、アウティングは「人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであり、許されない行為であることは明らか」と言及され、アウティングの違法性について日本で初めて言及された判決となりました。
そして、2018年には、一橋大学のキャンパスがある国立市で、アウティング禁止を盛り込んだ「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」が施行。2020年6月に施行されたパワハラ防止法でも、アウティング防止策を講じることが事業者に義務付けられることに。一橋大学アウティング事件は、制度を前に進め、確実に社会に変化をもたらしてきました。
変化は社会だけでなく、個々人の行動へ。10年の歴史と変化と希望を書籍化~当事者や支援者、学者、新聞記者など、8名の様々な視点から次世代へのメッセージを届ける~
その後、多くのLGBTQ+の方々がいるなかで、自らの人権が守られていないことについて、声をあげる当事者も増えてきました。また、多くの人が心を痛め「もし自分がアウティングの現場にいたら」と考えるなど、一人ひとりに何らかの意識の変化、行動の変化、描く未来への変化がもたらされています。本書の編著者でありゲイ当事者である松中氏は、当時「彼は私だ」と感じ、事件を機に電通を退社し、これまでのLGBTQ+と社会をつなぐ場づくりの活動に加えて、法整備を求める活動スタートしました。
本書の中では、男子学生の家族や友人が語る当時の想いの他、「事件報道後、大学の内部では何が始まったのか」「アウティングしてしまう側の視点」「社会に問いかけた課題と現在地」など、LGBTQ+等の性的マイノリティ当事者や支援者、学者や新聞記者など、8名の著者による様々な視点から、この10年の歴史と変化と希望について語られます。
この度、次世代へのメッセージとして届けるために、クラウドファンディングで200名以上の支援者・250万円以上の寄付が集まり出版・8月24日(日)から発売いたします。
第一章 第一章 一橋大学アウティング事件の経緯、主要な訴訟期日など(松中 権)
第二章 彼が遺した「黄色い一枚の絵」、
家族や友人の「希望」を、未来につなぐために(松中 権)
◆第二部 一 橋大学アウティング事件と大学
第三章 ハラスメントと大学と学生、―研究と教育を支える環境とは(本田 恒平)
第四章 事件報道後、大学の内部では何が始まったのか(太田 美幸)
第五章 アカデミアの宿題―アウティング事件が大学に問いかけるもの(川口 遼)
第六章 国立市の動き、くにたち男女平等参画ステーション・パラソル(木山 直子)
◆第三部 一橋大学アウティング事件と社会
第七章 『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』(松岡 宗嗣)
出版後の反応―アウティングしてしまう側の視点を考える
第八章 報道の現場から―社会に問いかけた課題と「現在地」(奥野 斐)
第九章 一橋大学アウティング事件を契機とした「アウティング」に対応する法制度の展開(神谷 悠一)
第十章 一橋大学アウティング事件から一〇年。彼が生きたいと願った未来へと、一〇年間でどこまで近づけたのか(松中 権)
付録 「彼は私」でした。一橋大学アウティング事件で、電通を辞めて向き合ったひとつの感情(松中 権)
【執筆者】
・松中 権(プライドブリッジ会長、認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表)
・本田 恒平(立教大学経済学部助教、独立行政法人労働政策研究・研修機構研究会委員、LGBTQアライ)
・太田 美幸(一橋大学大学院社会学研究科教員)
・川口 遼(社会学者、東京都立大学大学院人文科学研究科客員研究員。専門はジェンダー・セクシュアリティの社会学、男性性研究。プライドブリッジ副会長。)
・木山 直子(国立市「くにたち男女平等参画ステーション・パラソル」ステーション長)
・松岡 宗嗣(一般社団法人fair 代表理事)
・奥野 斐(東京新聞社会部記者)
・神谷 悠一(全国連合会[LGBT法連合会]代表理事。日本学術会議特任連携会員[法学委員会社会と教育におけるLGBTIの権利保障分科会構成員]。兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザープライドブリッジ副会長、一般社団法人LGBT法連合会事務局長)
◆編著 松中権氏のコメント・プロフィ―ル

「今年の8月24日で、彼が亡くなられて10年となります。節目と呼ぶのが良いのかはわかりませんが、歴史と変化と希望を、きちんと書籍としてまとめて残し、ひとりでも多くの方に、手に取っていただく機会をつくりたい。そんな想いを共有する8名が、それぞれが感じ、考え、動き、見つめてきた10年間の変化を文章に綴りました。みなさんが、経験してきた10年間の変化と、今まさに抱き、描いている希望と重ねながら読んでいただけると嬉しいです。
そして、この書籍が、一人ひとりが当然にもっている権利を勝ち取るために、次の一歩を踏み出す、みなさんの背中をやさしく支えるものとなりますように。
なお、本書は特定の個人を糾弾することは目指していません。一方で、一橋大学アウティング事件に関わるすべての人の声や思いを反映しているわけではありません。著者8人の視点でつむいだ内容であることをご理解いただけますと幸いです。」
⚫︎プロフィール
1976年、金沢市生まれ。ゲイ当事者。認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表。一橋大学法学部卒業後、2001年に電通入社。2010年にNPO法人を仲間たちと設立しLGBTQ+と社会をつなぐ場づくりの活動を展開。2016年に第七回若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞。2017年に16年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代表に。誰にとっても安心・安全な一橋大学を目指し卒業生らと「プライドブリッジ」を立ち上げる
とともに、インクルーシブな職場づくり(work with Pride)や、結婚の平等(同性婚の法制化)等にも取り組む。NHKドキュメンタリー番組『カラフルファミリー』が話題に。金沢レインボープライド 共同代表/NOTOTO.共同代表/新公益連盟 理事/東京大学総長室アドバイザー。
◆株式会社サウザンブックス社 コメント
サウザンブックス社では、世界で読まれている名著であるにも関わらず翻訳されていない本の翻訳出版や、現在の業界のしくみだけでは出版が難しい本を、クラウドファンディングを活用して出版しています。
特にLGTBQ+をテーマにした本は、新刊を中心としたマーケットに沿わず出版されていない本が多数あり、サウザンブックスPRIDE叢書シリーズとして注力し、これまでに17点を刊行して参りました。
このPRIDE叢書シリーズでは、セクシュアル・マイノリティが誇り高く生きていくための本、そして、それを応援する多くの多くの方の気持ちに届く本の出版を心がけております。
本書『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』が、LGTBQ+をとりまく環境がより改善していくことの一助になることを願い、この度、刊行いたしました。
サウザンブックス社 本書担当 古賀一孝
◆書籍概要
書名:『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』
編著:松中 権
著:本田 恒平、太田 美幸、川口 遼、木山 直子、松岡 宗嗣、奥野 斐、神谷 悠一
仕様:並製本・四六版・全1C・273頁
発行・発売:サウザンブックス社
発売日:2025年8月24日
本体価格:定価 2,300円(税別)
ISBN:978-4-909125-67-5
詳細・本書購入先URL:http://thousandsofbooks.jp/project/outing/
※報道関係者様へ
本書籍に関するご取材について、献本又は編著者へのインタビュー対応も可能です。ご希望の場合、広報窓口までお問合せください。
その他プロフィール
・本田 恒平 ほんだ こうへい
立教大学経済学部助教、独立行政法人労働政策研究・研修機構研究会委員、LGBTQアライ。専門は政治経済学、戦後労使関係・労働政策。一九九五年に東京都国立市に生まれ、二〇二四年に一橋大学大学院経済学研究科総合経済学専攻博士後期課程を修了(経済学博士)。独立行政法人労働政策研究・研修機構などを経て、現職。主な研究業績には、「1990年代外部労働市場規制緩和における『新時代の「日本的経営」』の影響力」『社会政策』(No.43、二〇二三年)や「港湾労働における労働組合の役割:全日本港湾労働組合小名浜支部の労働者供給事業を事例に」『大原社会問題研究所雑誌』(No.783、二〇二四年)、「外部労働市場規制緩和と労働組合:日経連批判言説の再考」『大原社会問題研
究所雑誌』(No.793、二〇二四年)などがある。
・太田 美幸 おおた みゆき
一橋大学大学院社会学研究科教員。専門は教育社会学、ノンフォーマル教育、比較発達社会史。編著『ジェンダー平等のまちをつくる―東京都国立市の挑戦』(新評論、二〇二五年)、『増補改訂版 ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざした教育へ』(新評論、二〇二五年)、単著『スヴェンスカ・ヘムの女性たち―スウェーデン「専業主婦の時代」の始まりと終わり』(新評論、二〇二三年)、論文「性の多様性をめぐる教育政策研究の課題」『日本教育政策学
会年報』第24巻(二〇一七年)など
・川口 遼 かわぐち りょう
社会学者、東京都立大学大学院人文科学研究科客員研究員。専門はジェンダー・セクシュアリティの社会学、男性性研究。一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学後、東京都立大学子ども・若者貧困研究センター特任助教、名古屋大学ジェンダーダイバーシティセンター特任助教などを務める。現在は、行政官として勤務しながら研究を続けている。プライドブリッジ副会長。
・木山 直子 きやま なおこ
国立市「くにたち男女平等参画ステーション・パラソル」ステーション長。他自治体の男女共同参画センター勤務を経て現職。さまざまな生きづらさに関する相談を聞き、ジェンダー平等に関する啓発事業・居場所づくりを行う。また、研修や、学校への出前授業なども積極的に行っている。令和二年から四年まで清瀬市の男女平等推進委員会委員にも参画。男子四人の子育て経験から、親たちの気づきの役に立ちたいと考えている。
・松岡 宗嗣 まつおか そうし
愛知県名古屋市生まれ。性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair 代表理事。Yahoo!ニュースやGQ、HuffPost等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房、二〇二一年)、共著に『LGBTとハラスメント』(集英社新書、二〇二〇年)など。
・奥野 斐 おくの あや
一九八三年、新潟県生まれ。東京新聞社会部記者。お茶の水女子大学卒業後、二〇〇六年に中日新聞社入社。ジェンダー、LGBTQ、子ども、保育問題を継続して取材している。LGBT法連合会の「LGBTQ報道ガイドライン」作成に参加。共著に『子どもたちにせめてもう1人保育士を―時代遅れの保育士配置基準をいますぐアップデートすべきこれだけの理由』(ひとなる書房、二〇二三年)。東京新聞有志によるポッドキャスト「新聞記者ラジオ」でも取材の裏側などを配信中。
・神谷 悠一 かみや ゆういち
性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会(LGBT法連合会)代表理事。日本学術会議特任連携会員(法学委員会社会と教育におけるLGBTIの権利保障分科会構成員)。兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、内閣府ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ構成員などを歴任。主な著書に『差別は思いやりでは解決し
ない―ジェンダーやLGBTQから考える』(集英社新書、二〇二二年)、『検証「LGBT理解増進法」―SOGI差別はどのように議論されたのか』(かもがわ出版、二〇二三年)など。
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ
~ クラウドファンディングで250万円以上の寄付を集め、ついに書籍化。8月24日(日)から発売開始。~
世界中の価値ある本や一般読者からの希望タイトルをクラウドファンディングで出版する株式会社サウザンブックス社(東京都渋谷区、代表取締役:古賀一孝)は、2015年にアウティングがきっかけとなり失った命・事件を風化させないことを目指した書籍『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』を2025年8月24日(日)に発売します。
http://thousandsofbooks.jp/project/outing/
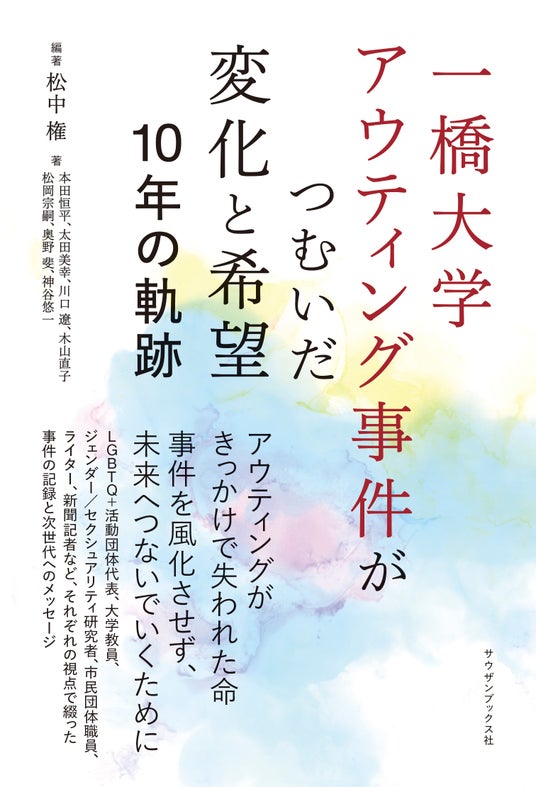
命が失われた「一橋大学アウティング事件」の風化防止へ
2015年6月、一橋大学法科大学院に通うひとりの男子学生が、同級生が参加するLINEグループにて、ゲイであることを本人の同意なく暴露(アウティング)されました。男子学生は心身の不調を訴え、大学のハラスメント相談室、担当教授、保健センターに助けを求めましたが、結果的に状況の改善がなく、同年8月24日に校舎から転落。
男子学生の命が失われてから、2025年で10年。現在では改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)でアウティングを防ぐ義務が企業に課されるなど、社会的にもプライバシーや人権への配慮が広がっています。しかし、当時は当たり前ではなく、現在の日常においてもアウティングの危険性が潜んでいます。本事件を風化させず関係者の声を形にして世の中に広く伝えるために、本書籍を出版します。
市から国へ、社会を動かすきっかけに。~日本で初めてアウティングの違法性について言及した判決とその後~
男子学生が亡くなった翌年、遺された両親は同級生と大学を相手に損害賠償を求めて提訴。遺族の請求が東京地裁・高裁ともに棄却されましたが、アウティングは「人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害するものであり、許されない行為であることは明らか」と言及され、アウティングの違法性について日本で初めて言及された判決となりました。
そして、2018年には、一橋大学のキャンパスがある国立市で、アウティング禁止を盛り込んだ「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」が施行。2020年6月に施行されたパワハラ防止法でも、アウティング防止策を講じることが事業者に義務付けられることに。一橋大学アウティング事件は、制度を前に進め、確実に社会に変化をもたらしてきました。
変化は社会だけでなく、個々人の行動へ。10年の歴史と変化と希望を書籍化~当事者や支援者、学者、新聞記者など、8名の様々な視点から次世代へのメッセージを届ける~
その後、多くのLGBTQ+の方々がいるなかで、自らの人権が守られていないことについて、声をあげる当事者も増えてきました。また、多くの人が心を痛め「もし自分がアウティングの現場にいたら」と考えるなど、一人ひとりに何らかの意識の変化、行動の変化、描く未来への変化がもたらされています。本書の編著者でありゲイ当事者である松中氏は、当時「彼は私だ」と感じ、事件を機に電通を退社し、これまでのLGBTQ+と社会をつなぐ場づくりの活動に加えて、法整備を求める活動スタートしました。
本書の中では、男子学生の家族や友人が語る当時の想いの他、「事件報道後、大学の内部では何が始まったのか」「アウティングしてしまう側の視点」「社会に問いかけた課題と現在地」など、LGBTQ+等の性的マイノリティ当事者や支援者、学者や新聞記者など、8名の著者による様々な視点から、この10年の歴史と変化と希望について語られます。
この度、次世代へのメッセージとして届けるために、クラウドファンディングで200名以上の支援者・250万円以上の寄付が集まり出版・8月24日(日)から発売いたします。
【目次】
◆第一部 一橋大学アウティング事件と家族と友人第一章 第一章 一橋大学アウティング事件の経緯、主要な訴訟期日など(松中 権)
第二章 彼が遺した「黄色い一枚の絵」、
家族や友人の「希望」を、未来につなぐために(松中 権)
◆第二部 一 橋大学アウティング事件と大学
第三章 ハラスメントと大学と学生、―研究と教育を支える環境とは(本田 恒平)
第四章 事件報道後、大学の内部では何が始まったのか(太田 美幸)
第五章 アカデミアの宿題―アウティング事件が大学に問いかけるもの(川口 遼)
第六章 国立市の動き、くにたち男女平等参画ステーション・パラソル(木山 直子)
◆第三部 一橋大学アウティング事件と社会
第七章 『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』(松岡 宗嗣)
出版後の反応―アウティングしてしまう側の視点を考える
第八章 報道の現場から―社会に問いかけた課題と「現在地」(奥野 斐)
第九章 一橋大学アウティング事件を契機とした「アウティング」に対応する法制度の展開(神谷 悠一)
第十章 一橋大学アウティング事件から一〇年。彼が生きたいと願った未来へと、一〇年間でどこまで近づけたのか(松中 権)
付録 「彼は私」でした。一橋大学アウティング事件で、電通を辞めて向き合ったひとつの感情(松中 権)
【執筆者】
・松中 権(プライドブリッジ会長、認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表)
・本田 恒平(立教大学経済学部助教、独立行政法人労働政策研究・研修機構研究会委員、LGBTQアライ)
・太田 美幸(一橋大学大学院社会学研究科教員)
・川口 遼(社会学者、東京都立大学大学院人文科学研究科客員研究員。専門はジェンダー・セクシュアリティの社会学、男性性研究。プライドブリッジ副会長。)
・木山 直子(国立市「くにたち男女平等参画ステーション・パラソル」ステーション長)
・松岡 宗嗣(一般社団法人fair 代表理事)
・奥野 斐(東京新聞社会部記者)
・神谷 悠一(全国連合会[LGBT法連合会]代表理事。日本学術会議特任連携会員[法学委員会社会と教育におけるLGBTIの権利保障分科会構成員]。兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザープライドブリッジ副会長、一般社団法人LGBT法連合会事務局長)
◆編著 松中権氏のコメント・プロフィ―ル

「今年の8月24日で、彼が亡くなられて10年となります。節目と呼ぶのが良いのかはわかりませんが、歴史と変化と希望を、きちんと書籍としてまとめて残し、ひとりでも多くの方に、手に取っていただく機会をつくりたい。そんな想いを共有する8名が、それぞれが感じ、考え、動き、見つめてきた10年間の変化を文章に綴りました。みなさんが、経験してきた10年間の変化と、今まさに抱き、描いている希望と重ねながら読んでいただけると嬉しいです。
そして、この書籍が、一人ひとりが当然にもっている権利を勝ち取るために、次の一歩を踏み出す、みなさんの背中をやさしく支えるものとなりますように。
なお、本書は特定の個人を糾弾することは目指していません。一方で、一橋大学アウティング事件に関わるすべての人の声や思いを反映しているわけではありません。著者8人の視点でつむいだ内容であることをご理解いただけますと幸いです。」
⚫︎プロフィール
1976年、金沢市生まれ。ゲイ当事者。認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表。一橋大学法学部卒業後、2001年に電通入社。2010年にNPO法人を仲間たちと設立しLGBTQ+と社会をつなぐ場づくりの活動を展開。2016年に第七回若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞。2017年に16年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代表に。誰にとっても安心・安全な一橋大学を目指し卒業生らと「プライドブリッジ」を立ち上げる
とともに、インクルーシブな職場づくり(work with Pride)や、結婚の平等(同性婚の法制化)等にも取り組む。NHKドキュメンタリー番組『カラフルファミリー』が話題に。金沢レインボープライド 共同代表/NOTOTO.共同代表/新公益連盟 理事/東京大学総長室アドバイザー。
◆株式会社サウザンブックス社 コメント
サウザンブックス社では、世界で読まれている名著であるにも関わらず翻訳されていない本の翻訳出版や、現在の業界のしくみだけでは出版が難しい本を、クラウドファンディングを活用して出版しています。
特にLGTBQ+をテーマにした本は、新刊を中心としたマーケットに沿わず出版されていない本が多数あり、サウザンブックスPRIDE叢書シリーズとして注力し、これまでに17点を刊行して参りました。
このPRIDE叢書シリーズでは、セクシュアル・マイノリティが誇り高く生きていくための本、そして、それを応援する多くの多くの方の気持ちに届く本の出版を心がけております。
本書『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』が、LGTBQ+をとりまく環境がより改善していくことの一助になることを願い、この度、刊行いたしました。
サウザンブックス社 本書担当 古賀一孝
◆書籍概要
書名:『一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡』
編著:松中 権
著:本田 恒平、太田 美幸、川口 遼、木山 直子、松岡 宗嗣、奥野 斐、神谷 悠一
仕様:並製本・四六版・全1C・273頁
発行・発売:サウザンブックス社
発売日:2025年8月24日
本体価格:定価 2,300円(税別)
ISBN:978-4-909125-67-5
詳細・本書購入先URL:http://thousandsofbooks.jp/project/outing/
※報道関係者様へ
本書籍に関するご取材について、献本又は編著者へのインタビュー対応も可能です。ご希望の場合、広報窓口までお問合せください。
その他プロフィール
・本田 恒平 ほんだ こうへい
立教大学経済学部助教、独立行政法人労働政策研究・研修機構研究会委員、LGBTQアライ。専門は政治経済学、戦後労使関係・労働政策。一九九五年に東京都国立市に生まれ、二〇二四年に一橋大学大学院経済学研究科総合経済学専攻博士後期課程を修了(経済学博士)。独立行政法人労働政策研究・研修機構などを経て、現職。主な研究業績には、「1990年代外部労働市場規制緩和における『新時代の「日本的経営」』の影響力」『社会政策』(No.43、二〇二三年)や「港湾労働における労働組合の役割:全日本港湾労働組合小名浜支部の労働者供給事業を事例に」『大原社会問題研究所雑誌』(No.783、二〇二四年)、「外部労働市場規制緩和と労働組合:日経連批判言説の再考」『大原社会問題研
究所雑誌』(No.793、二〇二四年)などがある。
・太田 美幸 おおた みゆき
一橋大学大学院社会学研究科教員。専門は教育社会学、ノンフォーマル教育、比較発達社会史。編著『ジェンダー平等のまちをつくる―東京都国立市の挑戦』(新評論、二〇二五年)、『増補改訂版 ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざした教育へ』(新評論、二〇二五年)、単著『スヴェンスカ・ヘムの女性たち―スウェーデン「専業主婦の時代」の始まりと終わり』(新評論、二〇二三年)、論文「性の多様性をめぐる教育政策研究の課題」『日本教育政策学
会年報』第24巻(二〇一七年)など
・川口 遼 かわぐち りょう
社会学者、東京都立大学大学院人文科学研究科客員研究員。専門はジェンダー・セクシュアリティの社会学、男性性研究。一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学後、東京都立大学子ども・若者貧困研究センター特任助教、名古屋大学ジェンダーダイバーシティセンター特任助教などを務める。現在は、行政官として勤務しながら研究を続けている。プライドブリッジ副会長。
・木山 直子 きやま なおこ
国立市「くにたち男女平等参画ステーション・パラソル」ステーション長。他自治体の男女共同参画センター勤務を経て現職。さまざまな生きづらさに関する相談を聞き、ジェンダー平等に関する啓発事業・居場所づくりを行う。また、研修や、学校への出前授業なども積極的に行っている。令和二年から四年まで清瀬市の男女平等推進委員会委員にも参画。男子四人の子育て経験から、親たちの気づきの役に立ちたいと考えている。
・松岡 宗嗣 まつおか そうし
愛知県名古屋市生まれ。性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair 代表理事。Yahoo!ニュースやGQ、HuffPost等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房、二〇二一年)、共著に『LGBTとハラスメント』(集英社新書、二〇二〇年)など。
・奥野 斐 おくの あや
一九八三年、新潟県生まれ。東京新聞社会部記者。お茶の水女子大学卒業後、二〇〇六年に中日新聞社入社。ジェンダー、LGBTQ、子ども、保育問題を継続して取材している。LGBT法連合会の「LGBTQ報道ガイドライン」作成に参加。共著に『子どもたちにせめてもう1人保育士を―時代遅れの保育士配置基準をいますぐアップデートすべきこれだけの理由』(ひとなる書房、二〇二三年)。東京新聞有志によるポッドキャスト「新聞記者ラジオ」でも取材の裏側などを配信中。
・神谷 悠一 かみや ゆういち
性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会(LGBT法連合会)代表理事。日本学術会議特任連携会員(法学委員会社会と教育におけるLGBTIの権利保障分科会構成員)。兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、内閣府ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ構成員などを歴任。主な著書に『差別は思いやりでは解決し
ない―ジェンダーやLGBTQから考える』(集英社新書、二〇二二年)、『検証「LGBT理解増進法」―SOGI差別はどのように議論されたのか』(かもがわ出版、二〇二三年)など。
企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ
