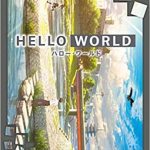一見正しいけれど……? ダウンロード違法化、コンビニからの「成人誌」の排除
更新日:2019/2/7
■「ダウンロード違法化の拡大」がもたらすもの
文化庁は1月25日に「海賊版ダウンロードの違法範囲をネット上の全てのコンテンツに拡げる」とした意見の最終取りまとめを行った。審議会に参加していた有識者の多くから異論や慎重論が出されたにもかかわらず、国会への著作権法改正案の提出を優先させた形だ。
これまでもすでに音楽や映画については海賊版と知りながらダウンロードを行った場合は違法だった。それがあらゆるネット上の静止画=写真・マンガ・イラスト・雑誌・論文・アイコン画像などに範囲が拡大される可能性が高まっている。さらに、文化庁は、罰則(懲役2年以下・200万円以下)も設けたい考えだ。
「海賊版だと知ってのダウンロードだからやむを得ないのでは?」と思う読者もいるかも知れない。しかし、この違法化は強い「副作用」を生むことが懸念されている。竹宮恵子氏が会長を務める日本マンガ学会が1月23日に発表した反対声明では大きく2つの点が指摘されている。
●二次創作のダウンロードまでも禁止される恐れ
→ネット上でも生み出される二次創作は、コミケに象徴されるように日本で多様なコンテンツが生まれる源泉となっている。その利用に萎縮効果がもたらされてしまっては、著作権が本来目的とする「文化の発展」が損なわれてしまう。
●研究や創作のための「記録」までも禁止される恐れ
→ネット上に存在する静止画はその出所が不明なものも少なくない。そういったコンテンツを画面キャプチャなどで記録することも「違法」となってしまっては、研究や創作が円滑に行なえなくなる恐れが出てくる。
このダウンロード違法化は、先日法制化が見送られたサイトブロッキングに代わるものとして、文化庁や権利者団体がその実現を目指しているという見方もある。しかし、サイトブロッキングの大きな根拠となっていた漫画村はすでに運営されておらず、反対声明でも指摘されているように、同種のサイトもそこで行われているのはダウンロードではなく、ストリーミング型のサービスがほとんどだ。静止画のダウンロードを違法化したところで、対策にならないという声は大きい。
そもそも本来は著作権を守ってほしい立場の漫画家とも関係が深い団体から、このような反対声明が出てきているということは重い意味を持つ。議論の場は審議会から国会に移るが、「海賊版対策」といった一見分かりやすいが、副作用を生みかねない誤った理解のもとでの検討とならないよう注視していく必要がある。
■コンビニからの「成人誌」の排除は正しい?
このダウンロード違法化の拡大でネット上で議論が噴出していたころ、コンビニ各社(セブン-イレブン・ローソン・ファミリマート)が「成人向け雑誌」の販売を取りやめることを表明している。
こちらの記事でも取り上げたように、そもそも日本では「ポルノ」は解禁されておらず、何をもって「成人向け」とするのかは曖昧なのだが、いずれにせよ、これまでも店頭では一般向け雑誌との間に「柵」を立てたり、立ち読みができないような処理を施すなどして、いわゆる「ゾーニング」が行われてきた。
今回のこの販売の取り扱い中止については、日本雑誌協会からは「範囲が不明確」だとして写真週刊誌などにも影響が拡がることを懸念する声が上がっている。ただでさえ雑誌の販売が減少を続けるなか、貴重な販路であるコンビニでの取り扱い中止の範囲が拡がれば、大きな影響が及ぶのは想像に難くない。
たしかに、表紙の過激さを競うかのような(実際には自主的に露出は過去に比べて抑えられているのだが)「成人誌」は、整然・清潔なコンビニ店舗のなかでは異質な存在とはなっていた。そして、スマホ・タブレットでの雑誌購読が拡がる中、かつてはコンビニを象徴していた雑誌コーナーの縮小が続いている。今回の各社の判断はそんな変化を受けてのものであったかも知れない。
しかし一方で、その範囲が不明確なまま一気に取り扱いの停止というところまで至ったことには違和感もある。たとえば、表紙をフィルムで覆ったり、タバコのようにカウンターの中において販売したりという選択肢はなかったのだろうか? あるいは店舗の立地ごとに判断があってもよかったかも知れない。「成人誌」は、かつて映画業界がそうであったように、新人漫画家やライターが原稿料を得ながら商業媒体で腕を磨く貴重な場でもあり、ここから一般誌への転進を果たした描き手も少なく無い。そんな場が今回の決定で大きく縮小されてしまう恐れが出てきた。
「海賊版対策」「成人誌の排除」といった、一見正しいようで実は副作用がある短絡的な判断がこのところコンテンツ政策の分野で続いている。筆者も含め、業界関係者のみならずコンテンツの受け手である読者も違和感や危機感を様々な場で表明していく必要があるだろう。
文=まつもとあつし
まつもとあつし/研究者(敬和学園大学人文学部准教授/法政大学社会学部/専修大学ネットワーク情報学部講師)フリージャーナリスト・コンテンツプロデューサー。電子書籍やアニメなどデジタルコンテンツの動向に詳しい。atsushi-matsumoto.jp