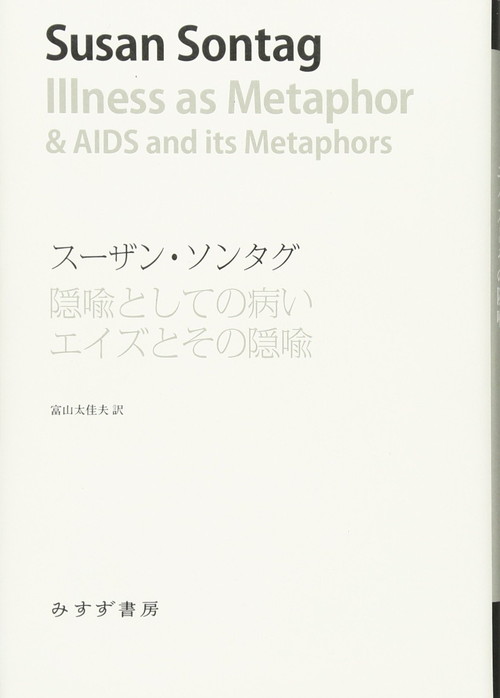新型コロナウイルスも、感染者も“悪”ではない。病の隠喩によって奪われる人間の尊厳【読書日記18冊目】
公開日:2020/4/27
2020年4月某日
怒り狂っていた。
感染した人間に申し訳なさを抱かせる空気に。
強まる同調圧力に、相互監視に。「人間vs.ウイルス」「ウイルスに打ち勝とう」「みんな一致団結して頑張ろう」といったスローガンのもと、「自粛」の「要請」に「従わない」人をさも「思いやりのない」人間かのように仕立てる空気に、「声かけ」と称して自由を抑圧する権力に、怒りや思想の表明を強要する人間たちに。
何もかもを「敵」「味方」のふたつに分かつ人間に、勝手に期待しておきながら問題が起きると崇拝していたはずの存在に平気で罵詈雑言を浴びせる人間に、他人を攻撃しないと自分を保てない人間に、大上段から他人を断罪する人間に、自己責任論に終始させる人間に、それらを強さだと思っている人間に。
あらゆる怒りを身体が割れんばかりに溜めても、それを発露させる余力さえない非力な人間の私に。

疫病が蔓延し始めたことを知ったのは1月末で、それも知人づてに聞いたのだった。「インフルエンザが流行っているみたいなのでお気をつけてくださいね」とメールをしたら、もらった返事に「新型肺炎も流行っているそうですからご用心ください」と書かれていて、はて何のことだろうと思ったのを今でも覚えている。それからウイルスの蔓延によって、世の中の情勢やムードは瞬く間に変わっていき、不安が世の中を塗りつぶし、怒りが、苦しみが、あちこちで噴出した。
SNSでは「まるで戦時中のようだ」といった言葉が飛び交い、感染により亡くなった人について「あの人の死を無駄にしてはいけない」と団結を呼びかける。国や政府による干渉を拒んでいたはずの人たちさえも、猛烈な勢いでロックダウンを求め始めた。それぞれに様々な事情や背景があってのことだろう。しかし、それこそ、立ち行かなくなった現在の突破口を「戦争」に見出す動きに酷似しているようで怖くなる。
ウイルスそれ自体よりも社会の流れに恐怖を感じていた。政治そのものだけではなく、身近な人を含めた世の中全体について。殺伐としたSNSのタイムラインといった直接的なことだけでなく、何かもっと、大きくて、目に見えぬ、グロテスクな蠢きが私を「侵して」いるのを感じていた。
*
3月中頃だったか、私が盟友と呼んで慕っている友人が、Twitterで「これを読み返すなら今かな」と、ある本について紹介していた。その友人は私が4年以上前から大変世話になっている方で、彼女の勧めてくれる本や紹介してくれる人はもれなく大事な存在になるので、彼女自身はもちろん、その審美眼をとても信頼している。
ツイートを見てすぐに購入したのだけれど体調が悪くて活字を目で追えず、読み始めたのは4月も中旬に差しかかった頃。しかし、読み始めてすぐに知りたかったことが書かれていると察し、時間も忘れて読みふけっていたら朝が来ていた。その本は、スーザン・ソンタグの『隠喩としての病い エイズとその隠喩』(みすず書房)だった。
この本は、タイトルにもある「隠喩としての病い」と「エイズとその隠喩」の2編のエッセイが収録されており、そのテーマと主張は単純明快。“隠喩”として使用された病をテーマに、隠喩がらみの病気観を一掃するべきだということが徹頭徹尾唱えられている。
「隠喩としての病い」ではペストや梅毒などと比較されながら「結核」と「癌」がもつ「隠喩」の特異性が説かれる。原因や治療法が解明されていなかった結核や癌が「神話化」され、身体の病気なのにも拘わらず、「情熱的な人」「無法者」「人生の敗者」などと精神分析的なイメージが付与されてしまう事例とその害悪が、詩や小説、戯曲、政治家の言葉などを引用しながら紹介される。執拗にも思えるほど大量の事例が列挙されたテキストからはペン先が潰れんばかりの筆圧と著者の怒り、書き手としての使命感を受け取らずにはいられない。
これほどまでに著者が力を込めて語る背景には、乳癌が発見された著者自身の切実な体験もあるだろう。ソンタグは当時のことについて、「最初に思ったのは、こんな目にあうなんて私は何をしたんだろうということ。私は人生を間違えた。自分を抑圧しすぎた、ということ」と話しており、作中でもこう語っている。
“私の目標は、何よりもまず実践的なものであった。癌になるという体験を歪めてしまう隠喩的な附属品がきわめて重大な結果をもたらすということ、そのために人々は早期に治療を受けたり、十分な治療を受けるためにいっそう努力したりするのを尻込みするのだということを、私は何度も目にして、暗澹たる想いにとらわれたからである。隠喩と神話は人を殺す、私はそう確信した。”
隠喩とその害悪については列挙すればキリがないが、そのひとつに「病気懲罰説」がある。
表向きには病気自体が悪者にされるが、病気の心因説では罹患するのも、回復するのも最終的には病人の責任とされる。件のウイルスによる発症が心の弱さから来ていると思っている人はいないだろうが、その原因を「自己管理のなさ」に担わせている人もいるのではないか。
おまけに、治療法がわからない病気は、「汚染」「弱さ」などといったイメージと同一視され、その名前に関連するものが恐怖の対象にされる。したがって件のウイルスを悪魔視することは、感染した患者の悪魔視や、当事者を病気の症状とは別のところで追い詰めることと、ほぼイコールであると言っていい。
また、エイズの隠喩について書かれた「エイズとその隠喩」の中では、病気に対して社会全体で「戦いを挑む」ことが、患者を追い詰めることに直結するとも書かれている。
“要するに、戦争というものが集団のイデオロギー的動員のための機会になってくると、「敵」の打倒を目標としてかかげる改善キャンペーン全体に使える隠喩として、戦争という概念が有効になってくるのである。(中略)総力戦では、支出も総力になる、打算は無用――戦争とはいかなる犠牲もあたりまえのものになる緊急事態なのだから。しかし病気に対する戦争は、研究にもっと熱意を、もっとお金をという掛け声にはとどまらない。(中略)病気をデーモン化する発想から、患者に罪をきせる方向への移行は必然である。患者を犠牲者とみることなど平気なのだ。もちろん無垢だからこそ犠牲者ということになるのだが、すべての関係概念を支配する鉄則によれば、無垢は罪につながる。”
つまり、「人間vs.ウイルス」という構図や「打倒ウイルス」というスローガン自体が、患者に罪をきせることになりかねない。実際に、自分の治療に専念していいはずの患者が世の中に向かって感染を報告し、謝罪しなければならない状況ができあがってしまっている。死んだ人間が急に崇め奉られることはよくあることだが、感染による著名人の死を「無駄にするな」という呼びかけは、戦争による死者の英雄視と何が違うのだろうか。「ウイルスに打ち勝とう」というスローガンが叫ばれる中、亡くなった人は実質的に「負けた」ことにならないか。
ウイルスはウイルスとして存在し、ウイルスとしての生を全うしているのみだ。私たちがやるべきことは事実に基づいた適切な対処と行動。「戦争」という概念に翻弄されてはいけない。これは「戦争」ではない。
*
この本を読んで、私が感じていた目に見えぬ、グロテスクな蠢きの正体がわかった。存在していないはずの「神話」あるいは「イメージ」、そしてそれらに人々が翻弄されていることである。
ウイルスは悪ではない、感染した人も悪ではない、自粛要請下で外出ないし営業することも悪ではない、もちろん在宅している人も悪ではない、異議を申し立てることが悪いと言っているわけではない、しかし事実ではない「イメージ」に翻弄されてはいけない、これはウイルスとの戦いではない、戦争ではない。言葉を、意味が持つ力を、侮ってはいけない。
「隠喩は暴露し、批判し、追求し、使い果たさねばならない」とソンタグは言う。
ウイルスは人を殺すかもしれないが、病にまとわりつく言葉やイメージは人を形容詞化し、人の尊厳を奪う。感染した瞬間から人は恐怖の数字としてカウントされ、隠喩の恐怖に憑かれた人間は我を忘れて個性を失い、おしなべて同じ姿かたちになっていく。そのことに、存在もしない意味に、神話に、イメージに、隠喩に、私は憤っている。怒りにうち震えている。
自分が人間であることを誇りに思ってなどいない。
しかし、他の生を生きられない以上、命あるうちは、少なくとも私は固有の人間でありたい。
文=佐々木ののか バナー写真=Atsutomo Hino 写真=Yukihiro Nakamura
【筆者プロフィール】
ささき・ののか
文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。Twitter:@sasakinonoka