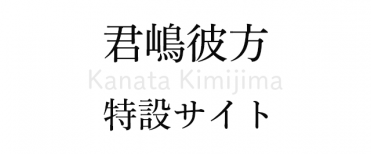勢いにまかせて、二年付き合っている彼女を実家に誘う 【君嶋彼方『一番の恋人』試し読み(4/6)】
公開日:2024/6/6
プロポーズの返事は衝撃的なものだった。
「好きだけど、愛したことは一度もない」
二年付き合った恋人は、恋愛感情も性的欲求も抱かない人だったのだ――。
『君の顔では泣けない』で鮮烈なデビューを飾った君嶋彼方さんの長編三作目の試し読みを大ボリュームでお楽しみください。
君嶋彼方『一番の恋人』試し読み(4/6)
服を着込んでサウナを出る。せっかく汗を流したばかりだというのに、外は熱気と湿気が漂っていて、飲み屋へ向かうまでの間でまたじっとりと汗をかき始めていた。柳瀬もあちいあちいと言いながら、額や首筋の汗をハンカチでひたすら拭いている。
「あのー、すみません」
唐突に声をかけられ、振り向く。お
「ちょっと道に迷っちゃって……駅ってどっち方向か分かりますか?」
「ああ、駅ですか」
僕は手振りを加えながら駅への道を説明する。彼女たちは理解してくれたようで、「ありがとうございました!」とそれぞれぺこりと頭を下げた。
それじゃあ、と踵を返そうとすると、背の低い方が僕の方をじっと見ながら、「お兄さんって、誰かに似てますよね」と言ってくる。
「あ、分かる! あの人でしょ」と背の高い方が人気の若手俳優の名前を挙げると、「そうそう! その人!」と二人ではしゃぎ始める。どんなリアクションを取っていいか分からず、作り笑いを浮かべてその様子を眺める。
「お兄さんたち、お時間ありますか? 良かったら私たちと一緒に飲みません?」
背の低い方が僕らに尋ねてくる。あー、と僕は耳の裏をぽりぽりと
「ごめんなさい。今から二人だけで飲みに行くつもりだったので。一応お店も予約してて」
そう答えると、えーそっかー残念、と二人は口々に言い、それじゃあと去って行った。僕も会釈を返し、飲み屋への道を再び歩き始める。
「あの二人、結構可愛かったな」
ぽつりと柳瀬が言った。隣を見ると、不満げに唇を突き出している。
「え! もしかして、一緒に飲みたかった?」
「別にそういうわけじゃないけどさあ」
「悪い、せっかく久々に二人で飲めるしと思って……」
「いいんだって! どうせあの子たち、お前のことしか見てなかっただろ」
「え、そうか? 一緒に飲もうって言ってたじゃんか」
「そんなの口実だっての! 二人ともお前目当てだよ」
「えー。そうかなあ」
「うるせえな! そうなの!」
柳瀬がふざけて僕にどんと体当たりしてくる。「何すんだよー」と負けじと僕も体当たりし返す。そうやって横並びで体をぶつけ合いながら、僕たちはげらげらと笑って飲み屋へと向かっていった。
地下鉄を使って帰る柳瀬と別れ、僕はJRの駅へと向かう。何の気なしに空を見上げると、高く並んだビルの隙間から、月が出ているのが見えた。立つ位置をずらして、全体が見えるようにする。まんまるで大きな満月が、真っ黒な空の中に浮かんでいた。
僕はスマホを取り出し、写真を撮る。千凪とのラインを開く。【おしり】というメッセージが入っていた。仕事が終わった、の意だ。お仕事終わり、を簡略化していった結果「おしり」という言葉になり、僕らは仕事が終わるとそう送り合うのが習慣化していた。
お疲れ様、を簡略化した【つー】の二文字を打ち、続けて月の写真とメッセージを送ろうとしたとき、千凪からメッセージが来た。
【今日、月やばくない?】
続けて、月の写真が送られてくる。僕のよりもはっきり大きく映った満月だった。僕は思わずにやけそうになる口元を手で隠しながら、返事をする。
【すごい、かぶった、俺も今ちょうど送ろうとしてた!】
【え、ほんと? すごい!】
僕はそのまま千凪のアイコンをタップすると、通話ボタンを押して耳に当てた。コール音はすぐにやみ、千凪の声が聞こえてくる。
「どうしたの? 電話なんて珍しいね」
「うん。なんか、急に声聞きたくなって」
何それ、と千凪が笑う。妙だと思われているんだろう。僕は元々電話が得意ではなくて、緊急時や用件があるときにしかしない。
「飲みの帰り? 柳瀬くんだっけ?」
「うん、そう。さっき解散して駅に向かってるところ。千凪は? 何してたの?」
「私はね、ペディキュア塗ってた」
「ペディキュア? って何だっけ?」
「足に塗るマニキュア。夏はさ、サンダル履く機会が多いから」
「そっか。楽しみにしてる」
「ん。ありがと」
ゆっくりと歩く僕の脇を、人々が忙しなく通り過ぎていく。酔いのせいか、熱帯夜のせいか、妙な高揚感に包まれて頭がふわふわしている。やがて駅に着き、僕は改札の横の柱にもたれかかる。
「実はさ、千凪にお願いがあって」
「えっ、なになに、怖い怖い」
「大丈夫、怖くないって。……あのさ、よかったら、来月俺の実家に一緒に来てくれないかな」
沈黙。電話の向こうで息を
「ごめんごめん、急すぎたよね」
僕は慌てて謝る。頭の中で伝えるべき言葉を整理して、ゆっくりと息を吐いた。
「あんまり重く受け止めないでほしいんだ。そんなに特別な意味はなくて。前からさ、家族から彼女の顔を見たいってしょっちゅう言われてたんだ。多分、俺が千凪の話ばっかするからだと思うんだけど。だからさ、一度でもいいから、顔を見せてあげたいなって思って」
千凪は沈黙したままだ。失敗したな、どうしよう、と首筋を搔きむしっていると、「いいよ」と小さな声が返ってきた。
「えっ? 何て?」
「いいよ。私も、番ちゃんの親御さん、会ってみたいし」
ほっと胸を撫で下ろす。柱に預けていた背を正し、スマホを持つ手を入れ替える。
「よかった。でも、無理させてない?」
「ううん、大丈夫。番ちゃんにも、私のお母さんに会ってもらってるわけだしね」
以前、実家住まいの千凪を家まで送っていったとき、たまたま千凪の母親と鉢合わせたことがある。数分立ち話をしただけだったが、ものすごく緊張してしまった。
「ごめんね、ありがとう。じゃあ家族には、来月千凪も連れてくって伝えておく」
「うん。よろしくね」
おやすみ、と言い合って、電話を切る。深く息を吐いて、空を見上げる。月は駅やビルに遮られて、切り取られた闇しか見えない。
千凪は今から緊張しているだろうか。そう考えると少し申し訳なかったが、でも千凪を、自分の大好きな人を家族に紹介できることに喜びを感じているのも事実だった。
番ちゃん、と僕を呼ぶ千凪の声が耳の奥に
一番、という父の願いと期待が込められた名は、嬉しくもあったが重圧でもあった。何事にも一番になれるように。でも、全てのことで一番になるなんて、無理だ。
だから千凪に番ちゃんと呼ばれると安心できた。自分は何番でもいいのだと、許してもらえている気がした。
その日は灰色の雲が空をぶ厚く覆っていて、暑さはいつもより和らいでいた。電車の冷房もきちんと効いていて、寒いくらいだ。けれどさっきから、耳の後ろ辺りから冷えた汗が垂れ続けている。緊張から来るものだと自分でも分かっていた。指の腹で
「緊張してるね」
湿った指をズボンで拭いながら「分かる?」とぎこちなく笑みを返す。
「だって口数少ないもん、さっきから。しかも、家に近付くにつれてどんどん
「千凪には隠しごとできないなあ」
冗談めかしてみるが、やはり頰は固まったままだ。きっと千凪の方が緊張しているに違いないのに。もし、自分が千凪の実家に行くことになったら、と考えてみる。確か母親と二人で暮らしていて、妹が一人いると聞いた。一体どんな会話が繰り広げられるのだろうかと想像してみる。
僕は千凪の母親に頭を下げる。お嬢さんとお付き合いさせていただいてます、道沢一番と申します。千凪の母親が訊いてくる。うちの娘を選んだ理由はなんですか。あなたが娘と付き合うことで娘は幸せになれますか。これじゃあ、まるで就活だ。うちの会社を選んだ理由はなんですか。あなたがうちの会社に入ることでメリットはありますか。
そもそも、娘が彼氏を連れてきて喜ぶ親はあまりいないだろう。僕はお宅の娘さんとセックスしています。そう宣言しにいくようなものじゃないか。
「でも、分かるよ。私ももし、番ちゃんを自分の実家に連れてくことになったら、絶対緊張するもん」
千凪も同じ想像を巡らせていたのか。なんだか嬉しくなって、頰が少し緩む。
「やっぱそう?」
「うん。番ちゃんほどじゃないとは思うけどね。自分の家族を見られるってことは、自分の内臓を見せるみたいなものだから」
内臓。少しグロテスクな響きの単語を、僕は
「お母さんがいて、妹がいて、もう今はいないけど、お父さんがいて。その家族の中で、私は形作られてきたってことでしょ。それって、内臓みたいなものだなって」
「なるほど。ちょっと変わった考えだけど、なんか納得」
僕という人間の中に、父や母や兄が、内臓のように存在している。そう思うとぞっとするが、でもきっとそれは間違いではない。家族だけではない、今まで出会ってきた人や環境が、あらゆる臓器になって、僕を生かし、
「うちの家族は、正直言うと、そんなに胸張って紹介できるような感じじゃないんだけど。でも、それでも私の内臓だから。だから、番ちゃんにいつか解剖してもらわなきゃ」
「解剖かあ」まるで医者が手術をするように、右手を何か
「メスでしゅっと、ってやつか」
「そう、メスでしゅっと。それで、私のことを番ちゃんにもっと知ってほしいって思ってる。きちんと伝えなきゃって思ってる。その中身が、どんなにえぐいとかグロいとかって思われてもいいから、全部」
もっと知ってほしい。その言葉を頭の中で
「そっか。じゃあ、千凪にも俺の内臓をきちんと見せないとな」
「そうだよ。じっくり観察するからね、覚悟してね」
「うわー。頑張ります」
そんなことを話しているうちに、耳の後ろから垂れていた汗はすっかり乾いていた。最寄りの駅まで、あと二駅だ。
「ちなみにさ。千凪の内臓の一部に、俺はいてくれてますか?」
「もちろん。小腸あたりかな」
「小腸かぁ」
そう言って笑い合う。
僕にとっての千凪は一体何なんだろうと考えてみて、すぐにその答えは出てくる。心臓。
僕の中を時折駆け巡る、
僕にとって、千凪は心臓だ。
(つづく)
作品紹介
一番の恋人
著者 君嶋 彼方
発売日:2024年05月31日
『君の顔では泣けない』の著者が描く、恋愛を超える愛の物語
道沢一番という名前は、「何事にも一番になれるように」という父の願いで付けられた。
重荷に感じたこともあったが、父には感謝している。「男らしく生きろ」という父の期待に応えることで一番の人生はうまくいってきたからだ。
しかし二年の交際を経て恋人の千凪にプロポーズしたところ、彼女の返事は「好きだけど、愛したことは一度もない」だった――。
千凪はアロマンティック・アセクシャル(他人に恋愛感情も性的欲求も抱くことがない性質)で、長年、恋愛ができないが故に「普通」の人生を送れないことに悩み、もがいていたのだった。
千凪への思いを捨てられない一番と、普通になりたい千凪。恋愛感情では結ばれない二人にとっての愛の形とは。
詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000035/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら