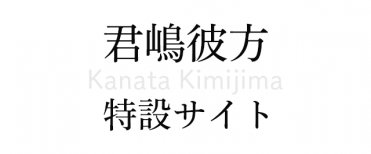父の口から、衝撃の発言が飛び出した―― 【君嶋彼方『一番の恋人』試し読み(5/6)】
公開日:2024/6/7
プロポーズの返事は衝撃的なものだった。
「好きだけど、愛したことは一度もない」
二年付き合った恋人は、恋愛感情も性的欲求も抱かない人だったのだ――。
『君の顔では泣けない』で鮮烈なデビューを飾った君嶋彼方さんの長編三作目の試し読みを大ボリュームでお楽しみください。
君嶋彼方『一番の恋人』試し読み(5/6)
実家のチャイムを鳴らす。
インターホンから、「はい」と余所行きの母の声が聞こえてくる。硬さを帯びたその声色に、僕の背もぴんと伸びる。そうか、緊張しているのは僕らだけではないのだとようやく気付く。
「一番だけど」
声が裏返らないよう、ゆっくりと答える。何も言わずにインターホンが切れる音がして、僕は思わずふうと息を吐いた。後ろに立つ千凪の顔が見られない。きっと彼女も、
がちゃりとドアが開いた。母が顔を出す。その小綺麗さに少し驚く。髪は濃いブラウンに染められ、白髪の跡はない。服もいつものような着古したものではなく、モスグリーンのワンピースだ。普段貴金属なんてつけないのに、首には金のネックレスが揺れている。場違いなくらい気合の入った格好に僕は気恥ずかしくなる。千凪ですら、薄手のブラウスにスカートというカジュアルな装いなのに。
「おかえりなさい」
「ただいま。あの、えっと」
僕が何と紹介しようか
「初めまして。一番さんとお付き合いさせていただいている、
堂々とした、涼やかな声が玄関先に響く。それでいて堅苦しさのない柔らかな口調で、母がほっと
「一番の母です。こちらこそごめんなさい、わざわざ遠くから。暑かったでしょう、入って」
「お邪魔します」
千凪が母と僕の後をついて、家の中に入る。いつもはばらばらに脱ぎ捨てる靴を、きちんとこちらへ向け揃え直している。
実家はいつも通り整然と片付けられている。玄関先の靴箱の上には見たこともないアロマが置いてあって、漂う甘ったるい匂いに慣れないまま、廊下を歩く。
母がドアを開ける。ダイニングテーブルの席に兄が、リビングのソファに父が座っている。
「ただいま」
僕の声に、父がテレビから目を離し、こちらを見た。兄も振り向く。僕は深く息を吸う。
父が、ゆっくりと立ち上がった。耳の後ろにまた、汗がじっとりと
「初めまして。神崎千凪といいます」
千凪がまた、深々と頭を下げる。
「一番の父です。どうぞよろしく」
父も頭を下げる。静かで穏やかな声。
「兄の勝利です。よろしくお願いします」
兄も立ち上がって会釈を返す。今日は仕事はなかったようで、それでもいつものような部屋着ではなく、黒い半袖シャツにジーパン姿だ。
「あの、これ良かったら。お口に合えばいいんですけど」
行きがけにデパートで買ってきたお菓子を、千凪が袋のまま渡す。「あら、ありがとう!」と母が無理が滲んだはしゃいだ声を出す。
「夕ご飯もそろそろできるから、もうちょっと待っててね」
「私、何かお手伝いしましょうか?」
「いいのよ、座って待っててね。ちょっと簡易的な椅子で申し訳ないんだけど」
そう言って指したテーブルには、いつもの四脚の椅子の他に、黒のデスクチェアが置いてある。僕が自室で使っていたものだ。二つずつ向かい合った椅子の間の辺、つまり
「え、待って。ここに千凪座らせるの?」
客人をこんな取ってつけたような椅子に座らせるつもりなのだろうか。しかもこのままでは、父と兄の間に千凪が挟まれるという、妙な構図になってしまう。
「ごめんなさい。駄目だったかしら」
母が台所から困った顔を
「あ、じゃあ、僕がそっちに」
腰を浮かせかけた兄を、「勝利」と父が鋭い声で制する。
「すみませんね。椅子が足りなくて」
父が客人用の笑みで謝るも、決してその腰を浮かそうとはしない。
「こんなところに座らせるなんて変じゃない? 俺がこの椅子座るから、隣に千凪を座らせてあげて」
「
この席順にはきっと父なりの理由があるのだろう。家庭内の力関係。役割。崩してしまえば、家族のバランスが崩れると本気で思っているのかもしれない。でも、そんなこと客人の千凪には関係のない話だ。言い返そうとすると、千凪が袖を引っ張ってきた。
「一番くん。私、ここでいいから。大丈夫だよ」
でも、と言いかけて、口を
流れる気まずさにどうなるかと思ったが、食事は思ったよりも和やかに進んだ。家族の質問に千凪が朗らかに答え、時折冗談を言って場を沸かせる。千凪の社交性には何度も救われてきたが、今日ほどそれをありがたく思ったことはなかった。
「一番くんはよくご家族の話されるんで、一度お会いしてみたかったんですよ」
千凪の言葉に、母が「あら」と頰に手を当てる。「そうなんだ」と兄がちらりと僕を見た。
「そんなに話してたっけ?」
「話してたよー。お母さんは料理が上手で、お兄さんは昔から優しくて、って。あと、お父さんのことは尊敬してるって」
「ほう。尊敬か」
父が意外そうに目を開いて、僕を見た。急に居た堪れなくなってくる。
「はい。厳しいけどいろんなことを自分に教えてくれて、それがなかったら今の自分はないって」
「ほお。そんなこと初耳だけどな」
「あー、もう、もうよくない? この話は終わり!」
恥ずかしくなった僕が大きく手を振って、食卓は笑いに包まれた。
いつも客人が来るときに母が作る、手作りピザやトマトのマリネを平らげると、「デザートにしましょうか」と母が立ち上がる。
「ケーキ買ってきたのよ。せっかく千凪さんにもお菓子持ってきていただいたんだけど」
「あ、お渡ししたのは日持ちするんで大丈夫ですよ。ケーキ、ありがとうございます」
「ごめんなさいね。千凪さんは紅茶とコーヒー、どっちがいい?」
「私はみなさんと同じもので。あ、手伝いますよ」
「いいの、いいの。今日は座ってゆっくりしてて」
千凪と母のやり取りを、僕はぼんやりと眺める。自分の恋人がありふれた気の遣い方をし、自分の親がありふれた断り方をする。そんな光景を見ることになる日が来るとは思いもしなかった。
「失礼ですけど、千凪さんは」その様子を同じように見ていた父が、千凪に向き直って尋ねる。「おいくつでしたっけ?」
「私ですか? 二十九です」
そうですか、と父が目を細める。
「それじゃあ一番とは、結婚を前提にお付き合いしているという認識でよろしいですか?」
唐突な発言に、場が凍った。
今までどんな言葉に対しても笑っていなしていた千凪も、表情を失い何も返せないでいた。
「何だよ父さん、急に」
引き
「急ってこともないだろ。お互いもういい歳なんだし、それくらい視野に入れた付き合いをしないでどうする」
父は表情一つ変えず僕をじっと見つめている。千凪は何と答えていいか分からないのか、視線を泳がせていた。母は何も聞こえなかったふりをして、紅茶の支度をしている。父がまさか今日この場で、結婚という言葉を口にするとは思わなかった。
どう答えたらいいんだろう。考えた末、意を決して、僕は口を開く。
「俺は、考えてるよ。結婚したいって思ってる」
千凪が目を
「そうか。一番がそう思っているならよかった」
父の上機嫌な声色に、僕はほっと胸を撫で下ろす。
「お待たせしました」母が見計らったように、ケーキと紅茶を運んでくる。「千凪さん、好きなのを選んでちょうだいね」
「わあ、どれも
ようやく表情を和らげた千凪が、テーブルに並べられたケーキを見て弾んだ声を出す。
「私どれも美味しく食べられる自信ありますから、みなさんお先に選んでいただいていいですよ?」
「いいのよ、気にしないで。お好きなのをどうぞ」
「うーん。すっごく迷いますけど、じゃあ、これで!」
そう言って千凪が手に取ったのは、ショートケーキだった。
絶対にそれを選ぶ父のために、母が買ってきたものに違いなかった。ぴりっと、空気が張り詰めた気がした。ちらりと父を見ると、「どうぞどうぞ」と笑顔で勧めている。千凪は無邪気にそれを自分の方へと寄せる。
父は笑みを浮かべて見届けると、フルーツタルトを手に取った。誰も選ぶことのないそのケーキは、母が余分に買ってきたものだろう。その後はいつもの通り兄、僕、母の順番でケーキを選んでいった。
「ねえ、千凪さん」千凪がケーキを食べ終わる頃を見計らったように、母が話しかける。「奥の部屋に一番のアルバムあるんだけど、見る?」
「え、いいんですか! 見たいです!」
「ちょっと! そんなの見せなくていいよ!」
僕の抵抗虚しく、二人はきゃっきゃとはしゃぎながら奥の部屋へと消えていった。二人の配慮や気遣いがあってこそなのだろうが、とりあえずはいがみ合うほど馬が合わない、というわけでもなさそうで、ほっと胸を撫で下ろす。
男三人だけ残された食卓が、しんと静まり返る。なんとなくばつが悪くて、ぬるくなった紅茶を胃に流し込むと、僕は口を開く。
「千凪、どうだった? いい子だろ」
父と兄を交互に見遣る。兄が片方の口角を上げた。
「そうだね。イチとお似合いだと思うよ」
「ほんと? ありがとう。父さんは、どう思った?」
どきどきしながら尋ねる。父はきっと、僕に遠慮することなく評価を下すだろう。厳しい言葉が飛んでくることを覚悟しながら耳を傾ける。
「そうだな。気が利くし、いい子だな」
眼鏡を人差し指と中指で押し上げ、千凪たちが去っていった部屋の方に首を動かす。
「結婚するつもりなんだろう?」
またその単語が唐突に現れ、一瞬僕は答えに窮する。けれどすぐに「うん」と頷く。
「なら、いいんじゃないか」
それだけ言うと父は、半分ほど紅茶の残ったカップを持ち上げ、軽く口をつけるとソーサーに再び下ろす。
僕はほっとする。どうやら父も千凪のことを気に入ってくれたようだ。
自分の恋人に対する父の評価を気にするなんて、我ながら情けないと思う。それでもやはり、家族には心から祝福してほしい。
祝福。ふと浮かんできたその単語が、僕の中にゆっくりと落ちていく。そしてようやく理解する。
僕は、千凪と結婚したいと思っている。
(つづく)
作品紹介
一番の恋人
著者 君嶋 彼方
発売日:2024年05月31日
『君の顔では泣けない』の著者が描く、恋愛を超える愛の物語
道沢一番という名前は、「何事にも一番になれるように」という父の願いで付けられた。
重荷に感じたこともあったが、父には感謝している。「男らしく生きろ」という父の期待に応えることで一番の人生はうまくいってきたからだ。
しかし二年の交際を経て恋人の千凪にプロポーズしたところ、彼女の返事は「好きだけど、愛したことは一度もない」だった――。
千凪はアロマンティック・アセクシャル(他人に恋愛感情も性的欲求も抱くことがない性質)で、長年、恋愛ができないが故に「普通」の人生を送れないことに悩み、もがいていたのだった。
千凪への思いを捨てられない一番と、普通になりたい千凪。恋愛感情では結ばれない二人にとっての愛の形とは。
詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000035/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら