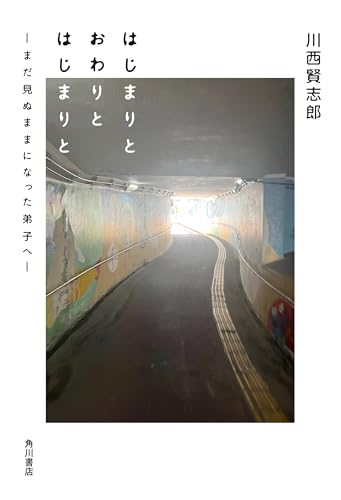川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/始点
公開日:2025/1/29
お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。
2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。
漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。
※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA、2025年2月15日発売)から一部抜粋・編集しました
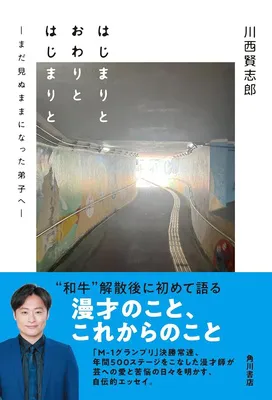
②始点
※書籍の収録順とは一部異なります
笑いにおいて大阪という土地は、少々厄介に思われることがある。それは“自分たちこそがお笑いの本場である”というプライドの高さを感じさせる雰囲気が漂っているからだ。
今でこそ薄まってはきているが、僕が芸人になりたての頃は、なんばグランド花月で標準語のイントネーションを話す芸人が舞台に立つと、露骨に笑いが小さくなってしまう光景を目にしたことがあった。これには理由があるそうで、遡ること江戸時代。大阪という場所は、商人の街であった。物の売り買いをする際に、大切になってくるのがコミュニケーション。商売人はなんとかして物を売りたい、客としては少しでもいいから値切りたい。そんな小さな駆け引きにおいて、会話が重要になってくる。お釣りを渡す時によく言う「はい、500万円!(500円のこと)」や「べっぴんさんやから大根一本おまけしといたろ」なんかは、商売を円滑にやっていくための小粋な一言として生まれたのだろう。客の方も「ほなこれ3つ買うから、端数くらいまけて」などと、少しでも得をするように交渉することが日常的であったそうだ。そういったところから、大阪は笑いやユーモアが生活の一部として根付きやすい土地だったように思われる。だからこそ、笑いを提供する寄席が、大衆に好まれ、興業として成り立ったわけだ。また、漫才が生まれたのが大阪だと言われていることも、大阪人の笑いに対するプライドを育んでいったのだろう。そして、もれなく僕の地元にもその雰囲気は色濃く感じられた。
大阪と奈良の県境には、生駒山という山が南北に跨っている。その山のちょうど麓あたりにある、池島町。ここが僕の地元である。町工場が多く“モノづくりのまち”と言われたり、高校日本一を決める花園ラグビー場があることから“ラグビーの聖地”とも言われたりする東大阪市の一部だ。実際、僕の父親も職人のために作業着などを販売する店を営み、僕は中学・高校とラグビー部に所属していたので、家庭に土地柄がもろに反映されていると言える。そして、実はもう一つ。あまり知られていないのだが、僕の出身地である池島町は、吉本興業や上方漫才に縁の深い土地でもあった。
現在の吉本興業ができあがるまでには、岡田政太郎という人物が大きく関わっている。明治43年、この人は風呂屋に芸人を呼んで、小さな寄席をやり始めた。当時は落語が格式があるとされていてお笑いの中心であったため、それ以外の芸は『色物』と言われて少々軽んじられていたそうだ。そんな時代に“もっと安くてとにかく笑えるものを”と、たくさんの色物とされる芸人ばかりを招いて寄席をやったところ、評判になった。今で言うところの、やり手のベンチャー企業のようなものだろうか。どんどん寄席を拡大していき、さらに増やしていくために寄席を開いてくれる興業会社と力をあわせて展開するようになった。この興業会社というのが、後の吉本興業である。
そういった寄席に立つ芸人の中に、玉子屋円辰という人物がいた。円辰という芸名は、煙突のように背が高かったことに由来しており、それが池島の方言である河内弁の訛りで“えんたつ”であったことから、命名されているそうだ。この人はその名の通り、もとは卵を売り歩く商人をしていた。その際に、江州音頭というのを歌いながら売り歩いていたそうで、それがとても上手で美声であったために人気がでた。そんなきっかけから、彼は寄席小屋にも立つようになった。ある日の寄席でのこと、彼がいつものように音頭を披露するが、客が全然のってこない。ふと太鼓を叩いている者に目をやると、なんとも面白い顔をしていたそうだ。どうやら客はそちらに気を取られて、音頭に集中できていない。円辰さんが堪りかねて「なんちゅう顔しとんねん!」とツッコミを入れると、その場のお客さんが大笑い。これが、後に漫才となっていったという話があるのだ。
この岡田政太郎と玉子屋円辰という二人の人物が、偶然にも池島町出身であった。僕はそれを知った時「おれは将来、吉本と漫才を背負って立つべき人間なのかもしれない!」と誠に勝手ながらではあるが、そう思った。むしろそうあるべきだと、この会ったこともないお二人に言われているような気がした。
現在でも、池島町には玉子屋円辰さんのお墓がある。生駒山の緑が望めるところに立つ、まさに煙突のようにすらっと背の高い墓石だ。僕も実家へ帰ることがあれば、お参りをさせてもらっている。墓石の前に立ち、「あなたが創った土壌の上で、漫才をやらせてもらっています」と、よく手を合わせたものだ。いつも芸事における話を聞いてもらおうと、一方的にだが語りかける。師匠がいない自分にとっては、円辰さんこそが師と呼べる存在なのかもしれない。身体的に、直接的に、何かを師事しているわけではない。だけど、確かに自分にとっては感謝を述べるべき相手であり、この方の存在が心の中にある。言うなれば、これは“時代をこえたプラトニックな師弟関係”のようなものではないか。歴史を巻き戻し、思いを巡らせ、その時代に向けて言葉を届ける。そんなことが、芸の世界において今後も生まれていけばいい。きっと将来、同じように芸事に取り組む人たちにとって、過去は学びとなる。その時代において、失われそうになっているものに気づけたり、それを取り戻す時の支えになってくれる。
今の時代は、YouTube やTikTok などあらゆる発信ツールが生まれ、誰でも自己表現ができる素晴らしい時代になった。どこからがプロでどこまでが素人か、という線引きもなくなってきている。だけど、そういった場所で求められるものは再生回数やいいねの数。その物差しだけで測られるような場面が増えたことで、本当に良質なものがぼやけて曖昧になっているようにも思える。今、きっとお笑いも品位が問われる時代になっている。
地元へ戻るたびに、今でも墓石の前で手を合わせる。円辰さんが生きた時代とは、まったく違うお笑いやエンターテイメントが、現代には存在している。時代を問わず普遍的に求められる、本当に価値があるものとは何か。もちろん答えてはくれないが、墓石の前で語りかける。そしてその光景を、お二人や僕を育ててくれた生駒山の自然という大きな師匠が、悠然と見守ってくれている。
<第3回に続く>