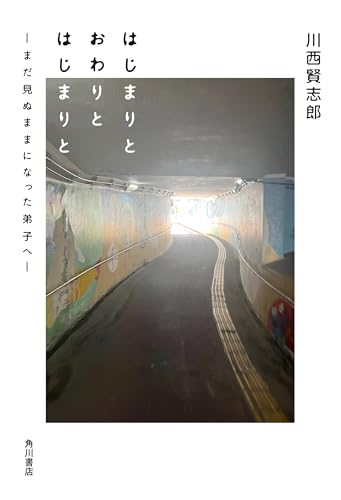川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/前説での光景
公開日:2025/2/5
お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。
2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。
漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。
※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA、2025年2月15日発売)から一部抜粋・編集しました
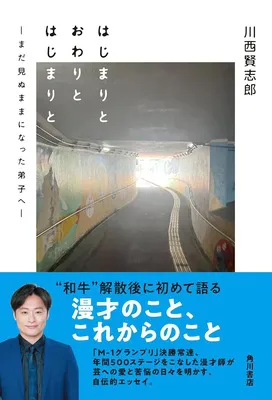
③前説での光景
※書籍の収録順とは一部異なります
どのようにして漫才師として歩んできたかを少し話していきたい。この世界に入った動機は、お笑いが好きで、漠然とテレビの人気者になりたいというものだった。そして、いつの日かそうなれるようにと漫才に励んだ。そこから徐々に、漫才がテレビに出演するための手段ではなく、目的に変わり、活動の中心を舞台に決めた。それでも、心掛けていたことがある。それは、一定数のテレビ出演やメディアの仕事もやり続けること。その理由は、漫才師として必要なものがそこには在ったからだ。
劇場へ観に来たことがある方は知ってらっしゃると思うが、本公演が始まる前には前説というものがある。これから公演を見るにあたって、注意事項を伝えたり、少し空気をあたためておく役割だ。僕もずいぶんと長い間、この前説をやってきた。言いかえれば、出番がもらえるようになるのが遅く、時間がかかったということだ。前説で賑やかして、舞台袖にさがり、トップバッターの芸人に頭を下げて「お願いします!」と言って送り出す。ここまでが前説の仕事。時には同期や後輩にあたる芸人がトップバッターを務めることもあり、自業自得ではあるが悔しい思いもした。ただ、この前説の何がいいか。悔しい思いをさせてもらえることも一つだが、公演を見学することができるのだ。普通なら、出番をもらえていないような若手芸人が、勝手に舞台袖にやってきてネタを見るだなんてことは許されない。ただ、前説をやったのであれば、そのまま舞台袖に残り、公演を観ることができる。暗転になり、出囃子が大音量で鳴る。舞台上のスクリーンにこれから登場する芸人の名前が映し出される。明転して、その芸人が現れる。
まだ前説をやり始めてすぐの頃、強烈に覚えている光景がある。それは、あらゆる芸人が同じ舞台に登場しては捌けてを繰り返す中で、知名度によってお客さんの反応が全く違ったことだった。当たり前と言えばそうなんだが、それでも強烈なものがあった。
寄席という場所は、全国各地から旅行のプランの一環として観に来られているお客さんなども多いため、地域性や年齢層も様々だ。たとえ関西で立派に賞を獲得していたとしても、全国の皆さんにはそこまで知ってもらえていない。お客さんからすると、まだまだ売れない若手芸人の一組でしかないわけだ。これが全国区のバラエティなどにも出演している芸人ならば、反応が一気に変わる。暗転の中、舞台上のスクリーンに名前が映し出される。この時点でまず「おぉ……!」という低い唸り声があがる。次に、明転して、舞台にその芸人が登場すると、さっき一度は押し殺した高揚感が一気に弾けるかのように「ワァーっ!」と歓声があがる。満席で約1000人ほどが一斉に声をあげるのだ。歓声や笑い声が一気に弾ける瞬間というのは、音とともに空気が振動していることまで感じ取れるような、そんな迫力がある。それは、たとえ舞台袖にいても十分に伝わってくる。もちろん、まだ名前が知られていなくても実力があれば徐々にお客さんを摑んで大きな笑いを取ることだってできる。逆に、知名度による最初の爆発力が凄くても、実力がなければ尻すぼみに終わる。そういったシビアな環境ではある。だから、芸が育つ。
パフォーマンスを超越して、まず一目見ることができたというだけで、お客さんを興奮させて更なる満足度を与える。そんな漫才師の姿を見た時に、漫才師として大きくなるためには、世間の知名度を上げる必要があるということを強く思い知った。
<第4回に続く>