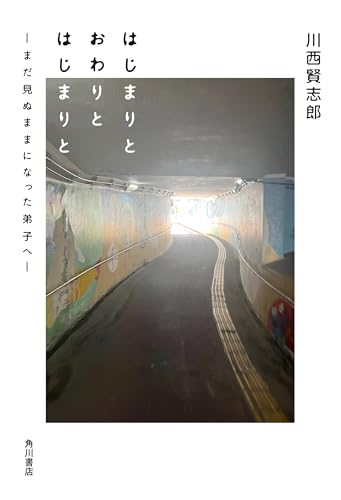川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/理想像を摑むため
公開日:2025/2/12
お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。
2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。
漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。
※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA、2025年2月15日発売)から一部抜粋・編集しました
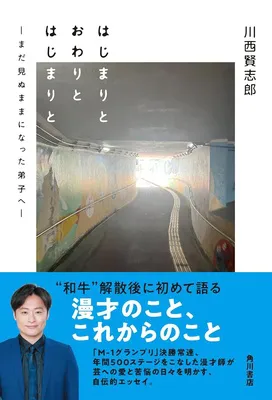
④理想像を摑むため
※書籍の収録順とは一部異なります
漫才師として活動の拠点になるのは、舞台。
その舞台でより輝くために身を置くべき場所が、テレビ。
この矛盾しているような循環を、うまく成立させながらやっていかなければいけない。少しでもバランスを崩した時、おそらくそれはタレントになるんだと思う。本人が望んでそうなったのならいいが、自分は違う。あくまでも漫才師として在りたかった。
そもそも自分がそう在りたいと明確に思い始めたのは、2014年頃。それまでは正直、中途半端に芸人をやっていた。劇場のオーディションには受かり、吉本所属の芸人になって、定期的にライブに出演する。賞レースの決勝にまでは残るが、これといった結果は出ない。多少の浮き沈みの振り幅はあれど、停滞した期間が7年ほど続いていた。途中からうっすら気づき始めていた。あ、たぶんもうこの世界に入った時に描いていたテレビの人気者みたいな未来はないんだろうな、と。そりゃそうだ。それなりの事しかやってこなかったんだから。“どうして自分は報われないのか”ではなく“すべて報われてちょうどこの結果だ”と納得できてしまうあたり、大概自分はクズだなと思った。
そこから、少しずつ変わっていった。初めのうちは、「このままじゃもう後がないぞ」という危機感から、漫才に打ち込んだ。打ち込めば打ち込むほど、結果も少しずつ上向いた。はっきりとした形で報われることがなくとも、良くなってきているという実感はあった。そうなると、今まで以上に細部を工夫したくなったり、漫才に関わるすべての作業が楽しくなった。
「自分は本来、作り込んだ何かをお客さんに披露することが好きな人間なんだな」
それまでにテレビやラジオの仕事も、少しではあるがやらせてもらう機会はあった。だけど改めて、その根本に気づくことができた。“テレビの人気者になる”という漠然としたままの指針が、この時ようやく一つ前に進んだのだ。自分がやるべきことは、これだ。そう覚悟が固まっていく時期に、関西の漫才コンテストで初めて優勝することができた。
そこからさらに2年ほどかけて、じわじわと全国区でも結果が出るようになっていった。一番わかりやすいものが、M‐1グランプリ。毎年12月に開催される、全国規模のプロアマ問わず参加することができる漫才の大会だ。2001年からスタートして、2010年まで。そして、2015年から再び開催されるようになり、現在も続いている。僕も芸人になる前から、この時期になるとテレビに張り付いて夢中で観ていた。自分が芸人になったことにも、漫才をするようになったことにも、大きく関係している。そんな憧れのステージに、幸運にも立つことができた。
そして2016年の年末、間違いなく自分の人生が大きく変わった瞬間だった。準優勝。優勝こそ逃したが、そこで印象を残せたことで、全国のテレビ番組から一気にオファーが舞い込んできたのだ。その時、僕は思った。
前説時代に見たあの時の光景に、自分もなれるかもしれない。
これまでの自分は、中途半端にやってきた皺寄せがしっかり現れて、いったんテレビは諦めていた。その分漫才に打ち込むと、漫才がより好きになって、漫才が認められ出した。その結果、テレビの世界からお声がかかるようになった。まさに自分が理想とする漫才師への道が開かれた気がした。
そこからの数年は怒濤のようだった。東京へ拠点を移し、まずは知名度を上げるためにあらゆる番組出演のオファーを受けた。それと並行して、寄席の出番も増えた。劇場が使いたがってくれている時期に、しっかり笑いを取れる姿をアピールしておきたかったこともあり、急増した寄席にも立った。加えて、獲り切れなかったM‐1グランプリで優勝するために、自主的な全国ツアーを打ってネタを磨いた。テレビ・寄席・全国ツアー、常にこの3つの活動を同時進行させた。それぞれを止めることなく、加速させていくような意識だった。後々の話になるが、この時期に引き受けたロケの映像を見返す機会があり、そこにはロケをしている自分がたしかに映っているのだが、内容をあまり思い出せないことがあって怖くなった。わかりやすく自分のキャパをこえてしまっていたんだと思う。それもこれも〝あの時の光景〞を摑むためだった。
<第5回に続く>