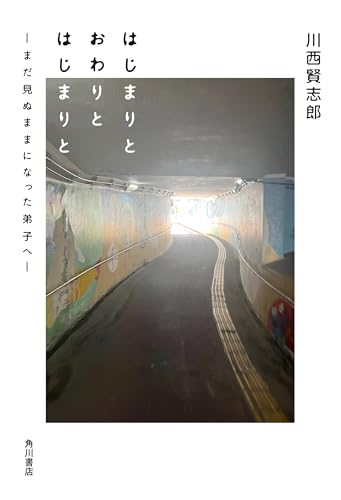川西賢志郎『はじまりと おわりと はじまりと―まだ見ぬままになった弟子へ―』/舞台で必要なもの
公開日:2025/2/19
お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。
2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。
漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』から一部抜粋してお届けします。
※本記事は書籍『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』(川西賢志郎/KADOKAWA、2025年2月15日発売)から一部抜粋・編集しました
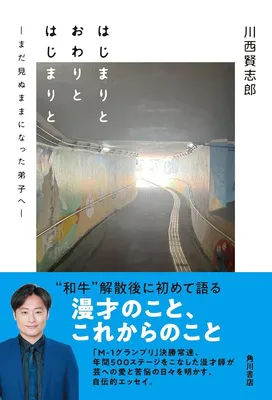
⑤舞台で必要なもの
※書籍の収録順とは一部異なります
数年間にわたって、舞台とテレビという二つの場所を行ったり来たり。そのサイクルを繰り返していく中で、顕著な“違い”を感じるようになる。
それは『舞台で必要となるものがテレビではとくに求められない』ケースがあること。
この話をするにあたって、自分が漫才をする上で大切になると思っているものを知ってもらう必要がある。例えば、ネタに関する着眼点・発想・構成なんかもそうだが、これらはすべて方法論の中に集約されるようなもの。大切であることには違いないが、これらを活かすためになくてはならないもの、さらに言えば、それがなければネタが良くても殺してしまうことになりかねないものが存在する。それは、舞台上でその時の空気を摑みとる“舞台感覚”だ。
漫才師は、その日の客席に合わせてネタをやる必要がある。たとえそれが決まりきった定番のネタであったとしても、その時の空気に合わせて適切な間をあけて喋ったり、言葉のニュアンスを少し変えてみたり、台詞に強弱をつけて発したりする。いわば、最適解を見つけるわけだ。それをやることによって、お客さんが大いに笑いやすくなる。
寄席という場所は、その日その時でまったく空気が変わるもの。ネタ中に笑いを取りにいく台詞を言った後、まるで重い腰を上げるかのように遅れ気味で反応が返ってくる日もあれば、次から次に笑わせてくれといわんばかりに反射的に笑いが返ってくる日もある。かと思えば、そういった人達が半々くらいで入り混じっており、個々が好きなところで好きなように笑う自由なお客さんたちの日もある。正直、そんな日は難しい。ネタの始まりで、どこに照準を合わせてどの程度ですすめていくのかを探りながらやらなければならない。誰かに合わせて笑わせにいきすぎたら、その誰かに含まれていない誰かは置いてけぼりを食らってしまう。
大きな笑いを起こすために、10分間という持ち時間の中でいかに空気をまとめ上げるか。それはとても繊細な作業になってくる。日々新しいお客さんと出会って、その度に最適解を見つけていく。これの繰り返しによって培われるのが“舞台感覚”であり、これをどれだけ持ち合わせているかが、俗にいう『腕がある』ということの証明だと僕は思っている。冒頭で述べた『舞台で必要となるもの』とはまさに、この“舞台感覚”のこと。では、これがテレビにおいてはとくに求められていないと感じるのはどういった時か。
バラエティや情報番組などで欠かせないのが、ロケ企画。どのテレビ局やどの時間帯でも見かけるものだし、自分もよくやってきた種類の仕事である。例えば、どこかのお店を紹介するロケに行って、店主さんが陽気なキャラクターでボケたがりな人だったとしよう。ロケとしては賑やかになるが、どうすれば視聴者を飽きさせずにより面白くできるかを考えることが必要となる。ここは芸人の腕の見せ所。1回目のやり取りはオーソドックスに拾う。2回目は、少し言葉選びや語気を強めにしてみる。3回目で変化をつけた拾い方をしてみる。変化というのは、その店主の発言自体に取り合うのではなく「あかん、この人ボケすぎてロケにならんから今日はもう帰ろう」とか「家族か誰か人質に取られてボケるよう指示されてる?」など、違った目線でのアプローチをしてみるということだ。こういった台詞の選び方や間の取り方一つで、現場が面白いと感じたり、店主本人にも楽しい気分になってもらえたりする。いわば、舞台感覚を用いて笑いを作っていくわけだ。
ロケを終え、現場単位での手応えをクリアできたとして、いざ放送を迎える。その際、編集によって一連の流れが切り取られて放送されることがある。テレビの性質上、限られた尺に収めるためには当然のこと。ただこれが、1回目と3回目のやり取りを繫ぎ合わせて、2回目だけがなくなっている場合なんかがある。そうなると、映りとしては急にぐっと踏み込んだ言葉選びや態度になっていたりして、現場で段階的に積み上げたバランスが狂ってしまい、視聴者目線での受け取り方が変わってしまう。
あくまで番組的には、お店の情報を芸人が楽しくお届けしてくれたらいいわけだから、とくに問題がないことはわかる。でも、漫才師としての目線でいうと、映像の中の自分は随分と繊細さを欠いた雑な仕事をしているなぁという風に思えてしまうのだ。今のように途中のやり取りを一つ省いた編集以外に、稀に時系列そのものが入れ替わってしまっていることだってある。こうなると、芸人としての振る舞いに関してはまるっきり別物となってしまう。
番組にもよるが、編集における最優先事項は“笑い”ではなく“情報”であったりする。だから、これは起こりうることだし許容するしかないだろう。そして編集とは、“現場にあった出来事や雰囲気をいったん壊して再構築する作業”であったりもする。その作業をやるということは、“現場で導きだした最適解”が、必ずしも“放送時の最適解”とは限らなくなるということ。つまりは、常に最適解を叩き出すという漫才師の“舞台感覚”は、それほど重要ではないということになってくる。
流れの中にこそ勝算を見出す、漫才師。
壊して並べることに勝算を見出す、テレビ。
ここに“違い”があるように思う。