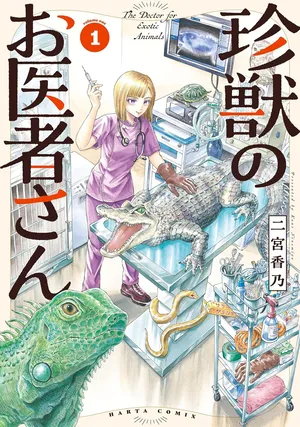猛禽・珍獣ブームが日本の動物の未来を危うくする? 獣医と漫画家の異業種インタビュー!『僕は猛禽類のお医者さん』『珍獣のお医者さん』著者・監修者 鼎談
公開日:2025/4/12
猛禽・珍獣ブームが日本の動物の未来を危うくする
齊藤:おふたりに関係するから申し訳ないけど、私は珍獣ブームが密輸や密猟につながると思って心配しているんです。最近は減りましたが、獣医になりたてのころにホウシャガメ、ヤシオウム、スローロリスとか希少種が診察に来て驚いたことがありまして。違法に飼育されている動物を通報や指導するシステムはできているんでしょうか?
田向:動物病院間ではシステムができていないですし、おそらく大半の獣医師は違法かどうか判断できないと思います。でも密輸や密猟が疑われる小型のサル類や爬虫類はかなり減ってきている印象です。そもそも珍獣は世話がすごく大変だから、気合が入った愛好家しか飼ってはいけないんですよ。私が懸念しているのは、珍獣が槍玉に挙げられてエキゾチックアニマル全体への法的規制が厳しくなるんじゃないかということですね。
二宮:コツメカワウソもワシントン条約で取引が禁止されましたし、不幸な動物が減るのはいいことですね。もしエキゾチックアニマル全体が規制されて、数が減っていった場合、田向先生が珍獣から猛禽類のお医者さんになったりして……?
田向:いや、ならないですよ(笑)。齊藤先生がいるのは北海道の釧路でしょう、絶対に寒いですよ。
齊藤:釧路湿原野生生物保護センターの近くはマイナス20度以下になることもあるからね。帰宅してからスコッチを飲んで温まっています(笑)。もうひとつ聞いてみたかったのは、家庭で飼育されているハヤブサのフリーフライト(自由に飛ばせる)にルールはあるのかどうか。飼い主が外来種のハヤブサをロストする(行方不明にさせる)と、在来種である日本のハヤブサとハイブリッド(交雑種)ができる。在来種に大きな影響があると思っているんです。
田向:とくにルールはないですが……ああ、確かにハヤブサだとハイブリッドができますよね。ハイブリッドがいることは認識していましたが、ロストとはあまりリンクしていなかったけれど問題ですね。
齊藤:首都圏にある自然環境保全センターで保護したハヤブサの中に、まともな日本のハヤブサとは思えないものがたくさんいたのにはびっくりしてね。飼い主がロストしたセーカーハヤブサやシロハヤブサ、あるいは在来種と交雑した子孫と思われます。
二宮:日本の野生動物を捕まえて飼育するのはダメなのに、外来種のハヤブサはペットショップで入手できて、飼う場合にも許可やルールがないんですね。
田向:飼い主がちゃんと飼育管理することが前提だから。でも逃しちゃうから問題が起きるわけです。ハイブリッドで有名なのが日本固有種のオオサンショウウオ。京都の料亭が食用に輸入した中国産が逃げて交雑が起こってしまいました。遺伝子汚染という状態になって固有種が絶滅の危機に追いやられた動植物は多いんですよ。
齊藤:野生の在来種(日本の野鳥)と飼育由来の種(外来種)が多数交雑したら、在来種個体群の遺伝的状況を元に戻すのは難しいでしょう。獣医師は自分が診る動物がどこから来た者なのか判断する知識をもつべきだと思います。もちろん飼い主さんにも自分が飼育している者について知ってほしい。たとえばハヤブサは細胞内に侵入したウイルスのRNAを検知する遺伝子が欠損しているから、高病原性鳥インフルエンザに罹患した水鳥を襲って感染したら、おそらくほぼ100%死ぬと思われます。知らずしらず飼い鳥を危険にさらしているわけですよ。
二宮:自分が大切にしている動物と在来種や固有種を守るためにも、外来種をしっかり管理して飼育できるとよいのですが。
動物を救えなかった獣医師の姿を描くことで命の重さを伝えたい
二宮:漫画に登場するエキゾチックアニマルの中でも鳥を描くのが難しいなと思っていて、齊藤先生に鳥を描くときのアドバイスをいただけたらうれしいです。
田向:『珍獣のお医者さん』は獣医師にも読まれているから、ちょっとした違いにも気づかれそうですよね。
齊藤:まずは鳥の種類がわかるように特徴をつかむことから始めるといいですよ。オオワシなら前腕部前方の羽毛を白く尾羽を菱形にする、シマフクロウは耳羽を大きく体羽に黒い筋を入れる。鳥類はイヌやネコとの身体的な違いが大きいから、骨格まで理解して描くと鳥好きの人から見ても自然な姿になると思います。
二宮:ありがとうございます! 先ほど獣医師は「命を助けたい」から始まるとおっしゃっていましたが、漫画では救えなかったときの姿まで描きたいと思っているんです。命について考えるきっかけになれるといいな、と考えていて。
田向:飼い主さんからすると大切な家族だから治るのが当たり前なんですが、動物は必ず死ぬんですよ。命を預かる仕事ではあるけど、最終的には助けられない日が来る。そんなときに飼い主さんの悲しみを受け止めるのも獣医師の役割だと思っていますね。
齊藤:私は田向先生のように飼い主さんと接する機会がないので、動物の死を悼んだり話したりできる相手がいるのはうらやましい面もあるんです。野生動物に限っては生きている者より死んだ者を圧倒的に多く診ることになるから。
二宮:都市部では亡くなった野鳥や野生動物を見かけにくいかもしれません。スズメが大量死したお話をうかがいましたが、そういった現場は見たことはありませんでした。
齊藤:野外で死んだ野生動物はほとんど見つからないけど、偶然が重なって私のところに運ばれてくることがあるんです。生きて収容されても助けられないことが多い。それでも命を無駄にしないために野生動物法医学で死因を究明し、事故の予防に役立てています。彼らは自然界で起きていることを知らせてくれるメッセンジャーだと思っているんですよ。
二宮:命ある者を診る職業ならではのお話ですね。先生方はつらいこともたくさんあると思いますが、やめたいと思ったことはありませんか?
田向:もちろんあります。毎日やめたいと思っています。一生懸命やるほど「わー!もうやめたーい!」ってなっちゃうんですよ(笑)。
齊藤:そう、私も自分がやめないのを承知のうえで「やめたいなあ!」とか言ってみるわけです(笑)。でも絶対にやめませんから。田向先生と一緒だと思いますね。
二宮:おふたりとも誠実ですよね。全力で真摯に向き合っているんだと思いました。先生方に憧れて獣医師を目指す人もたくさんいるので、伝えておきたいことを教えてください。
田向:必要なのは、飽くなき探究心とあきらめない心。さっきも言ったとおり助けられないことも多くて、毎日のように気分がへこむんですよ。すぐやめてしまう若手もいます。でも獣医師になったばかりでは何もできなくて当たり前だし、早く一人前になろうと焦る必要もない。20年30年と続けてようやくわかってくることがあります。
齊藤:野生動物が関わる保全医学は獣医学だけでは解決しないことが多いから、広い視野をもってほしいなと思います。いろいろな業界との折衝であったり政府を動かすためのロビーであったり、獣医学以外のスキルが必要になるんだよね。それから、懐疑的であれ。本当にこれでいいのか、もっといい方法はないか、クエスチョンをもちながら取り組むことですね。
田向:飼育動物を治すには飼い主さんに連れてきてもらわないといけないんです。われわれは飼い主さんとの付き合いもしっかり考える必要がありますね。
二宮:田向先生はよく「気軽に来てほしい」って言いますよね。田園調布にあって病院も立派なのに、診療費を開業以来ほとんど値上げしてないんですよね。
田向:ちょっとしたことでもいつでも受診しやすいように飼い主さんの負担を抑えたいという思いがあって……。
齊藤:今も20年以上前の診療費でやっているんでしょう、それはすごいな。
二宮:齊藤先生が本に書けなかったという「秘境ロシアをゆく」のエピソードもうかがいたいんですよ。遭難したり拘束されたりと大冒険らしいですね。田向先生のダークな珍獣の話と一緒に、いつか漫画に描けたらと思っています。
齊藤:いや、絶対に描けない(笑)。
田向:特定されるから無理でしょ(笑)。
二宮:では描けない話の続きは、釧路湿原野生生物保護センターに取材にうかがったときに……。寒いのが苦手な田向先生も連れて行きます(笑)。
齊藤:ぜひ、大歓迎しますよ! スコッチとおいしい魚を用意して待ってます。
文=金子志諸
齊藤慶輔

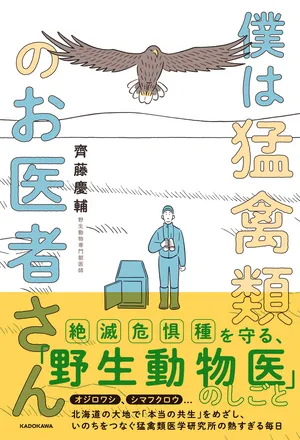
田向健一

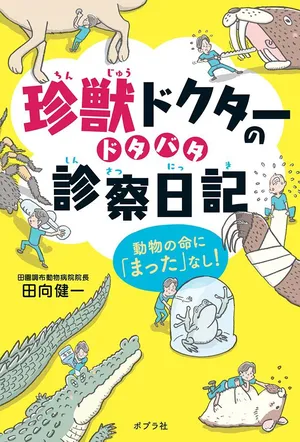
二宮香乃