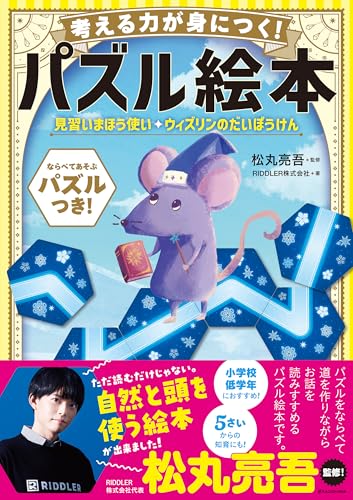松丸亮吾 もし学校の校長になったら「授業のない学校をつくる」。ひらめき学習塾「リドラボ」塾長として、小学生にすすめるのは“創作活動”《インタビュー》
公開日:2025/5/24
「答えが曖昧な問題」が「ひらめきの爆発力」をはぐくむ

——特別授業では子どもたちに直接教えていましたね。すごいなと思ったのが、間違っているかも…と思うような回答でも否定していないことでした。子どもと接する時に気をつけていることはありますか?
松丸:何かを答えたっていうことは、その子なりの考えがあるはず。それを否定すると、その子の考え自体を否定することになります。間違っていることを伝えるとしても、何が違っているのかを納得させるところまでいかないと良くないと思うんです。だから、リドラボでは頭ごなしに否定をしません。それもあって、リドラボのカリキュラムでは問題の答えを曖昧にしています。たとえば、今日の授業にあった「クリティカル間違い探し」です。
[クリティカル間違い探しとは?]
絵を見ながら、よく考えたらおかしいクリティカルな間違い(=現実ではありえないおかしな間違い)を指摘する問題。実際に出題されたのは、「長針が長すぎる」というクリティカルな間違いが隠された時計の絵。その時計はヨコに長い長方形で、長針は「2」のあたりを指している。「2」のところは面積が広いので、長針が長すぎても枠の中におさまっている。ところが、タテの長さ(時計で言うと12と6の間の長さ)が短いため、長い針が「6」にすすむと、長すぎる針が枠をつきやぶってしまう。こんな時計はありえない…。時計の絵に違和感を覚えていても、頭で考えたり、想像を膨らませたりしないと、何がおかしいのかわからない。「2」にある長針が「6」にいった時のことを想像する…などの方法で、「長針が長すぎる」というクリティカル間違いが見えてくる。
松丸:授業ではいくつかの出題があり、そのひとつが、いろいろな文具が出てくる絵の中にクリティカル間違いを探す問題です。その絵の中にあるコンパスを見て「コンパスの鉛筆が短すぎるんじゃないか」と指摘した子がいました。その指摘は、現実にありえない間違いではありませんでした。だけど、コンパスの鉛筆が短すぎると使いづらいですよね。だから、「たしかにこれは不便だね」という受け止めの一言を添えました。正解だとは言いませんが、否定もしません。僕たちの想定と違う答えがあっても、その子の考えがそうなら合っているんですよね。それを理解しようとしています。
——同じ文具の絵の中で、「ペンの蓋が外れている」という発言もありました。松丸さんがここでも、正解とも不正解とも言わないけど「これは…だらしないね」と受け止めていたのが興味深かったです。
松丸:そんな発言もありましたね。子どもの着眼点って面白いなと思います。発想が柔軟で、思いも寄らない答えを言ったり、会話をしていてもすごく面白いことを言ったりする。ただやっぱり、正解主義などで抑制されると、純粋なひらめきの爆発力がどんどん失われていくんです。講演会や授業でも、躊躇なく手を挙げるのは小学校低学年くらいまで。「いい方法思いつく人いる?」と聞いても発言できない中高生はたくさんいます。それではみんな平均的な人になってしまい、面白いことをひらめく人はなかなか出てこないので、もったいないですよね。
——一方的に間違いを押し付けて子どもを萎縮させているのは大人たちだという自省があります。家庭で子どもを抑圧しないようにすることも大切だと思いますが、さらに「ひらめきの爆発力」を高める方法はあるのでしょうか。
松丸:謎解きやゲームを作っている仲間の話を聞くと、小さい時に必ずというほど創作体験をしているんですよ。僕の場合は、「ゲームを作るゲーム」で遊び、それで友だちに遊んでもらったり、自分で作った謎解きを友だちに解いてもらったりしていました。考えていることをただ形にして誰かに見せるというのが、すごく楽しくて。今でも「こうしたら面白くない?」っていう自由な発想で謎解きを作れているのは、小さい時から自分のアイデアをアウトプットすることの楽しさを持ち続けてきたからだと思います。