なぜ日本では離婚後の「共同親権」が受け入れられにくいのか? 嘉田由紀子が歴史的・制度的な観点から考察する【書評】
公開日:2025/5/16
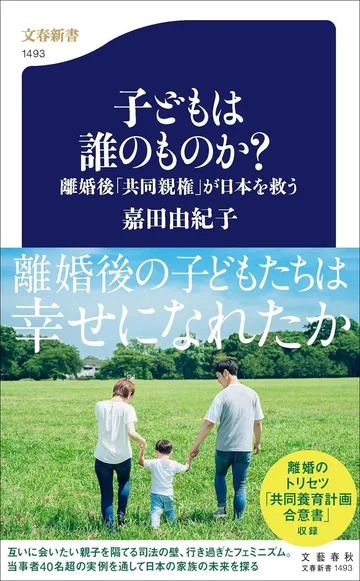
共同親権という言葉が、新聞やニュースで語られる機会が増えてきた。特に離婚後も共同親権を選択できるよう法律が改正され、2026年までの施行が発表されてからは、その是非や影響に注目が集まっている。
しかし、「そもそも共同親権とは何か」「なぜ日本では受け入れられにくいのか」といった本質的な問いに向き合える情報は、そう多くない。『子どもは誰のものか? 離婚後「共同親権」が日本を救う』(嘉田由紀子/文藝春秋)は、そうした問いへの手がかりを与えてくれる一冊だ。
著者の嘉田氏は環境社会学者であり、かつ過去に滋賀県知事を務めるなど政治家としても活動してきた経歴をもつ。また、自身も離婚・子育ての当事者としての経験がある。著者の専門知識と個人史の両面から、多角的かつ実践的に共同親権の可能性を論じている点が、本書の大きな特長だ。
第1章・第2章では、親権の定義や法的背景に立ち戻りつつ、日本の単独親権制度が抱える課題を明らかにしていく。中でも親による子の「連れ去り」問題は、当事者の生々しい体験談が描かれており、読者が制度の不備を具体的に理解できる構成になっている。
選択的共同親権が可決されて以降、共同親権の課題に世論が注目している印象があるが、単独親権制度にも問題は少なからずある。それを理解しやすいよう、国内外の取り組みや事例の解説を交えながら、離婚に関する日本の法制度の現状が語られる。
第3章では、「なぜ日本では共同親権が受け入れられにくいのか」という核心に踏み込む。嘉田氏はその要因のひとつとして、「フェミニズム思想が制度変革を阻害しているのではないか」という独自の仮説を提示し、自身の経験談を振り返りながら考察を深める。賛否を呼びうる視点ではあるが、感情論ではなく歴史的経緯と制度的背景から丁寧に論じている点に注目したい。
第4章では視点を子どもに移し、離婚による両親との離別を経験した子どもたちの語りを通して、共同親権の意義を浮かび上がらせる。離婚によって会えなくなっていた親との再会を果たし、十年以上の月日を経て親子関係を回復させられたケースも紹介されており、親との交流の断絶を強いられた子どもの心境について考えさせられる。
最終章では、日本における家族制度の再構築に向けた具体的な提言が展開される。自治体による支援体制の整備や、教育現場の活用など、親と子だけでは解決困難な課題を「社会がどう支えるか」が問われる。離婚は少子化や子どもの自死率の高さに少なからず影響するのだから、親権の議論は個人間の良しあしだけでなく、社会全体で最適解を模索していくべきことなのだろう。
全体を通じて印象的なのは、未来を担う子どもたちを育むためには、離婚から社会が目をそらしてはいけない、というスタンスだ。親子の絆が法制度によって不当に分断されてはならないし、子どもたちが健やかに育つ環境は社会が支えていくものだ。そう簡単には答えが出ない問いに対し、著者は一貫して正面から向き合っている。
本書は、離婚を控える親や支援者はもちろん、家族制度や子どもの権利について考えるすべての人にとって示唆に富む一冊だ。制度改革の議論が進むいまこそ、感情論や政治的対立を超え、子どもを中心に据えた「未来志向の家族像」を模索する視点が必要である。本書には、そんな強いメッセージが込められているように感じた。
文=宿木雪樹




