アリストテレスは批判好きの嫌なヤツ? YouTuberネオ高等遊民が古代ギリシアの哲学者たちの人柄と想いをひもとく『ゆる古代ギリシア哲学入門 クセつよ逸話で学ぶ31人』【書評】
PR 公開日:2025/8/7
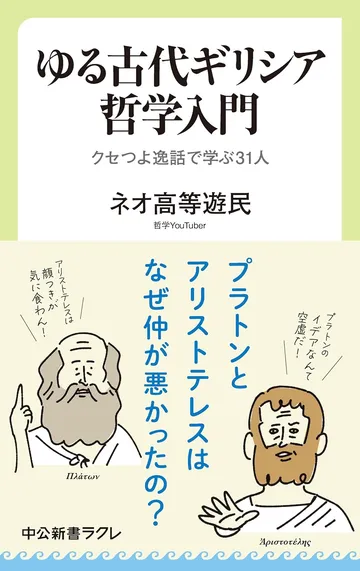
『ゆる古代ギリシア哲学入門 クセつよ逸話で学ぶ31人(中公新書ラクレ)』(ネオ高等遊民/中央公論新社)は、古代ギリシア哲学を“逸話”の切り口から学べる哲学入門書だ。紹介に入る前に、ひとつ問いたい。あなたにとって「哲学」とはどういうものだろうか。
倫理の授業で習い、哲学者の名前と格言だけテストに向けて暗記したところで止まっている人、あるいは自己啓発書やビジネス書の引用で触れた人もいるだろう。しかし、そこから「哲学とは何か」「哲学者とは何者か」まで立ち返って考える人は、ごくわずかではないだろうか。
本書は古代ギリシアの哲学者たちにフォーカスし、そういった「哲学の本質」まで読者をいざなってくれる一冊だ。誰もが知る格言の解説ではなく、“哲学者がどのような逸話を残したか”を中心に構成される。そこから、ひとりひとりの個性や当時の時代背景が見えてくる。はるか昔、私たちとはまったく違う環境で生きていたはずの哲学者たちが、不思議と身近に感じられてくる。そして、彼らのどのような点が、なぜ評価されたのか、ひいては哲学がどのような役割を担っていたのかを、感覚的に理解できるのだ。
例えば“万学の祖”と呼ばれるアリストテレスは、先人たちに対して「あいつは訥弁で明確なことを語らない」「あいつの学説は粗野だから無視して良い」など、かなり辛辣な批判をしていたそうだ。また、自身が病気になったときは、医師に「不調の原因を話してくれれば、先生の指示に従う」と条件を提示したのだとか。それだけ原因究明に執着した人物であるからこそ、後世に多大な影響を及ぼす人物たりえたのだろうと納得できる一方、“偉大な哲学者”というイメージとは少し違う、意外な人間らしさに触れられる。そこがまた味わい深く、面白い。
たくさんの逸話を読んでいくと、その哲学者の素顔に触れられる気がする。もちろん、長年語り継がれてきた逸話の真偽は定かではない。しかし、逸話という形で広く語られたということは、少なくともそのエピソードが哲学者の本質を象徴していると、当時の人々が判断したということだろう。ときに逸話は、彼らが残した学説以上に彼らを理解するヒントになるかもしれない。
本書の狙いは、おそらく哲学を今よりもっと面白く、身近に感じてもらうことにある。小難しい学問だと毛嫌いする必要もなければ、逆に難儀な学説を読み解こうと眉間にしわを寄せる必要もない。哲学者たちも私たちと同じく、世界に疑問を持ち、悩み、言語化しようと試みた人間なのだと捉えれば、哲学はもっと身近になるだろう。
そして本書を読み終えると、私たちもまた一人の哲学者になれる、ということに気付かされる。自分自身を振り返り、自分らしい生き方を見つけるために考え抜く。知的好奇心を絶やさず、世界の物事に疑問を持ち続ける。そういった姿勢を持って、これからを生きていきたいと思わせてくれる。タイトルには“ゆる”と冠してあるが、与えてくれる読後感は“ゆる”くはない。心の中に哲学を携えたい、けれども哲学をよく知らない人にこそ、おすすめしたい一冊だ。
文=宿木雪樹




