夏休みの帰省や旅行の有無から浮かぶ「格差」とは――移動が「できる人」「できない人」の間にある分断・不平等の実態【書評】
公開日:2025/8/22
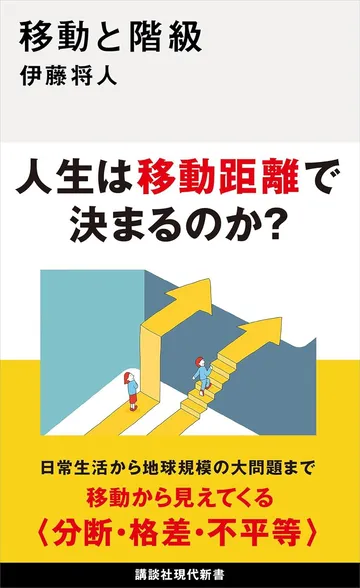
今年の夏休みももうすぐ終わりが見えてきた。旅行や帰省等で「移動」をした人も多そうだが、「行きたい場所に自由に行けた人」は、果たしてどれくらいいたのだろうか?
『移動と階級』(伊藤将人/講談社)は、移動における格差をさまざまなデータから可視化し、問題提起した一冊である。
移動格差とは、本書によれば
人々の移動をめぐる機会や結果の不平等と格差、それが原因で生じるさまざまな社会的排除と階層化
とのこと。
例えば裕福な家庭で育ち健康的な身体を持つ20歳男性なら、望めばフットワーク軽く日本全国、世界中どこにでも行き、さまざまな経験を積むことができる。
一方で、家庭環境が貧しく身体的な障害がある20歳の男性ならどうだろうか? 同じ年齢の同じ男性でも、「移動に対するハードルの高さの違い」によって格差が生じる可能性があることは、誰しも理解できるだろう。
移動格差になり得るのは、収入、居住地(都会か田舎か等)、家族の状況、身体的な障害等、さまざまな要因がある。
では著者が実施した、ある調査結果をご紹介しよう。
日本全国に住む半数弱の人は、自分を「自由に移動できない人間」だと思っているそうだ。「自由な移動」とは、「移動したいときに、自らの意思と選択によって移動できること」である。
人それぞれ理由は異なるが、年収層ごとに分類すると、年収が低いほど「自由に移動できる」という認識も低いことが明らかになった。
更に5人に1人は自分の移動をめぐる自由さに満足していない。「もっと自由に移動したいのに……」と不満を抱えている人も少なからずいるというわけだ。
本書の中には、昨今の物価高騰に関する調査もある。
物価高騰により、「自らの移動頻度が減少した」と回答した人たちを分析すると、その減少度合いは収入が低い階層の方が多く、収入が高い階層の方が低い。
つまり収入が低いと、物価に影響され「移動しづらく」なるということだ。
どうだろう。みなさんも移動に関する格差が存在することを、リアルにイメージできるようになってきたのではないだろうか。
ただ収入と移動格差に関連があることは、多くの人が想像しやすい側面だと思う。本記事を書いている私が盲点に感じたのは、移動格差はジェンダーにもあるということだ。
例えば、青森県中南津軽地域を対象にした地域移動におけるジェンダーと経済格差の調査研究によると、地元へUターンした理由が、男性は「転勤や就職」など仕事関連が多いのに対し、女性は「親に戻れと言われた」など、親の助言で実家に戻る割合が男性と比べ18.0%高かったそうだ。
この結果は、親の期待や家族への援助(ケア)の必要性によって女性が地元に戻る傾向があることを示唆している。
と著者は述べる。
本書ではこういった調査結果を紹介・分析し、私たちの身の回りに多くの移動格差が存在していると気づかせてくれる。私もジェンダーと移動格差の問題は、もっと深掘りして調べたくなった。
では、どうすれば格差は解消できるのか。「5つの観点と方策」を紹介しているので、気になった方はぜひ読んでみてほしい。生活に密接に関わる移動格差について知ることは、個人のみならず、社会の豊かさに繋がる大きな一歩になるはずだ。
文=雨野裾




