バブル期に一世を風靡した画家の謎。ブームの闇に迫るアート×ミステリー【篠田節子 インタビュー】
公開日:2025/8/29
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。

バブル期の日本で、爆発的な人気を得た外国人画家がいた。青く煌めく海中を泳ぐイルカ、優しい目をしたウミガメ─。その緻密な描画、幻想的な色彩で一世を風靡した彼は、美術館で鑑賞するものだった絵画を、インテリアへと大衆化させることにも成功する。だが、危うい販売手法が問題視され、いつしかその存在は忘れ去られていく。篠田節子さんの新刊『青の純度』は、そんなかつて時代の寵児だった画家をめぐるアート・ミステリーだ。
「これまでにも美術や音楽を題材にした小説を書いてきましたが、私は天才にはあまり興味がないんですね。自分が鑑賞する分にはいいのですが、小説にするならもう少しバイアスのかかったものを取り上げたくて。たとえば芸術的な価値は疑問視されながらも、圧倒的に大衆の支持を得た作家や演奏家っていますよね。その作品はどこまで本質に迫ったものなのか、それとも市場の中で消費される運命にあるのか。そんな芸術性と大衆性のせめぎ合いに興味があるんです。文芸の世界でエンターテインメント小説を書いている私の立ち位置と、重なるからかもしれません」
バブル期に人気を得た海や海洋生物を描く画家と言えば、クリスチャン・リース・ラッセンを思い浮かべる人も多いだろう。断っておくが、本書はモデル小説ではない。だが、その着想には彼の絵が関わっている。
「母の介護で追い詰められていた頃、母を寝かせてからリゾートホテルに向かい、1泊して翌朝帰るという息抜きをしていたことがあります。ある時、極限まで疲れ切ってホテルに行くと、地下の画廊にラッセンの絵が飾られていました。それまで私はラッセンに興味がなく、美術品としての価値もわかりませんでした。でも、夜明けの海を描いたその絵を見た途端、『ああ、この世界に逃げ込みたい。この絵の中に入りたい』と思い、その場に立ちつくしてしまったのです。バリ島やサイパン島のようなリゾート地には、虐殺や戦争など負の歴史がつきものです。豪華なホテルの裏に、スラムが広がっていることも珍しくありません。
ですが、ラッセンの絵にはそういった背景が感じられないんですよね。『だからラッセンが描く楽園に惹かれるのか。私が体験したあの瞬間を、人は求めているのか』と納得するものがありました。こうした経験から、マリンアート作家の物語を書いてみようと思ったのです」
作り手を衝き動かすのは純度の高い創作欲
出版社で働く有沢真由子は、50歳の誕生日にひとりリゾートホテルを訪れる。そこで目にしたのは90年代にブームを起こしたものの、今では忘れ去られた画家ジャンピエール・ヴァレーズの風景画。かつて美術関連書や雑誌の編集に携わっていた真由子にとって、ヴァレーズは評するに値しない画家だったが、バブルの遺産のような絵を前にして思いがけず心を揺さぶられてしまう。若くして管理職に就き、時に男性社員に追い越されながらも全力で走り続けてきた真由子だからこそ、目の前に広がる無邪気な楽園がことさら胸に響いたのだろう。男女雇用機会均等法の施行後に社会に進出し、第一線で活躍してきた女性の実情、その胸中がつぶさに描かれている。
「出版社をはじめとするマスコミ業界では、活躍する女性を前面に押し出す風潮がありました。女性の感性を生かして云々という華やかなお飾りではなく、実務能力や交渉力などが要求される厳しい世界で、彼女たちは管理職として仕事をこなしてきたんですね。真由子も畑違いの部署に飛ばされ、男社会で潰されそうになりながらも負けずに這い上がってきた人物です。そういう女性を、今の時代に書けたら、と思いました」
ヴァレーズに興味を抱いた真由子は、彼の本質に迫り、かつてのブームを検証する書籍の企画を立ち上げる。だが、彼の絵を再び仕掛けようとする画商が割って入り、話はなかなか進まない。真由子はヴァレーズ本人と交渉するため、彼が暮らすハワイ島へ向かうが、邸宅はとうの昔に引き払われており、連絡先もわからぬまま。ヴァレーズは今、どこで何をしているのか。行方を追う過程で、真由子はヴァレーズの日本人妻ミレの存在を突き止める。この女性がいかにも怪しげで、真由子ならずとも興味を惹かれてしまう。
「いわくありげな悪い女は、書いていて楽しいですね。彼女は、日本に嫌な思い出があってハワイにやってきたので、なにかあっても帰るに帰れません。野心家というより、背水の陣を敷いてなんとかハワイで這い上がろうとしている人なんです」
ヴァレーズを捜す中、やがて真由子はある事実を知ることになる。それは、現地ではヴァレーズそっくりの絵が量産されみやげものとして売られていること、そしてヴァレーズの名などまったく知られていないことだ。では、なぜ彼は日本で商業的な成功を収めることができたのか。マーケティングの裏側に隠された真実に迫ると同時に、真由子は画家の純粋な創作欲にも触れることとなる。
「認められたい、お金を儲けたい、芸術を創りたいというわけではなく、ただ自分が描きたいから描く。知り合いのイラストレーターも『物心ついた頃からいつでも描いていた。ただそれだけ』と話していましたが、無欲に描き続けることへの感動はありますよね。そうやって描いたものが広く受け入れられれば幸せですが、なかなかそうはいかないのも事実です。そういう難しさも描きました」
篠田さん自身も、やはり書きたいから書いている。そう気づいたのは、この作品を書いているさなか、95歳の先輩作家・皆川博子さんからかけられた言葉がきっかけだったという。
「数カ月前、皆川さんの入居されている老人ホームにふらっと遊びに行ったんです。その居室にあるのはパソコンと膨大な本で埋まった書棚。生活の匂いのしない、まさに作家の家でした。しかも机に置かれた本をふと見たところ、『それは次の作品の資料。今なんとなく読んでいるの』と。さらに『書きたいから書くだけなのよね。あなただってそうでしょう?』とおっしゃるのです。私も含めこれが作家の業であり、作品を生み出す原動力です」
心地よいものを臆面もなく好きだと言えたあの時代
執筆にあたって、ハワイでの取材も行った。それにより、後半のストーリー展開も変わったという。
「日系移民に対しては、サトウキビ畑などで働かされて大変苦労した人々というイメージがありました。ですが、現在は教育レベルが高く、社会的地位の高い方も多いんですよね。また、現地で日系人の墓地を訪れた時には、どの墓も日本側を向いていることに気づき、その望郷の念に心を打たれました。こうした取材から、ある人物の設定が変わり、その背景に奥行きが生まれました」
ヴァレーズを追う旅を通して、なぜ彼がもてはやされたのか、バブル期にアートがどのように受容されたのかというテーマも語られていく。篠田さんは、バブル期のあの狂騒を、アートをどう捉えているのだろうか。
「バブルの頃は、絵画ともイラストともつかないものが流行った時代でした。ヨーゼフ・ボイスやナムジュン・パイクのような難解な前衛芸術がもてはやされた時代から、単純に心地いいもの、欲望が満たされるものを恥ずかしげもなく肯定できる時代に移り変わったのがあの時期だったように思います。芸術性と大衆性のせめぎ合いをずっと書いてきたけれど、この小説を書き終えた今も結論は見えません。書けば書くほどわからないからこそ、何度もこのテーマを書きたくなるのかもしれません」
取材・文=野本由起、写真=干川 修
しのだ・せつこ●1955年、東京都生まれ。90年『絹の変容』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。97年『ゴサインタン 神の座』で山本周五郎賞、『女たちのジハード』で直木賞、2009年『仮想儀礼』で柴田錬三郎賞、11年『スターバト・マーテル』で芸術選奨文部科学大臣賞、15年『インドクリスタル』で中央公論文芸賞、19年『鏡の背面』で吉川英治文学賞受賞。20年紫綬褒章受章。
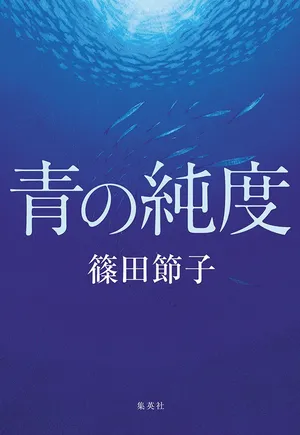
『青の純度』
(篠田節子/集英社)2420円(税込)
バブル時代、煌びやかな海中画で大衆の心を掴んだ画家がいた。彼─ジャンピエール・ヴァレーズは美術界では歯牙にもかけられない“終わった画家”。だが、50歳の編集者・有沢真由子は、彼の絵に不覚にも安らぎを覚える。やがてヴァレーズの書籍を企画した真由子は、作品の掲載許可を得るためハワイへ向かうが……。謎多き画家の知られざる闇に迫るミステリー!




