古代エジプトにも飲みすぎ注意の格言が。今も昔も変わらないお酒はほどほどにという社会常識/古代人の教訓①
更新日:2025/10/7
『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』(大城道則/ポプラ社)第1回【全4回】
4000年以上前の古代人は、すでに現代人が抱える仕事や日常の悩みを解決していた! 本書での「古代人」とは、古代ギリシアのソクラテスやプラトン、アリストテレスでもなければ、古代中国の賢人、思想家、哲学者の孔子や老子でもなく、ゲーテやニーチェよりもはるか昔に生きていた古代エジプト人のこと。現代人が抱える悩みを解決するヒントとなる、古代人が残した44の格言を紹介する『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』から、一部を抜粋してお届けします。
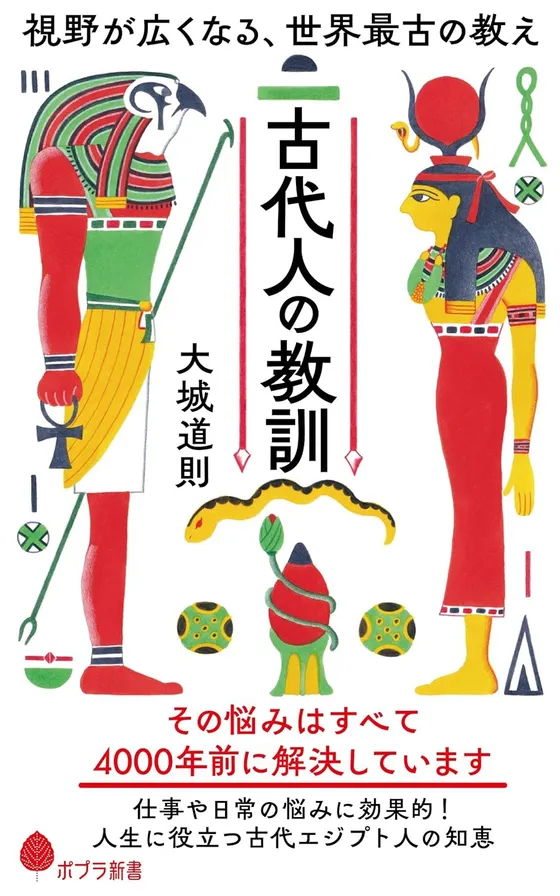
格言1 ビールは吐くまで飲むな
ビールを飲みすぎてはいけませんよ。飲みすぎれば、あなたは自分の気づかぬうちに、意味不明な言葉を口走ってしまうからです。もしも倒れ込んでしまい正体をなくしても、誰も介抱などしてくれないのです。一緒に飲んでいた友人は立ち上がり、「酔っ払いは向こうへ行け」と言うでしょう。あなたを探して、話をしようとしていた人は、あなたが赤ん坊のように寝転がっている姿を目にすることでしょう。(「アニの教訓」より)
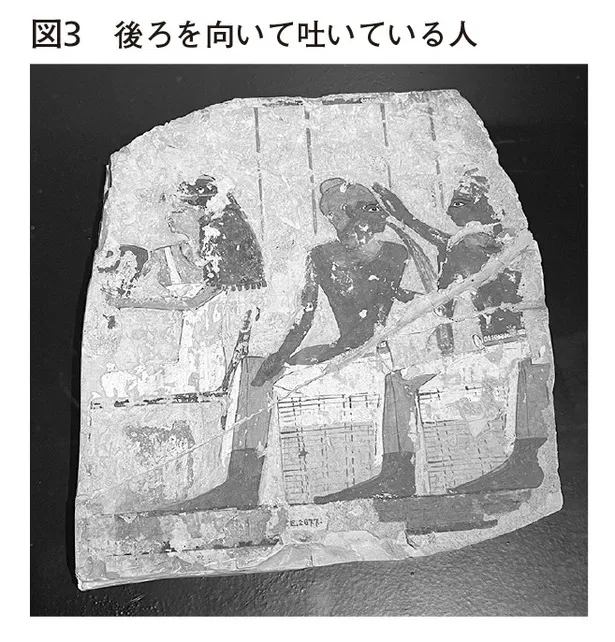
ビールは子供も飲む
お酒を飲める年齢の人は、このような経験をした、またはこのような現場に遭遇したことは多いだろう(図3)。特に自ら粗相をした経験を持つ人にとってはトラウマで、耳の痛い話だ。
現在のエジプトは国民の90%以上がイスラム教徒なので、ほとんどの人はお酒を飲まない。日本の居酒屋さんなどで日々頻発する、お酒を吐くまで飲むような失態をする人たちを目にすることはまずない。
しかし約90%強がイスラム教徒であるのなら、裏を返せばそれ以外の宗教の人もいるということだ。実際に残り約10%の人がキリスト教の一派であるコプト教の信者なのだ。よって首都カイロの街角には酒屋さんが幾つもある。私も何軒か知っている。実際に購入した経験もある。ただ、そのようなお店の雰囲気は少しダークで、お店に入るとなんだか悪いことをしているような錯覚に陥る。また当たり前なのだが、大都市の高級ホテルであれば、観光客としてビールもワインも飲めるのだ。観光客が禁断のビールの泡をうまそうに口にするのを目にするのは、エジプトが世界屈指の観光立国であることを再認識する瞬間でもある。
しかしながら、古代のエジプトは今とは少し様相が違っていた。7世紀の初め頃にイスラム教がムハンマドによって創始されて以降、段階的にアルコールは禁止されるようになったが、それ以前は禁止されていなかった。ビールもワインもエジプトで楽しまれており、野生のミツバチからハチミツを採って作ったハチミツ酒のミードなども飲まれていた。そして古代エジプト人たちは禁酒どころかむしろ、それらアルコール飲料を毎日のように飲んでいたことが知られている。
古代においては、土着のエジプト人だけではなく、エジプトを支配した異民族たち、たとえばペルシア人、ギリシア人、ローマ人もそれらを口にしたに違いないのだ。川辺に近づきワニやカバに襲われる危険性もなく、住血吸虫の住むナイル川の水を飲むよりも安全な飲み物こそがビールなのであった。
そのビールの起源が論じられる際にメソポタミアとともに真っ先にその候補に挙がるのがエジプトだ。古代エジプト人たちにとって最もポピュラーな飲み物であったビールは、水と少しだけ焼いたパンを原材料とし、これらを一緒にふるいで濾し、混ぜ合わせたものを壺に入れて発酵させたものであった。そのため見た目は、関西のミックスジュース(バナナやみかんなどのフルーツに牛乳などを入れてミキサーにかけた、とろみのあるジュース)のようでドロドロとしており、栄養価は高かったと考えられる。




