100%の頑張りで日常を乗り切ってしまう女性たちへ――科学的視点から考える「ストレスへの対処法」【書評】
公開日:2025/10/6
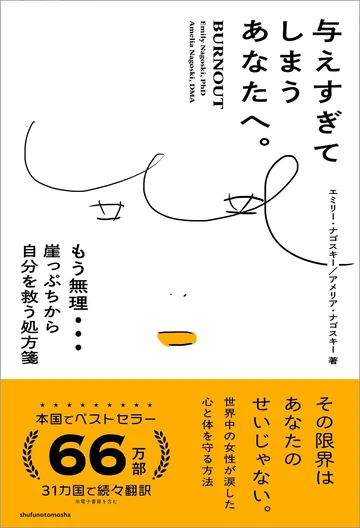
日常の中には、“やらなければならないタスク”が多すぎる。世間では男女平等が叫ばれつつあるが、果たして実態はどうだろうか。共働きが当たり前になった分、女性に圧し掛かる負担は、むしろ増えているように私は思う。
だから、私たちはお気に入りの入浴剤やいつもより丁寧なスキンケアなどで、なんとか自分を癒して仕事や家事、育児などで酷使した心身をケアしようとする。だが、なぜか心身はさほど癒されない。そんな日常を送り続けた末、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥ってしまうこともあるのではないだろうか。
なぜ、自分はこんなにもセルフケアが下手なのか…。『与えすぎてしまうあなたへ。 もう無理… 崖っぷちから自分を救う処方箋』(エミリー・ナゴスキー、アメリア・ナゴスキー:著、稲垣みどり:翻訳/主婦の友社)は、そんな苦しさを抱えている人に届いてほしいセルフケア本だ。
ストレス反応を癒す6つの方法
著者は、健康行動学の博士号を持つエミリーと、ミュージカル・アートの博士号を持つ双子の妹アメリア。本書は、世界31カ国で翻訳された話題書である。米国では、66万部を記録。ニューヨークタイムズのベストセラーにも選ばれた。バーンアウトに関する既存の書籍とは違い、科学的根拠に基づいた角度からストレス・マネジメントが学べる点が斬新だ。
著者いわく、ストレスと向き合う上で知っておくべきは、ストレスとストレス要因は違うものだという知識だという。
ストレス要因とはにおいや味、仕事、お金など、体にストレス反応を起こすもの。一方、ストレスとは、ストレス要因に遭遇した時、体に起きる神経学的、生理学的な変化のことだ。
私たちはストレスを感じると、ストレスの原因となる「ストレス要因」に反応しがちなのだそう。不快だと思ったものを取り除いてどうにか安心感を得ようとする。
だが、ストレス要因に対処しても、ストレスそのものに対処したことにはならないのだそう。なぜなら、ストレスの原因が去った後も、脳内や体内に生じたストレス反応は残ったままであるからだ。
だから、私たちは長く蓄積された“未完結のストレス”を抱え続け、バーンアウトを起こしてしまうのだという。
それを防ぐため、著者らは体や脳を安心させ、ストレス反応を完全に癒す6つの方法を、本書で紹介。例えば、パートナーと1回6秒間のキスや20秒間のハグをする、文や絵を描くというクリエイティブな自己表現などは、ストレスの対処に繋がるという。
不思議なことに、人間は自分の中に未完了の感情があると、心身に影響が現れる生き物だ。そんな人間らしい脆さを受け止め、ストレスとの向き合い方を見つめ直すことこそが、心身を軽くする第一歩になるのだ。
ストレス要因との向き合い方
なお、作者らはストレスそのものへの対処法だけでなく、ストレス要因への向き合い方も解説している。渋滞のような自力ではコントロール不能なストレス要因への対処法も知れるので、そちらも参考にしてほしい。
また、個人的にハっとさせられたのは、ストレスを癒すには対処法を知るだけでなく、自分を苦しめている“本当の敵”の正体に気づくことが重要だというアドバイスだ。それは、“頑張れない自分”を責めない思考を持つことに繋がるように思えた。
例えば、家父長制のように、自身が女性という理由で組織などから排除され、“力不足”と思わされていないか、日常を見つめ直すことは大切だ。
男尊女卑の時代があったため、私たち女性は「誰かに与えなければ」という刷りこみが無意識下にあるように思う。だからこそ、自分の中で常識になっている「奉仕の心」の正しさを疑い、少し立ち止まって、他者をサポートする生き方を続ける理由を考えることもバーンアウトから抜け出すためには大切なのかもしれない。
頑張り屋の人や真面目な人ほど、自分を労る時間を持とうとすると「わがままだ」とか「怠けているのでは…」という自分の声に責められてしまいやすい。だが、人間に必要なのは「睡眠」という分かりやすい休息だけではない。人間は脳や心が安心できる精神的な休息がなければ壊れてしまう、繊細な生き物なのだと思う。
本書には自分の日常や考え方を見つめ直せるワークシートも収録されているので、そうしたページも活用しつつ、自分が頑張りすぎな日常を送っていないか振り返ってほしい。あなたには自分を大切に扱い、心身を労る時間を確保する権利があるのだから。
文=古川諭香




