言葉を「体験」するインタラクティブノベル『ダレカレ』。独特すぎるプレイ体験に込められた秘密を作者に聞いた【ゲームクリエイターyonaインタビュー】
公開日:2025/10/16
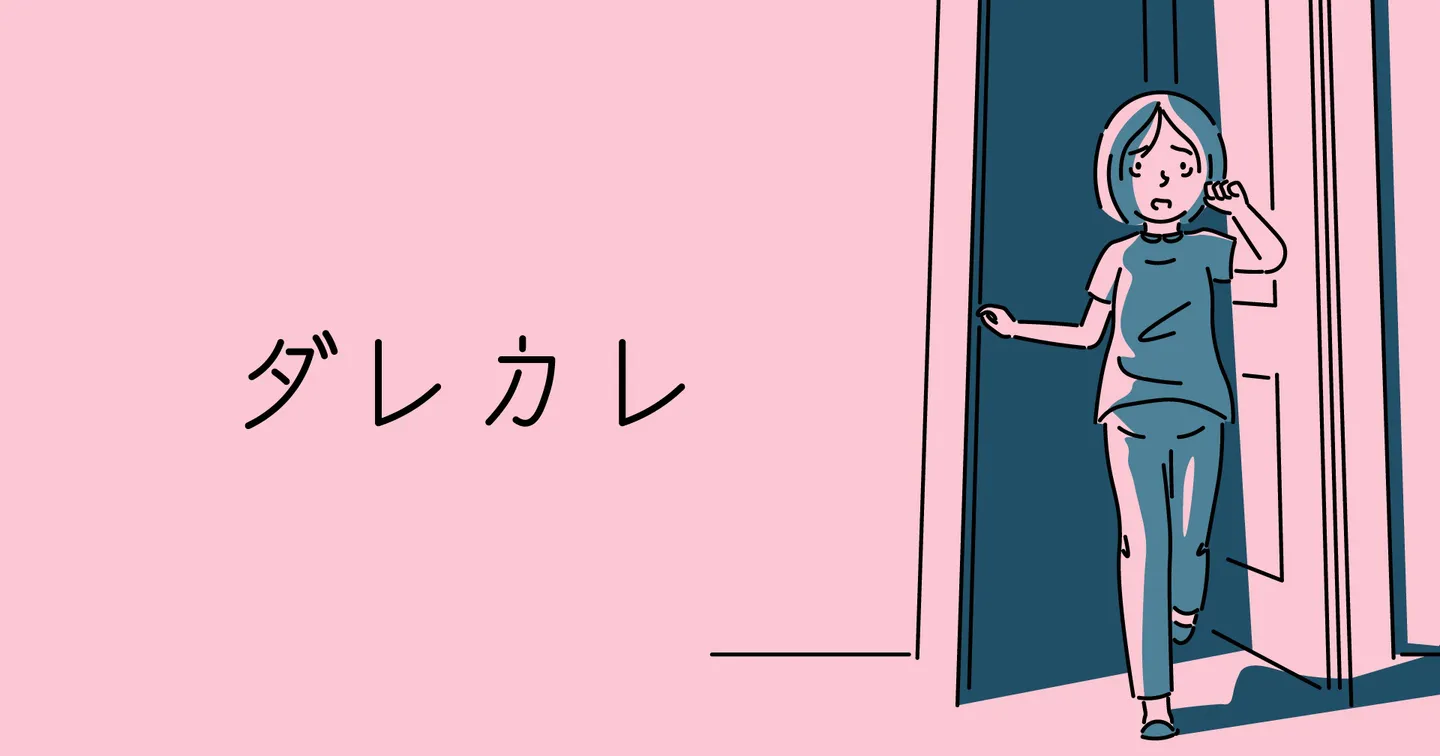
「私はロボットではありません」
パソコンを操作している際に、複数のタイルの中から煙突や信号機の写ったものを選んだ経験はないだろうか。もしくは、人間であることを証明するために、チェックボックスにチェックを入れた経験はないだろうか。
いずれも、パソコンをよく使うユーザーなら「あるある」とうなずいてくれるシチュエーションだと思う。このような例をはじめ、自分が行った操作に対してシステムが応答してくれることを「インタラクション」と呼ぶ。
このインタラクション要素がゲーム化されたことで最近話題となった『ダレカレ』をご存じだろうか。ゲームクリエイターのyonaさんが手掛けた作品で、2025年7月24日発売。インタラクティブノベルという珍しいジャンルのゲームだ。
読書体験や映画鑑賞、さらに言えば一般的なゲーム体験とも異なる独特なプレイ感が話題となり、「号泣した」「ゲームである意味がある」といった評判を獲得している本作。2025年10月16日にはノベライズ化作品『ダレカレ』も発売され、さらなる広がりを見せるこの独自の世界観がどのように構築されたのかをひもとくべく、yonaさんにお話を伺った。
yona
クリスチャンのゲームクリエイター。講談社ゲームクリエイターズラボ二期生。インディーゲームパブリッシャー「room6」でエンジニアを務めた後に独立し、現在までに『In His Time』『ダレカレ』の2作をリリースしている。
X:https://x.com/yona_unltb
note:https://note.com/yona_unltb
Steamクリエイターページ:https://store.steampowered.com/developer/tearyhand
※本インタビューは極力ネタバレのないように編集していますが、一部ゲーム内テキストの引用や、ゲーム内容を類推できる内容が含まれています。
人の認識の歪みを体験するためのインタラクティブノベル
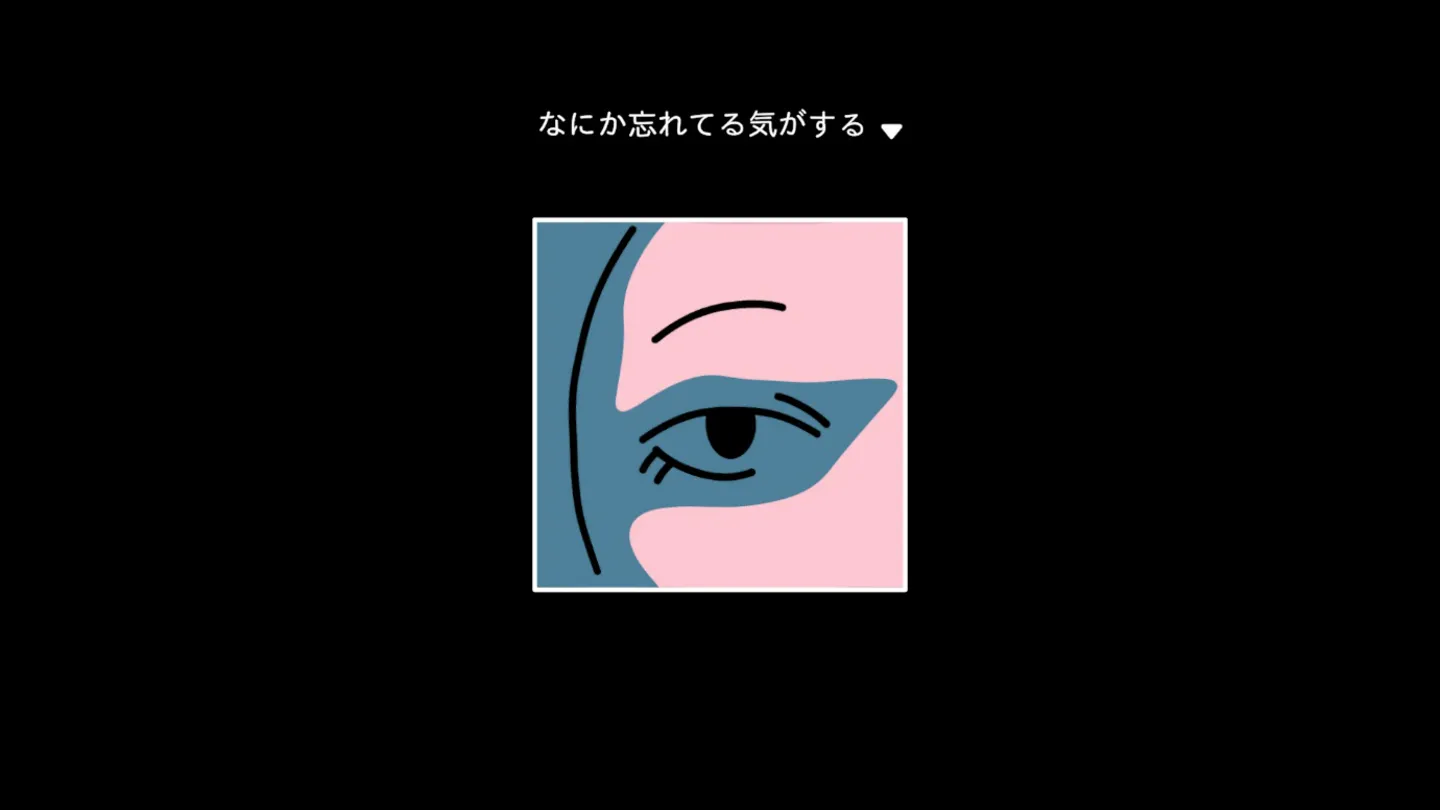
――まずは基本的な質問からさせてください。『ダレカレ』は、知らない方に説明するとしたらどのようなゲームなのでしょうか。
yonaさん(以下、yona):結構説明が難しい作品なのですが、一言で表すと「人の認識の歪みを体験するゲーム」です。
ジャンルとしてはインタラクティブノベルで、マウスでボタンを操作するというとてもシンプルな操作だけで完結するゲームです。
ひとつひとつのマウス操作自体に意味の込められた作品なので、プレイ中に生まれる「なぜこんな操作をするのか?」という疑問が、話を進めることで後々意味を持ってくるのが特徴的だと思います。
――簡単な操作の中にも深みがあるわけですね。
yona:そうですね。私の個人的な想いや信仰を形にした作品でもあり、メッセージ性も比較的強いと思います。
あと、日本ではまだまだ『ダレカレ』のようなアート性の強い作品はまだ少ないので、「ゲームでこんなことを体験できるんだ!」という感想を持っていただけることも多い、不思議な作品だと思います。
――インタラクティブノベルということですが、小説や漫画との違いをどう考えていますか。
yona:すごく当たり前のことですが、小説や漫画は真摯にストーリーに向き合うことができる媒体だと思います。一方でゲームはというと、ユーザーの体験という要素が強く出ます。つまり、ストーリーに体験が付随するかどうか、の部分で違いがあるんです。
ゲームはどうしてもプレイヤーの干渉ありきで進むので、ストーリーだけになってもいけないし、ゲーム体験だけが一人歩きしてもいけません。ストーリーと体験をどう組み合わせるか、というのが重要です。『ダレカレ』では、その体験部分をインタラクションに担わせています。
ちなみに私、読書スピードも遅いうえに漫画を親に禁止されていたので、こんな大層なことを言えるかと言うと怪しいんですけど…(笑)。
作品の企画を考える際にはいつも「自分が何のために生きているのか」に向き合わざるを得ない
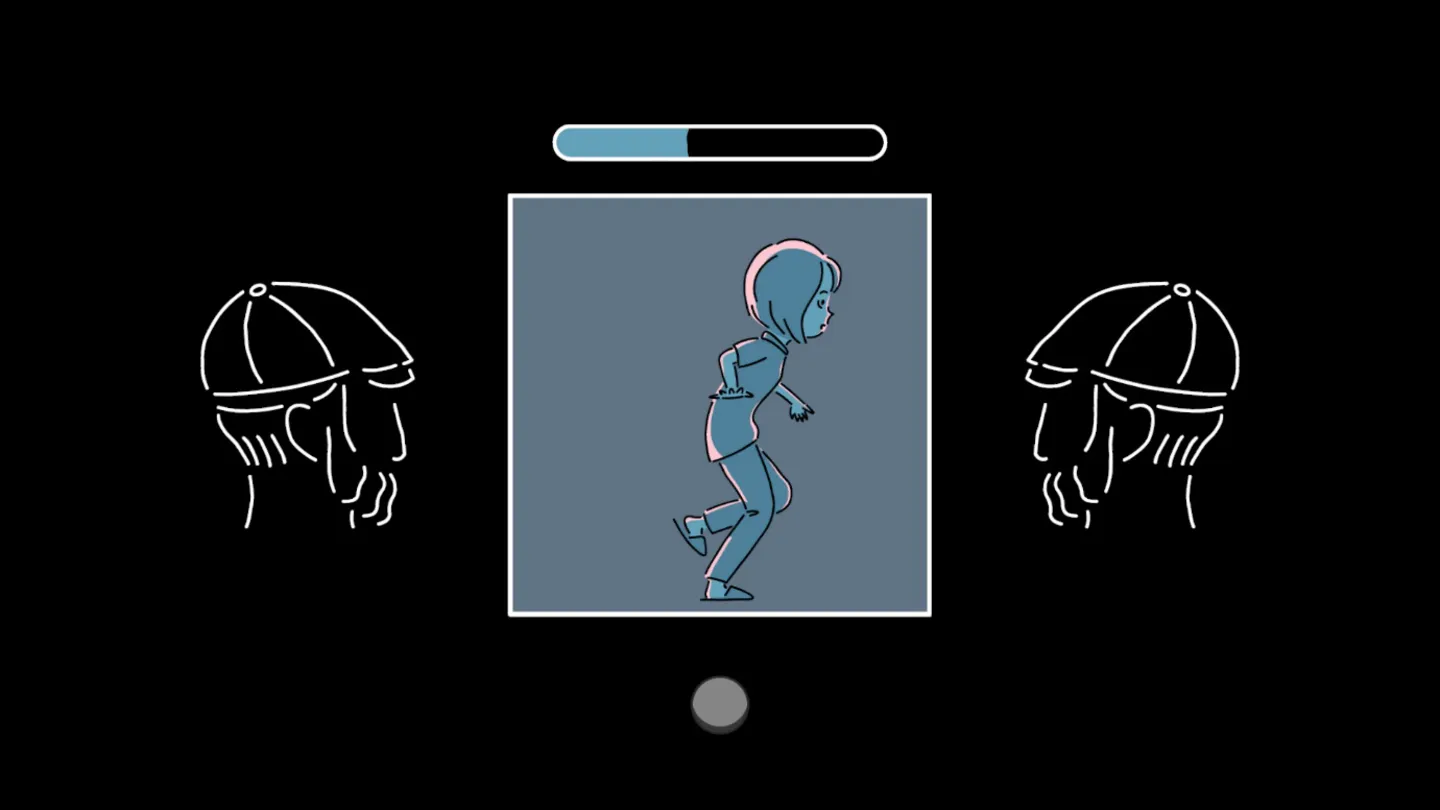
――本作はインタラクションを重視することで、テキスト量が意図的に減らされているような印象を受けました。
yona:おっしゃる通りで、私が『ダレカレ』において意識したところは、「遊びが言葉の代わりになっていく」という点です。なので、極力テキストでの説明ではなく、体験で言葉を語るようにしたいと思っていました。
本作においてテキストはストーリーの舵を取るような役割を担っていて、ゲームプレイはその舵に沿って話を進ませたかったんです。なので、インタラクションがストーリーを膨らませる役割を持っています。
――インタラクションでストーリーを膨らませるというと…。
yona:最近構造として近いと感じたのは、私の大好きな作品でもあるアニメ映画『ルックバック』(藤本タツキ:原作/2024年6月28日公開)です。
『ルックバック』もセリフを掛け合うシーンと、アニメーションと音楽だけで進むシーンが交互に繰り返されると思います。セリフで方向性を定めて、アニメーションと音楽でストーリーを膨らませている非常に上手い例だと感じました。その他、ミュージカルなども近い手法だと思います。
――なるほど。ちなみに作中のテキストはスムーズに書けましたか?
yona:本作はテキストとプログラムを同時進行していたので、一部のテキストを除いてスムーズに書けたと思います。どちらかと言うと、その後の推敲に時間がかかりました。
――推敲というと?
yona:実は私、テキストを書くのはあまり得意じゃないんです。制作の過程で『ダレカレ』のプロトタイプをいろいろな人に遊んでもらう機会があったのですが、その際に「どういうふうに感じたのか」「こちらの意図がちゃんと伝わっているか」といったことをプレイ中の表情やプレイ後の感想で確かめて調整していました。
開発段階では、テキストを読んでもらったときに「どういうこと?」と聞かれてしまうことも結構ありまして…。そのたびに「こういう表現だと伝わらないのか」と思って、もう少し説明を追加する、みたいなことを繰り返しています。なので、制作当初よりかなりわかりやすい表現になっていると思います。
テキストに関しては「これだとユーザーに伝わらないかもしれない」といった、本ゲームの担当編集でもある講談社の方々の率直な意見にもすごく助けられました。
――逆に、「伝わりづらい」と言われても貫いた言葉はありますか?
yona:ありますね。特にゲーム終盤は、私の思想が特に強く反映されているんです。だから終盤の表現に関しては「こうしないとおかしい」というのが私の中で明確にあって、「実際にこのような行動はとらないのではないか」といった指摘があっても、修正せずにそのまま進めました。
具体的には、ロジャー(ゲーム内に登場する男性で主要人物のひとり)が怒るシーンなどですね。自分の中で、この場面ではロジャーは絶対に怒るだろう、という確信がありました。
――ご自身の中で、登場するキャラクターはかなり明確に存在しているイメージなのでしょうか?
yona:そうですね。ただ、私は人の気持ちになる、ということがなかなかできない人間でして。どちらかというと私がよく知っている人だったり、自分自身だったりに当てはめているようなイメージです。
――テーマに関するセリフひとつひとつにリアリティがありましたが、参考にされた作品はありますか?
yona:ネタバレになるので詳細は省きますが、テーマに関する書籍やドキュメンタリー映像などは、かなりの数に触れたと思います。
雰囲気的に目指した作品で言うと、『PERFECT DAYS』『すばらしき世界』『オットーという男』『ボーはおそれている』などの、アート性の強い作品だと思います。自然なセリフ回しなどがすごくよく考えられていて、「こんな作品を作りたいな」と思わされる作品ですね。
――テーマと繋がる部分だと思いますが、ゲーム内では「祈り」や「愛」という言葉が度々使われていました。祈りや愛は、人生においてどのくらい大切なものだと考えていますか?
yona:ゲーム内の祈りの描写は、私の信仰を一般の方にも共感しやすい形で描いているものです。祈りは、「愛が表現として形になったもの」とも言えると思います。
――なるほど。では、愛に関してはどのように考えていますか?
yona:作品の企画を考える際にはいつも「自分が何のために生きているのか」に向き合わざるを得ないんです。
私の考えでは、人間は誰しも、誰かに愛される使命とか誰かを愛する使命というものを持って生まれてくると思っています。ただ一方で、人間は完全な愛を持ち合わせていない、という問題もあると思うんです。だからこそ、「愛はどこから来るのか」ということを考えています。
――yonaさんの中では愛という言葉の定義が、ライクやラブのような一般的なものと異なる気がします。
yona:愛という言葉は、私からするとすごく宗教性が高い言葉です。
わかりやすく伝えようとすると、そうですね。神様はいつも私たちを見守っていて、愛を与えてくださっている。その愛があるからこそ、私たちは誰かを思いやったり、相手のために行動できる、という感じでしょうか。
少し宗教的で小難しい話になってしまいましたが、『ダレカレ』は認識の歪みを通して私の考える信仰心や愛を表現しようとした作品であることは間違いありません。作品をプレイしていただければ、なんとなく感じ取っていただけると思います。




