東京をしのぐ人口を誇った1920年代の大阪。“ラジオと吉本興業”が新たにもたらしたイメージ【書評】
公開日:2026/1/2
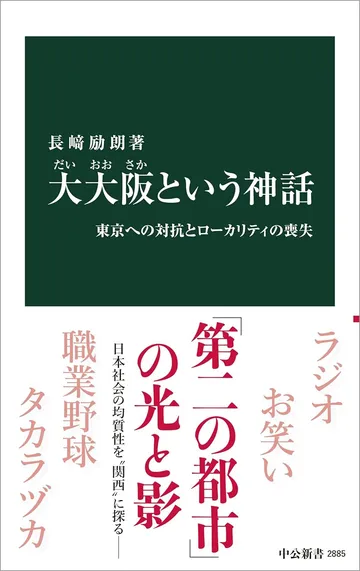
2025年、盛り上がりをみせて閉幕した「大阪・関西万博」。その舞台となった大阪はかつて、東京の人口をしのぐほどの大都市だった――。そこから約100年。現代へ至るまでに大阪のイメージがいかにして築き上げられていったのかをたどるのが、書籍『大大阪という神話 - 東京への対抗とローカリティの喪失』(長﨑励朗/中央公論新社)である。
かつて、大阪の人口が日本一かつ世界でも6~7位だったという驚き
タイトルの「大大阪」とは、1925年前後の大阪を表す言葉だ。1926年初頭、大阪市は市域を拡張し、人口で東京を上回る日本一の都市となった。世界でも6~7位に数えられたというから、その勢いは相当なものだ。しかし、本書が示すのは当時の成長が必ずしも成功物語ではなかったという事実だ。
当時の大阪では市域の拡張によって中心部に労働者の街が形成され、都市の形が変わりつつあったという。同じタイミングで、労働者の街に他の地域からも多くの移住者がやってきた。その変化を象徴する一節として、本書では尼崎出身の小説家・中島らもの言葉を紹介している。
ややこしいことには、一般に「がめつい」「えげつない」「ど根性」などで形容されている大阪商法というのは本来の大阪人のものではない。本来の大阪人というのは要するに老舗の坊々なわけで、もう少しボーッとしている。俗にいう大阪商法は、ガッツとアイデアで大阪原人を駆逐した近江商人のものなのである。
ここでの「大阪原人」とは、古くから大阪に住み、ローカルな空気の中で商売や生活を続けていた人たちだ。
しかし、大阪が巨大都市へと成長するにつれて「老舗の坊々」たちの中で共有されていた空気感は薄れていき、「がめつい」「えげつない」「ど根性」といった分かりやすいイメージが前面に押し出されていった。
1920年代以降の大阪はそうした背景を伴いながら、他の地域に向けて文化を発信する都市へと変わっていく。本書で記されているのは、その背景にあった東京への対抗意識と、本来あった大阪のローカリティが失われていく過程である。
ラジオと吉本興業が大阪のイメージを新たにした
当時の大きな変化としては、ラジオ放送の開始があった。本書によると、現在のNHK大阪放送局が開局したのが1925年6月1日で、第一声は地元の神主による25分にもおよぶ祝詞(のりと)だったという。
当時の様子を、大阪朝日新聞は「祝詞はマイクロフオンに通じてフアンに聴かせるといふ風変りの式で、まづ科学の殿堂を浄めの式でひきしめてのち」と報道。科学技術と神事がまじわる違和感を伝えたそうだが、ラジオがなかった時代の人たちの驚きと期待は想像にたやすく、東京に遅れて2カ月後に起きた大阪の変化は「古い大阪の終わりを告げる鎮魂歌」として、象徴的なものになったのだろう。
さらに、変化をもたらしたのが吉本興業だ。今でこそいわゆる“吉本芸人”を、テレビを中心に各所で見るが、本書によれば現代はいわば「二度目」の最盛期で、初めての最盛期は1920年代から1930年代だったという。
そして、吉本興業の最盛期を象徴したのが漫才だった。当時の人びとに漫才がウケた要因について、本書では「参加感覚」という言葉で示している。舞台と客席に分かれていながらも、その場にいる全員が同じ世間の空気を感じながら笑い合う。現代では当たり前の光景となったが、当時の人びとにとってはきっと新鮮で、やがては大阪イコール笑いという文化を作っていったこともうかがえる。
このほか、広く「阪急文化圏」として職業野球や宝塚などのルーツにもふれながら、大阪の過去と現在を結ぶのが本書の醍醐味だ。今ある「大阪らしさ」とは、何か。その答えを提示してくれる、興味深い書籍である。
文=カネコシュウヘイ




