行間から染み出す悪臭……。女子高生の匂いを嗅ぐ男と、患者の痰や大小便の悪臭に苦しむ男を、「嗅覚」を軸に描いた小説集
公開日:2023/9/25
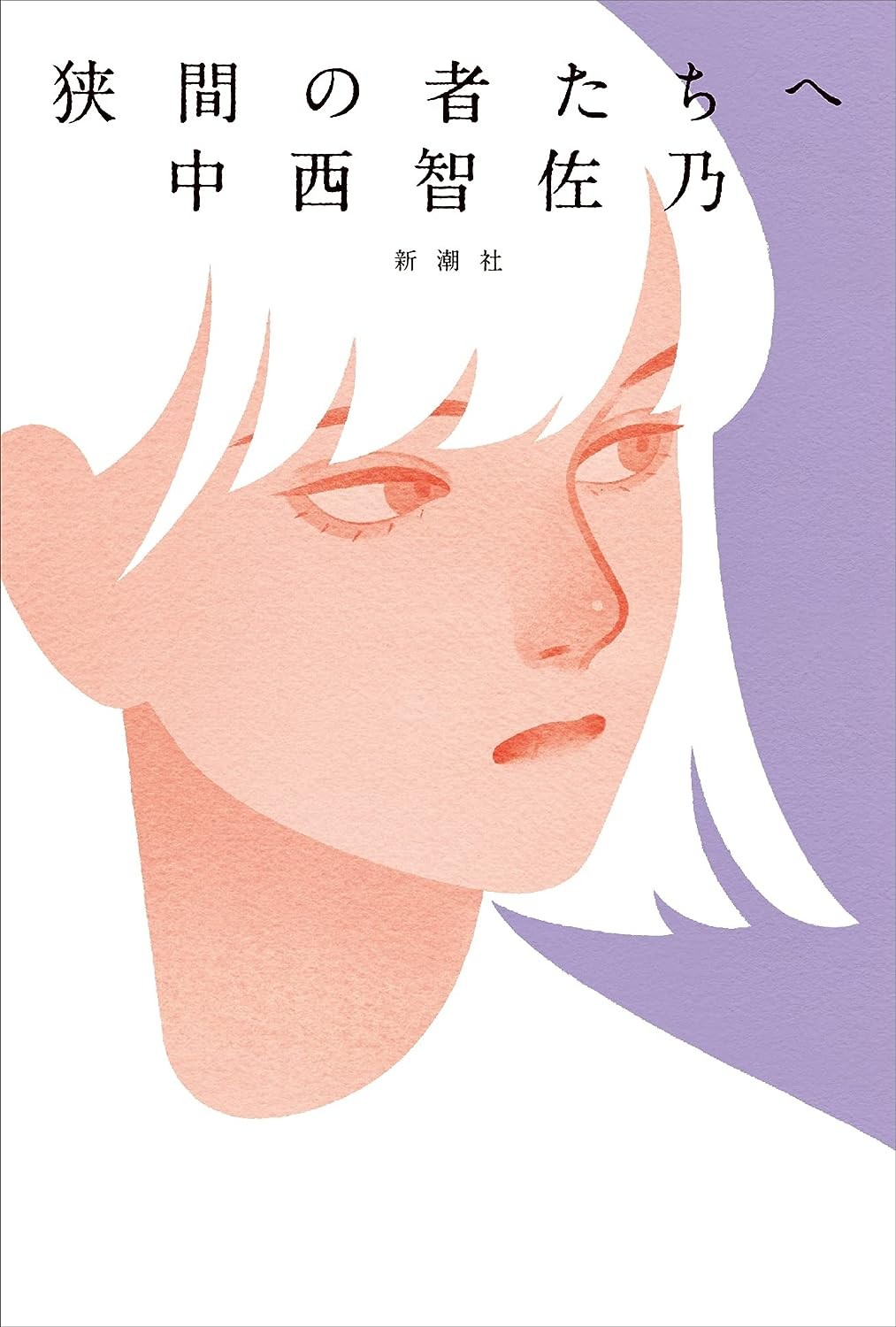
「尾を喰う蛇」で新潮新人賞を受賞した中西智佐乃氏が、初の単行本を刊行した。同作と「挟間の者たちへ」との2編が収められている著作『狭間の者たちへ』(新潮社)だが、前者の主人公・祐輔と後者の主人公・興毅の話には、共通のモチーフがちりばめられている。中年男性の歪んだ性欲、仄暗い内面、広義の意味での暴力、距離の近さがもたらす欲望——。続けて読むと息が詰まり呼吸が荒くなってくるこの2編は、いわば活字による劇薬である。
「尾を喰う蛇」の祐輔は、通勤電車の中で女子高校生に近づき、匂いを嗅ぐ。非力な者が徹底して暴力や欲望の標的にされるというのは、あまりにも非道で、あまりにも普遍的な光景である。祐輔は、匂い嗅ぐという行為を、「元気をもらう」と表現する。なんという欺瞞だと呆れるが、彼は、日々の辛さから逃避するために彼女に迫った。
祐輔は、彼の痴漢行為に気付いていながら、協力的な態度を見せる作業服の男と知り合う。その男はもっと露骨に彼女へのストーカー行為に耽っており、最初は同類として彼に親近感を抱いた祐輔も、恐ろしくなって逃げてしまう。
祐輔はまた、少女に出会う前は、あーちゃんという風俗で働く女性に思いを寄せていた。電車内の彼女同様、自分の欲望に忠実に匂いを嗅いでいたのだろう。むろん、金銭の授受と本人の同意があるという観点から、風俗と痴漢は違う。だが、女性を自由に、そしてぞんざいに扱えるという状況におかれると、祐輔は得も言われぬ快楽を覚えるのだ。
「挟間の者たちへ」の主人公・興毅は、36歳の介護福祉士。仕事は過酷極まりなく、座る間もなく老人を介護する日々だ。仕事のシフトを巡ってパートの女性たちに陰口を言われるが、興毅は夜勤も嫌がらずに引き受ける。結婚後の共働きをいやがる彼女とは別れ、子持ちの妹が住みついた実家に仕送りをする日々である。
彼の辛さは、嗅覚を通して描かれる。施設利用者たちが大便や小便を漏らすのは日常茶飯事であり、興毅は辛いながらも、自らの仕事を淡々とこなしていく。生理的に苦手な患者に、なんとか暴力を振るわず我慢している。それでも、ケアの最中につい力が入ってしまうこともあった。
患者から唾や痰をかけられたり、横暴な扱いを受けたりもする興毅は、自分の全身に悪臭がべっとりとこびりついていると感じている。興毅が腕を差し入れる患者の湿った悪臭は、祐輔が装着したマスクの内側まで届く。生臭さは行間から滲み出て、読者にも伝わるだろう。彼が自宅に帰って過剰なほど念入りに全身を洗う、それは何かの儀式にすら思える。
戦時中の光景が脳裏に読みがえったのか、当時の辛さや恐ろしさがフラッシュバックする高齢の利用者もいる。彼ら/彼女らの寝言や悪夢を聞いていた興毅は、それがトリガーになったのか、戦時中の画像を見漁るようになる。検索ワードに「戦争 画像 レイプ」と打ち込み、昏い欲望を満たすのが習慣になっていく。下半身をさらけ出した女性を、何人かの兵士が取り囲み、性暴力を振るっているだろう画像に見入るのだ。
祐輔も興毅も、自分の感情の揺れやブレを制御することに、困難を感じている。もし自分が同じ立場だったら、どうするだろうか。少なくとも著者は、弱者を攻撃する残酷さを、一部の特殊な人々の所業だとは考えていないように思える。
両作に共通するのは、匂いの描写だろう。香りではなく、あくまでも匂い、いや臭いか。満員電車で、介護施設で、肌と肌の距離が近くなることで、祐輔や興毅の眠っていた欲望が目を覚ます。人と人とが密着している状況そのものが、暴力に結びつく可能性を秘めているのだ。その描写の巧みさには舌を巻いた。
「正常」と「狂気」の境目がじわじわと融解する過程を見せられるような2編、決して愉快な話ではないし、嫌な汗を流しながら読んだが、それでも読んでよかったと思える。介護労働の厳しさを知ることができた、というのもあるが、むしろ、抵抗できない弱者への無言の暴力の恐ろしさを見せつけられたからだ。そして、そうした暴力衝動は一歩道を踏み外せば、誰にでも湧きあがるものだからだ。
文=土佐有明




