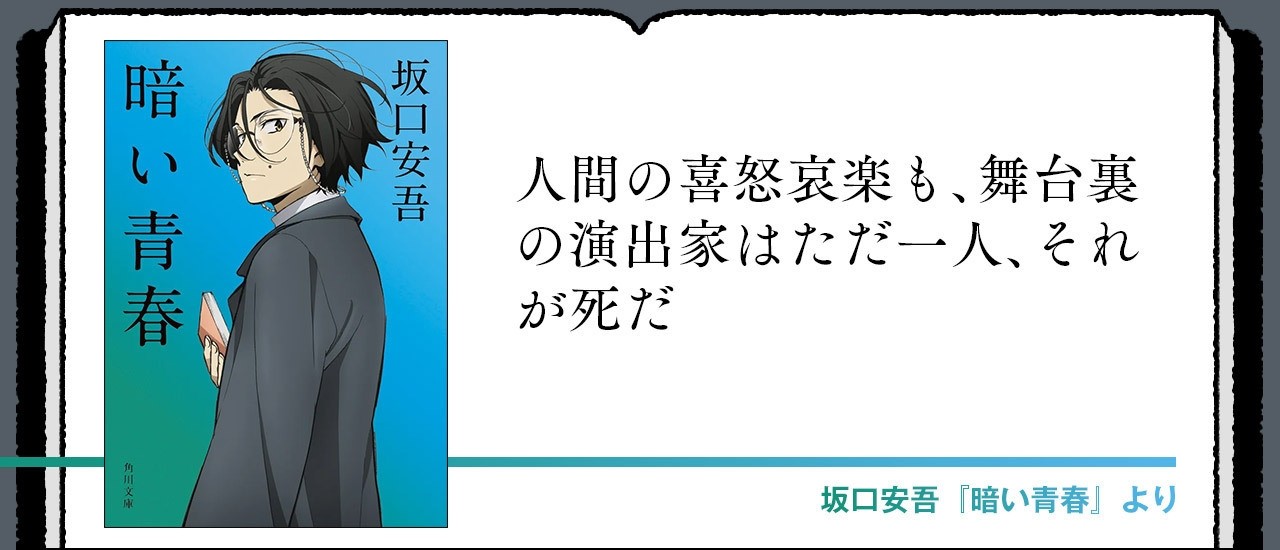ラランド・ニシダの「心に刺さったこの一行」――新井一樹『プロ作家・脚本家たちが使っている シナリオ・センター式 物語のつくり方』坂口安吾『暗い青春』より
公開日:2024/5/30
忘れられない一行に、出会ったことはありますか?
つらいときにいつも思い出す、あの台詞。
物語の世界へ連れて行ってくれる、あの描写。
思わず自分に重ねてしまった、あの言葉。
このコーナーでは、毎回特別なゲストをお招きして「心に刺さった一行」を教えていただきます。
ゲストの紹介する「一行」はもちろん、ゲスト自身の紡ぐ言葉もまた、あなたの心を貫く「一行」になるかもしれません。
素敵な出会いをお楽しみください。
ラランド・ニシダの「心に刺さったこの一行」
ゲストのご紹介
ニシダ
1994年7月24日生まれ、山口県宇部市出身。
2014年、サーヤとともにお笑いコンビ「ラランド」を結成。本書が初の著書となる。
ラランド公式サイト:https://www.lalande.jp/
【最近出会った一行】新井一樹『プロ作家・脚本家たちが使っている シナリオ・センター式 物語のつくり方』(日本実業出版社刊)より
わたしはハウトゥー本をよく読む。恥ずかしいことだという自意識は人一倍ある。
小説を書いたり、最近は脚本の勉強を少しずつ始めたりなどしていて、創作に関しての本は十冊近く読んだ。何か糧になったと言い切れるほどには、自分自身成長していないなと思う。
わたしは何か救いを求めて、そういった本を読んでいるのだと最近ふと気がついた。ハウトゥーを知りたいのではない。もちろん、その中で有意義な教えは頂戴して、何かに活かしたい気持ちはある。けれどそれよりも、今創作している自分を肯定する何かを欲しているのだ。
この本の中で
「何を書くか」×「どう書くか」=面白い物語
という方程式が書かれている。
「何を書くか」が作家性であり、才能であると本書の中では定義されている。そして「どう書くか」は技術である。そして、この二つの関係性に関して書かれた以下の一文が、わたしを多少なりとも救ってくれた気がするのだ。
「どう書くか」という表現技術が習得できていないだけなのに、才能という言葉で、創作から逃げてはいけません
才能という言葉が、わたしは大好きである。ない自覚があるから欲してしまうのかもしれない。
けれど、本書では才能と技術は別だと言い切っている。
才能が全てを決める要素ではないのだと。創作は天才にのみ許された知的創造だと無意識に思っているけれど、技術に関しては誰でも習得できるのだという言葉が、一つ安心材料になった気がした。
そして、本書は技術についての本である。何が書かれているのかは、皆さんが読んで確かめてほしい。
【忘れられない一行】坂口安吾『暗い青春』(角川文庫刊)より
文庫本の表紙がアニメキャラになっている。『文豪ストレイドッグス』に登場する坂口安吾らしい。最近よく見る名著の表紙をアニメや漫画のイラストにするタイプの本。
この手の流行には賛否あるのだろうけれど、わたしは賛成派である。学生時代、小畑健先生が表紙のイラストを描いた、太宰治『人間失格』を買って読んでいた。理由がなんであれ、本を手に取り読むことは尊い。文豪たちが異能力で戦っている事実からは距離を取って生きていきたいけれど。
表題作「暗い青春」は安吾自身のエピソードの羅列で進んでいく。芥川龍之介が自殺した後の芥川邸で同人誌の編集に勤しんだ思い出からはじまり、友人の死や、サーカスで起きた事故、就職面接など多種多様である。
青春ほど、死の翳を負ひ、死と背中合せな時期はない
この言葉に、一見すると焦点がなくバラバラだと思われたエピソードが収束していき、結果として安吾の生死への価値観が垣間見える。そう思わされてしまうほどの孤独が言葉に染みている。
人間の喜怒哀楽も、舞台裏の演出家はただ一人、それが死だ
文学史に残る名言だと思う。格好良すぎる。
戦争のある時代が死を身近に感じさせたのだろう。しかし、彼自身の感受性の鋭敏さもまた異質であり、読めば読むほど坂口安吾という人が分からなくなる。「暗い青春」の中で、彼は自分自身をぞんざいに扱っているような感じもすれば、愛おしさを持っているような気もする。絶望を語りながら、希望をにおわせているような気がする。読み切ったと同時に、また頭から読みたくなる。
そんな読書体験はそうあるものではないと思うのだ。
書籍情報
暗い青春
著者 : 坂口安吾
発売日:2023年12月22日
青春は暗いものだ。厭世の彼方に希望の光を見いだした、安吾の傑作
青春ほど、死の翳を負ひ、死と背中合せな時期はない――。同人誌を編集するため、あるじが自殺して間もない芥川龍之介の旧宅に通った日々。苦悶がしみついているかのように陰鬱な部屋が思い起こさせるのは、青春時代に死んでいった仲間たちの姿だった。人間の喜怒哀楽の舞台裏に潜む、振り払い難き「死」の存在に、無頼派の旗手が独自の視点から肉迫を試みた。表題作「暗い青春」ほか、火花の如き輝きを放つ短編10編を収録。