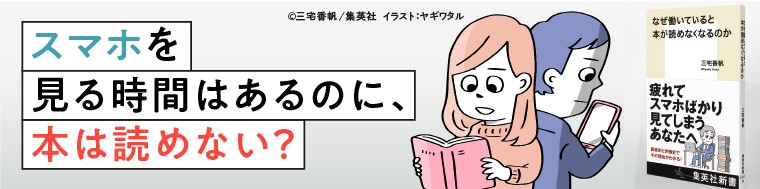『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』働くすべての人の疑問に迫る、2024年ベストセラー《著者・三宅香帆氏インタビュー》
更新日:2025/1/20
本の魅力は、ある程度の「長さ」
――本って、読む時代や自分の状況によって、まるで印象が変わるのもおもしろいですよね。
三宅 アーカイブ性が高いですよね。あと、やっぱりある程度の長さがあるというのは、重要だと思うんですよ。1冊分の誰かの体験を聴く機会ってそうそうないですし、聴いているだけでは受け止めきれないことも多いと思うんですけど、本なら、自分の心地いいタイミングとペースで、じっくり向き合っていける。もし「読む」ことが苦手なのだとしたら、今は「オーディオブック」というメディアもあります。どうしても聴く・観ることが優先されがちな現代において、読者を広げるために出版業界が仕掛けた画期的な試みだと思うんですよ。もちろん、作家さんへの収益分配など、検討すべきところは多々あると思いますが、今本が好きで書店に足を運んでくれる読者だけでなく、これから本を好きになるかもしれない可能性のある人たちをとりこむ努力を、出版業界は絶え間なく続けてきた。そのことも、本書を書く上で改めて気づかされたところです。
――三宅さんがYouTubeなど、執筆以外に活動の場をもたれているのも、読者を広げる試みのひとつなのでしょうか。
三宅 そうですね。本を読む以前に買うという体験のおもしろさを伝えたいと思っていて、私自身が書店に行く動画をあげたりしています。まずは書店がどういう場所なのか、どんなわくわくするような体験ができるのかということを、ひとりでも多くの人に知ってもらいたいな、と。今後、全国の書店さんをめぐって本を買う動画を配信する予定なので、投稿を重ねるなかで、より書店のためにできることが見えてきたらいいなと思っています。
――余暇を優先できる働き方をするために、「半身(はんみ)で生きる社会」を本書では提唱していました。今後、どうすればそれが実現できるのか、三宅さんならではの切り口で読んでみたいです。
三宅 ありがとうございます。「半身」という言葉は、もともと2023年1月に放送された「100分deフェミニズム」(Eテレ)で上野千鶴子先生が紹介していたもので。ちょうど連載を始めるタイミングだったので、そこに着地できるような内容にしたいなと、最初から考えていたんです。労働にフルコミットすることが正義とされすぎている社会には疑問があるけれど、働くことが好きな身としては「頑張らなくていいんだよ」みたいな言説も受け止めきれない部分がある。誰もが労働と余暇の価値を平等に認めて生きられる社会をつくっていくためにはどうしたらいいのか、私も、考えていきたいと思っています。