すぐにキレる上司、空気が読めない同僚や部下にどう対応する? 大人の発達障害を考える
公開日:2017/10/3
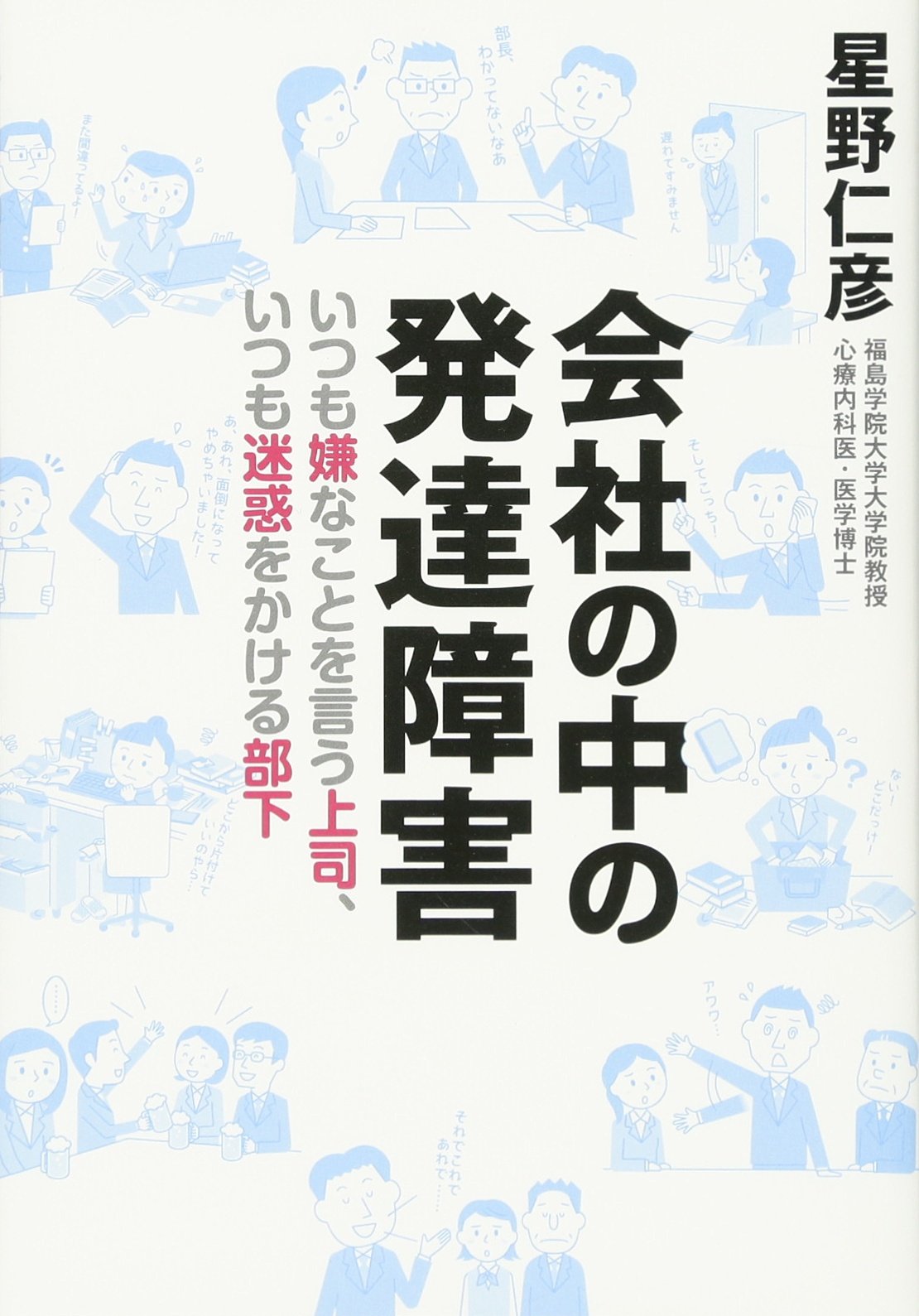
ゆとり教育には学力低下を招いたとする批判があるが、いわゆる「詰め込み教育」から、「生きる力」を身につけるため自ら考え能動的に学習させるという理念を具現化する教育現場でのカリキュラムづくりを行政が適切に支援できなかったことと、達成度を数値では評価しにくいことが批判の元になってしまったのだろう。むしろ問題は、近年注目されるようになってきた発達障害への対応ではなかったか。ゆとり教育の柱の1つに「個性重視の原則」があり、問題行動のある子供についても個性としてしまうことで治療の機会を逸していた可能性がある。そして、ゆとり教育以前にはそれらの子供への指導は体罰も含むもので、やはり医学的な観点からすれば不適切な対処であったと言わざるをえない。そう考えると、ゆとり教育以前の人たちも含め、発達障害を抱えた大人たちが治療の機会に恵まれぬまま、社会の中に多くいるということになる。
ただし、「発達障害」という用語には問題があるらしい。今回取り上げる、自身も発達障害だという心療内科医の著した『会社の中の発達障害 いつも嫌なことを言う上司、いつも迷惑をかける部下』(星野仁彦/集英社)では、病名に含まれる英単語の「Disorder」を「障害」と直訳していることが誤解を招いていると指摘している。本来は「日常生活上の多少のハンディ」という意味合いのもので、研究者の中には「発達アンバランス症候群」と呼ぶべきだとする声もあるという。用語としては一般に浸透しているため本書でも「発達障害」としているが、一考する必要はあるかもしれない。
この発達障害というのは、注意力に欠けて落ち着きがなく衝動的な行動を取る「注意欠如・多動性障害」、対人スキルや社会性などに問題のある「アスペルガー症候群」を含む「自閉症スペクトラム障害」、特定の能力(読み書きや計算)の習得に問題のある「学習障害」などの総称だ。明確な原因は現在のところ不明で、脳機能障害であるため本人の性格でもなければ家庭環境や心的外傷なども関係ない。治療は困難であるものの「調整」は可能であり、かつその能力を発揮できるように本書には著者が診察してきた事例と「周囲の対応案」が記されている。思い通りにならないとカッとなって暴言を吐く上司や、怒られても反省せず懲りずに同じ失敗を繰り返す同僚あるいは部下に悩まされているようなら、相手が発達障害でなかったとしても役に立つだろう。
本書を読んだ感想として私が強調しておきたいのは、本書で繰り返し勝手に相手を発達障害と断定することを戒めている点だ。法的に診断できるのは医師だけであるし、医学的な面でも発達障害の診断は難しい。本書には、主な診断基準や診断のためのヒントとなる質問表が資料として載っており、むしろ自分のことを調べるのに役に立つと思われる。というのも発達障害の特徴の1つとして、トラブルの原因が自分の側にあるとは気づかないことが多いからだ。そして、「本人はなかなか認めたがらず病院に足を運ばない」うえ、発達障害は他の精神疾患である、うつ病や統合失調症を併発する可能性を孕んでいる。そのことを考えると、自分が発達障害かもと思ったら、本書にもあるようにまず心療内科か精神科で診察を受けることが必要だろう。家族などの愛情を軸にした関係の中であれば苦労も共有してもらえるかもしれないが、職場での人間関係においては便宜的に振り分けられた他人との共同作業が必要になり、業務を達成しなければならない条件があるためトラブルに発展しかねない。著者は症状の改善に、本人が認める「認知」と受け入れる「受容」が必要だと述べており、何か大きなトラブルに遭って気落ちしている中で受診するよりも、落ち着いて話を聞けるときに行ったほうが良いはずだ。
文=清水銀嶺





