レストランのレビューも闇取引も信頼が重要。新しいビジネスを生む“信頼”はどう作る?
公開日:2018/9/19
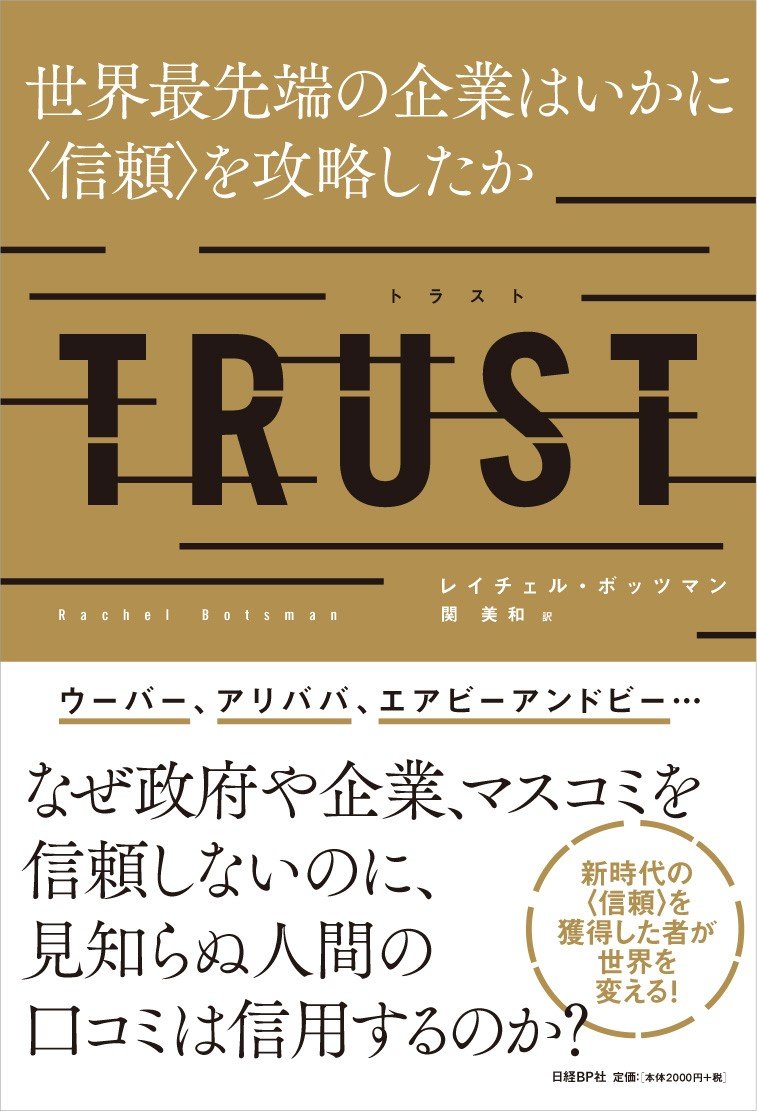
約10年前に発刊された『シェア』は、その後のカーシェアやエアビーアンドビー、Uber(ウーバー)などに代表されるシェアリングエコノミーの到来を予言し、それは近年さらに爆発的に拡大している。本稿で紹介する『TRUST 世界最先端の企業はいかに〈信頼〉を攻略したか』(レイチェル・ボッツマン:著、関 美和:訳/日経BP社)における、同著者の掲げるキーワードは「信頼」だ。従来型の制度への信頼の崩壊、分散された信頼の生まれる条件、そしてブロックチェーンの未来までを取り上げる。「信頼」を軸に、最先端の興味深い動向がギュッと詰まった1冊である。
■新しい「信頼」の形とは
少数の人間が力を掌握し、閉ざされた扉の影で運営され、特定少数の人に対する信頼で成り立つ仕組みは、いまのデジタル時代には不向きであると著者は述べる。
身近な例だと、かつてはレストランの予約をする時は、友人知人のおすすめやグルメ番組や雑誌といった、直接知っている人か誰もが知っているメディアの情報に頼っていた。顔も名前も知らない他人のレビューを頼りにレストランを予約しようなどと思う人はいなかったはずだ。
それが今では、予約する前にサイトでレビューを見てから、という人が多く存在する。レビュアーはまったく見知らぬ他人だ。レビューを頼りに予約をするということは、消費者とレビュアーまたはサイト運営会社との間に「信頼」が存在するということだ。旅先での宿泊の予約も似ているかもしれない。
■著者が提案する「信頼の積み木重ね」とは
人々が信頼を構築する際に必ずたどる行動パターンを、著者は「信頼の積み木重ね」と呼んでいる。信頼の積み木は3つの段階で構成されており、まず(1)新しいアイデアへの信頼、次に(2)プラットフォームと企業への信頼、最後に(3)個人(現在は機械やロボットの時もある)への信頼だ。
中でもとりわけ重要なのは、新しい(それはしばしば突飛で奇抜だったりする)アイデアへの信頼だという。新しいアイデアが理解され、不確実性が減ってリスクが低くなり、新しいアイデアを採用した方が良いと判断されると、既存のものからの乗り換えが起こり始める。そこにインフルエンサーのおすすめが加わると、加速度的に拡散していくのだ。
■いまや闇取引サイトですら「信頼」が重要
本書では、「信頼」に関連するユニークなエピソードがいくつか紹介されているが、中でも際立っているのは闇取引における信頼性についてだろう。
ダークネットと呼ばれる隠れたIPアドレス空間で行われる闇取引では麻薬や銃、偽造パスポートといったありとあらゆる違法商品が取り引きされているそうだが、この闇取引においても売り手はレビューや格付けといった判断基準で評価されるそうだ。
さらには街角の売人が売っている薬物よりも、ダークネットで売られている薬物の方が不純物が少なく高品質という調査結果も出ている。買い手による評価をダイレクトに受けるオンライン取引では、低品質の商品を売るとすぐに低スコアという反応が返ってくる。こんなところでも「信頼性」の構築が重要というわけだ。しかもデジタル取引のダークネット上でも見慣れた信頼関係が働く状況は、非常に興味深い。
■著者の予言はまたまた当たるのか?
本書後半は未来へとつながる話で、ビットコイン、ブロックチェーンを取り上げる。ブロックチェーンは膨大な数の人が共有する巨大な電子台帳で、インターネットに接続できる環境であれば誰でも参加できる。限られた人や組織が支配したり修正したりはできず、オープンかつ恒久的なデジタルデータのため、人々はその正確性に対してお互いを信頼し合える点が重要で、これは今までになかった信頼の形だ。
著者は、「10年かそこらもすればブロックチェーンはインターネットのような存在になり、それなしでは社会がどう機能するのか想像もできなくなる。ブロックチェーンはわたしたちがどう価値を交換し、誰を信頼するかを一変させるだろう」とまで述べている。
前作の『シェア』同様、著者のこの予言が当たるのかどうか、ワクワクしながらブロックチェーンを見守ることになりそうだ。本書はインターネット上の最先端やビジネスの動きを知りたい人からブロックチェーンに興味のある人、さらに前作『シェア』をおもしろいと思った人まで幅広くおすすめできる1冊である。
文=滝川 有紀





