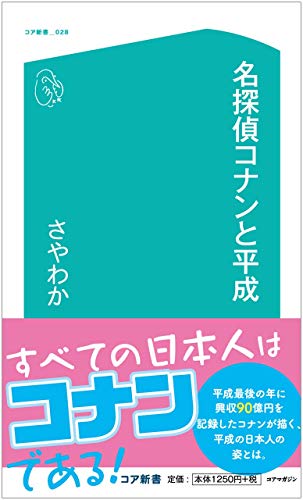平成の『名探偵コナン』を“風俗と文化”で考える。登場人物と自分を重ねてみると――
更新日:2019/5/13
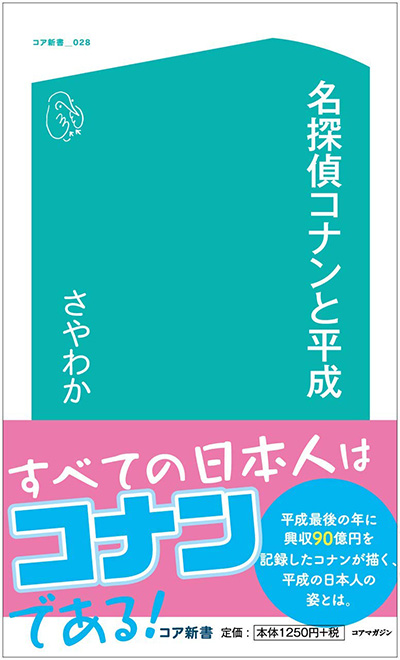
1994(平成6)年から『週刊少年サンデー』(小学館)にて連載が開始されている『名探偵コナン』(青山剛昌/小学館)は、もはやどんなマンガか説明するまでもないほど、老若男女から熱い支持を得ている国民的人気作品だ。その人気はコミックだけにとどまらず、2018年に上映された『ゼロの執行人』は、興行収入90億円という映画史上に残る大ヒットを記録した。
そんな『名探偵コナン』は平成初期から連載されている作品であるからこそ、作中には“平成の私たちの姿”が収められている。『名探偵コナンと平成』(さやわか/コアマガジン)は、そうした斬新な着眼点のもと、平成の日本人の姿や平成という時代を振り返る1冊だ。
著者であるさやわか氏は、『名探偵コナン』の連載第1回目に描かれていた、主人公の高校生探偵・工藤新一とガールフレンドの毛利蘭のやりとりに激しく心を動かされたという。
蘭は推理オタクの新一に対して、推理小説が好きなら探偵ではなく小説家になればいいだろうと言う。すると、新一はこんな言葉を返すのだ。
“オレは探偵を書きたいんじゃない…なりたいんだ!!平成のシャーロック・ホームズにな!!”
固定観念の枠に収まろうとしない新一の台詞に痺れたさやわか氏は『名探偵コナン』は平成の生き証人のようなものだと感じ、作中のあちこちに潜在する“平成の刻印”を見出したいと考えたという。
平成は、人々の価値観が多様化し、日本人のライフスタイルにも大きな変化が現れた時代。『名探偵コナン』の中には、そんな変わりゆく平成の風俗や文化がしっかりと描かれている。
■サスペンスの中に描き出された“平成の象徴”
殺人事件をテーマにしたマンガは世に多くあるが、『名探偵コナン』では毎回トレンドや世相を意識したトリックが使われている。例えば、『ゼロの執行人』ではインターネットに接続されている家電や機械を乗っ取って人を殺すという“IoTテロ”が物語の肝になっていた。
旬の技術や世相が反映されているからこそ、『名探偵コナン』を読めば、平成がどんな時代で、どのような文化を築き上げてきたのかが分かる。時代の移ろいと共に、作中にかつて出てきたPHSはスマートフォンに変わり、テレビやパソコンなどの家電はどんどんコンパクトになっていった。
平成という時代の進歩は阿笠博士が生み出す発明品からも読み解ける。例えば、コミック7巻に描かれていた「弁当箱型FAX」は、メールの普及という世相に伴いたった1回きりで登場しなくなった。
今の私たちにとっては当たり前にも感じられるが、平成の科学は時間をかけて進歩してきた。『名探偵コナン』はそんな事実にも気づかせてくれる作品なのだ。
■毛利蘭と世良真純に見る“平成の女性像”
犯罪捜査と人間ドラマが入り乱れる『名探偵コナン』は“殺人ラブコメ”という新しいジャンルを築き上げた。ヒロインとして重要な役割を担っている毛利蘭は、平成を理解するためにも欠かせない存在である。
『名探偵コナン』の連載が開始された平成初期は、「セクシャルハラスメント(セクハラ)」という言葉が流行語大賞の新語として認知され始めた時代。この頃から、性についての社会問題は徐々に変わってきた。
そんな変化や女性の進出を象徴するかのように、作中に登場する女性たちはみな一般的なラブコメマンガのヒロインとは違い、内なる強さを秘めている。蘭に至っては、初登場のコマで“電柱を殴って破壊する”ほど。自分で身を守り、犯人を倒す力強さを持った“脱・大和撫子”は、平成の女性たちのたくましさや意志の強さを代弁しているかのようだ。
また、蘭の同級生で「ボク」という一人称を使う世良真純も、時代を語る上で欠かせない重要なキャラクターだろう。彼女が初登場したのは、今から8年前の平成23年。「男はこうあるべき、女はこうあるべき」という固定観念にしばられない世良はジェンダーフリーの思想が広まる近年の世相を反映している。
生まれ持った性別を変えることは難しいので、自分の性に違和感を抱いていたとしてもどう生きていけばよいか苦しくなってしまうものだろう…。しかし、世良の姿を見ていると、「ありのままの自分で生きていけばいいんだ」とホっとすることができる。『名探偵コナン』は、平成という時代を巧みに描き続けてきた作品であり、悩める平成の人々に明るい希望を与えてくれる「人生指南本」でもあったのだ。
新元号「令和」が決まり、間もなく平成という時代は幕を閉じる。だが、『名探偵コナン』を手に取れば、いつでもがむしゃらに平成という時代を駆け抜けてきた“自分自身”に出会うことができる。私たちはみんな『名探偵コナン』に登場する“誰か”だったのだ。
文=古川諭香