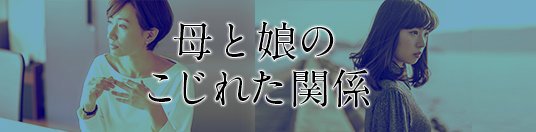「家族」としての親子、「他者」としての親子 ――『親子の手帖』著者・鳥羽和久さんインタビュー
公開日:2018/5/11
福岡市中心部で、小中高生が通う学習塾「唐人町寺子屋」を経営する傍ら、文具・食品・本を扱うセレクトショップ「とらきつね」、そしてイベントの企画にも関わる鳥羽和久さん。塾の生徒やその親たちと接する中で蓄積してきた思いを、フィクションの形で『親子の手帖』(鳥影社)にまとめあげた。どのような思いで本書の完成に至ったのか、お話を伺った。

思春期の子どもたちに「塾の先生」として接すること
――学習塾を経営されていながらも、本書の内容がドキュメントではなくフィクションであるのが特徴的ですね
鳥羽さん:関わってきた子どもたちやその親たちを、私が書くことで誰も傷つけたくなかったのが、その大きな理由のひとつです。プライバシーの問題も当然ありますし、フィクションという形態をとらざるをえなかった面もあります。
しかし、私自身は、フィクションだからリアリティがないとは全然思っていなくて、むしろフィクションだからこそ伝えられることがあると常々考えていました。今まで見てきたたくさんの親子がうみだした何百ものパーツのパズルを、一旦分解して組み立て直す。そうした作り方をフィクションだからこそすることができました。
――タイトルに「手帖」という言葉が使われているのも、鳥羽さんのアプローチに関係しているように思えました。
鳥羽さん:はい。手帖は、いつも携えておくものなので、自分のそばに置いてほしいなと思ってタイトルに入れました。現実的に置いてほしいという意味、そして抽象的に、頭の片隅に置いておいてほしい。そんなニュアンスです。決して、内容を私の考えの押し売りにはしたくありませんでした。「こうすればこうなる」といったような定式ではなくて、ただ寄り添うようなものを書こうと心がけました。
――「子どもは、親が言わないことを聞いている」という鋭い洞察がありました。親子といえども他者ですが、塾の先生、つまり明確な他者として子どもたちに関わられてきたことは、こうした観点に影響しているでしょうか。
鳥羽さん:おっしゃる通り、塾の先生は、親と子の関係とは違う距離感を持てる立場です。そこが本書を書く上での難しさでもありました。そういう人間が親子について書くことは、下手すると傲慢な作業になりかねないからです。
今は親子の関係が近すぎるせいで、いろいろな問題が起こると思っています。かつて子育ては、大家族や地域が前提とされていて、親子は非対称的な関係だという理解がありました。しかし、今はそれが対称的で密接な関係として成り立っているのかのような錯覚があると思います。
親が悪いとかそういうことではなくて、そういう風潮になってしまっているのだと気づく必要があると思います。この本を子どもに読ませたくないと思う親もいるかもしれませんが、そういう対称性を崩す「雑音」を親子の間に入れたいという思いがありました。
親が「言葉で教えること」ができなくなる、思春期の難しさ
――本書のテーマとなっているのは10歳以上から思春期にかけての子どもたちとその親に関してですが、この時期の子育てにはどのような難しさがあると思いますか?
鳥羽さん:親子のパワーバランスがあるとすると、10歳前後から子どものほうが段々と強くなってきます。15歳ぐらい以降は、基本的に子どもに決定権を預けるスタンスであるべきだと思います。
10歳以降で特に難しいのは、親が「何をやってきたか」でしか教えられなくなることです。言葉で言うことできないもどかしさを親が感じるほど、理想から逸れていってしまうかと思います。職人と見習いの関係のような形で、「自分の為人(ひととなり)がこうだから、子どもにこういうふうに伝わる」という流れを、親は引き受けるべきなのだと思います。
――受け持たれている生徒さんから、本書の感想を聞きましたか?
鳥羽さん:親御さんからの感想は多く頂いていまして、高校生では一人だけ感想を教えてくれた子がいます。「僕が出てきた」と話してくれたので、「気づいたね」と言いました。フィクションなので、本人がそのまま登場しているのではなく、感情移入できるキャラクターが出てきているんですね。
――私は、カンニングの話が特に印象に残りました。注意する側の立場になったことがありませんが、想像してみると注意の仕方はとても難しいなと思いました。
鳥羽さん:カンニングは指導の難しさを凝縮した感じがあると思います。カンニングにもいろいろな程度がありますが、カンニングせざるをえない子たちがいて、そのケースが気になっています。出来心では済まされないものです。自分で何がいけないのか気づいて直していける子もいて、そういう場合こちらはその過程を見守るだけでいいのですが、親の圧みたいなものがカンニングという形で出ることがあります。子どもがかわいそうで痛々しい。「何でこんなに自分を偽らなければいけないのだろう?」と。
カンニングに限らず、間違っている時の言い方はすごく難しいと思います。悪いと言うのも大事ですけど、それよりも間違いをひとつの考える機会にしたいですね。
――生徒さんが塾を巣立っていって、「私の知っているのはここまでです」と終わる文章がありました。生徒さんと他者である関係、塾である立場をよく示していると思いました。生徒さんのその後や、再訪などで何か思い出深いエピソードがあったら教えてください。
鳥羽さん:つい1~2週間前のことですが、東京の大学に通っている子が再訪してくれた時に、本書の話から、どうやっていじめを解決するかが話題になりました。「いじめる側」「いじめられる側」というような構図では解決できない点について、私は地政学的な考えを紹介しました。たとえば、北朝鮮がミサイルを撃つのは「そうなってしまっている」状況ですね。今までの歴史を見ると「そうなってしまっている」力の大きさ、致し方なさが存在します。学校でいくら指導しても、その指導にそういう視点が欠けていると、生徒は何も理解したことになりません。
その話をしている時に、その子が「中高時代、母親との関係にとても苦しめられたけど、母親が、致し方ない、そうならざるをえなかったほどのストレスを当時持っていて、それによって自分が追い込まれたのが今となっては理解できる。この本を読んでそれを言う気になった」と話してくれました。「そうやって見ることができるようになれて、良かったね」と、その子に話したことを思い出しました。
――塾とセレクトショップ「とらきつね」を一緒に経営されていて、とても珍しい経営形態かと思いますが、そのいきさつを教えてください。
鳥羽さん:開塾して13年目にはじめました。その2年ほど前に、単位制高校をはじめたのが大きかったと思います。これは、高校を途中でやめた子のセーフティーネットとしての役割があります。そういう子たちは、うちに来て友達も少ない状態で勉強しますが、それでは何も楽しくないので、何か刺激を与えたいなと思っていました。人生はいろいろ道筋があると知ってもらえる、仕掛けを作るんです。
「親子」というのは、ひとつの関係性に名付けられた名前でしかない
――母の日・父の日は親子の日と言ってもいいかと思いますが、何か母の日・父の日に関して思われることはありますか?
鳥羽さん:子どもたちがプレゼントを「とらきつね」に買いに来る姿は、本当にかわいらしいですね。それが一番好きかもしれません、プレゼントを選んでいる光景を見るのが。何でそんなにいいんでしょうね(笑)。結局、子どもが親のことを好きと素直に言うのとか、親のために何かやっているのが私たち大人は好きなのだと思います。親と子は言ってみれば他者なわけですが、学校で書かされた手紙であっても泣いてしまうのが親ですよね。そういった親子の関係にある一面も、また面白いなと思っています。
――さきほどの地政学の話ではないですが、父の日や母の日には日々揺れ動いている親と子の間のパワーバランスを、一歩立ち止まって考え直すことができますよね。
鳥羽さん:特に、思春期の子たちにとってはそれぐらいしか機会がないですからね。しかもどうするかは子どもに委ねられているのがいい点ですよね。
――特に女性にとっては、子どもを持つことと同時に、「産む」「産まない」「産めない」、そうした選択や運が人生に関わってきます。「子を持って一人前」という考えはいまだ根強いですが、そうした風潮は、現代社会においては一人の子どもに関わる他者の幅を狭めているようにも思えます。
鳥羽さん:私も子どもがいないのですが、この本に最初に食いつくのはやはりお母さんたちなんですね。そこから二歩三歩下がった形で、私も触れていいかしらと、まだ結婚していない方たちが近寄ってきます。でも、「親子」はある意味メタファーで、ひとつの関係に名付けられた名前でしかないと私は思っています。親子のことを書いていますが、「関係自体が私なんだ」という立場から、「関係」について書いたのがこの本です。たまたま私にとってそのメタファーは親子だっただけです。子どもがいない人にとっても、「関係」は同じ切実な問題なので、全くそこに境界はないと思います。子どもがいないと人生損していると考える人が当然いるにしても、それを言ってしまうのは違うと思っていて、それぞれの関係の結び方があると思います。
もし自分に子どもがいたら書くスタンスが違ったと思います。この本の特徴は、子どもの立場から書いたのか、親の立場から書いたのかわからなくなる場面があることですが、世の中にはどちら側からかに視点を限定して書いたものが多いですよね。そういう意味で、この本は少し変わっていますね。
――鳥羽さんだからこそ書ける内容、ということですね。
鳥羽さん:(笑)
「親子はこうあるべきだ」と決まっているわけではない。そうと心の中ではわかっていつつも、私たちは理想や一般像にしばられてしまいやすい。本書はインタビューにも記載の通り、読者に寄り添うように、方法論や価値観の押しつけなく、「親子」ひいては「人と人との関係」そのものに自由に思いを巡らすことができる一冊だ。
取材・文=神保慶政