理由なき拷問にあう世界――終わりの見えないシリアで生きるとはどういうことか
公開日:2017/6/30
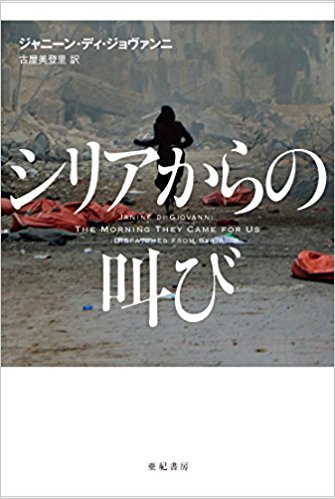
生きながらにして切り刻まれるという体験は、日本では手術以外にそう味わえるものではない。しかし、世界を見渡してみれば、政府がこれを拷問として行っている国がある。シリアだ。
シリアは、トルコ、イラク、ヨルダン、レバノン、イスラエルらと国境を接する共和国で、2011年から内戦状態に突入、現在も収拾がついていないどころか終わりがまったく見えていない。日々市街地で銃弾が飛び交うありさまで、在シリアの日本大使館は平成24年3月をもって一時閉館となっている。
『シリアからの叫び』(ジャニーン・ディ・ジョヴァンニ:著、古屋美登里:翻訳/亜紀書房)は、このシリアで一般市民がどのような生活を送っているのかを取材したノンフィクションだ。ちょうど今年の5月に、米国務省ジョーンズ国務次官補代行が、“シリアのアサド政権が、囚人を大量に拷問・殺人している証拠を隠滅するために、サイドナヤ軍事刑務所内に火葬場を建設して、彼らの遺体を処分している”と発表したばかり。本書はこの発表以前の発行だが、現地での市民インタビューから刑務所内のようすを聞き取っており、目のつけどころが際立っている。ここでは、ひとりの若者が著者に語った拷問のようすを紹介しよう。
Fは取材当時24歳。内気で優しそうな物腰の、法律を学ぶ男子学生だ。父は公務員、兄弟たちもみな大学教育を受けている。兵士というイメージからは程遠いFだが、胸には深くて大きな傷がある。理由は、生きながらメスで切り刻まれるという拷問を受けたから。彼はいったい何をしでかしたというのだろうか。
「最初は、自由と人権を求めていたんです」。Fは大学内で、独裁政権への批判をしつつも、武力を用いることには反対の立場だったという。スローガンを掲げての行進とシュプレヒコールで、アサド大統領の独裁を批判していた。しかし、こうした平和的なデモが、やがて武器を手にした反政府軍となってしまう。Fは運動から距離を置いた。しかし、なぜか突然Fは逮捕され拷問された。内容は、意識がはっきりしている状態での、感電・殴る・やけどができるように火を近づけるなどだ。加えて、そう、彼は切り刻まれたのだ。
まずは、ペニスを剃刀で傷つけ出血させられる。それから膀胱を力任せに押して無理やり尿を出された。次に、外科用のメスが腸に当てられる。「それから奴らはぼくの体から何かを引っ張り出した。(中略)腸だ。それを引き延ばした。奴らはそれを手でつかんで、体の外へ出した。(中略)(周囲にいた兵士が)こいつの腸の中にはすげえ大量の食い物が入っているぞと冗談を言った。それからぼくを縫い合わせた。しかしいい加減なやり方をしたので、皮膚と血がいたるところにこびりついていた」。
加えて苦痛だったのは、精神的な問題だった。なぜ自分が逮捕されたのだろうか? 反体制派の誰かが自分の名を売ったのだろうか? 「自分がすっかり裏切られたような気がした」。シリアという国に、シリア人に、政府に、同胞に、民主主義を求める平和的な抗議に暴力をもたらした者たちに――。それは、自分は公平に扱われていない、自分がしなかったことで罰せられている、という感覚だったという。
Fが刑務所から出られたのは、政府側の医師の出来心のおかげだ。ある日、Fの生死を確認しにきた医師が“ひとり言”をつぶやいたのだ。「私はアサド政権を支持している体制側の医師だ」「私の仕事は、(中略)さらなる拷問に耐えられるか確認することだ。しかし、もうこれ以上見ていられない」と。そして記録用のノートを手に、「おまえは死んだんだ」「いま私が言ったことがわかるか? おまえは死んでいるのだ。この記録によれば、おまえは死んでいる」とも続けた。医師が自分を助けようとしていると気づいたFは、生きたまま死体となり、死体置き場に運ばれた。そして、焼却までのわずかの間に、死体の山から抜け出したのだという。
現地のようすが生々しく伝わってきて、人間という存在の愚かさを考えさせられる本書。これまで、政権争いや宗教対立を理解することが難しいがために、注目できなかったシリア情勢。しかし、一般市民の具体的な語りなら、シリアに興味をもちやすい。日本から遠い国のことと流さずに、これからの情勢に注目していきたい。
文=奥みんす





