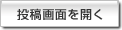2005年03月号 『明日の記憶』 荻原浩
更新日:2013/9/26

あまたある新刊の中から、ダ・ヴィンチ編集部が厳選に厳選を重ねた一冊をご紹介!
誰が読んでも心にひびくであろう、高クオリティ作を見つけていくこのコーナー。
さあ、ONLY ONEの“輝き”を放つ、今月のプラチナ本は?
2005年02月05日
『明日の記憶』 荻原 浩 光文社 1575円

一人称で語られる文体と、挿入される彼の備忘録は、ゆっくりと記憶を失っていく彼の病状を緻密に描写しており、悲しみと寂寞さを際立たせる。
おぎわら・ひろし●1956年埼玉県生まれ。広告制作会社を経て、97年『オロロ畑でつかまえて』で第10回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2002年『コールドゲーム』が山本周五郎賞の候補作となる。他の著書に『なかよし小鳩組』『ハードボイルド・エッグ』『誘拐ラプソディー』『メリーゴーランド』『僕たちの戦争』がある。
横里 隆
(本誌編集長。『明日の記憶』のラストはすごくよかった。あと、ばななさんの新刊『なんくるない』収録の「ちんぬくじゅうしい」もめちゃめちゃよかった。激オシです)
過去の思い出をすべて失っても
あなたは生きていけますか?
ひと昔前、卒業前に海外へ旅行する学生たちのことが、「思い出作りに奔走する若者たち」と揶揄されたことがあった。風説に同調した僕も、思い出にすがって生きるなんてカッコ悪いと思った。……若かった。今ならわかる。人は思い出にすがって生きるのだ、と。たったひとつの輝く思い出を糧に暗澹たる今日を生きていくこともできる。しかしこの小説の主人公は病によって生きる糧である記憶を失っていく。著者は問う、“過去の思い出”をすべて失ってもあなたは生きていけますか? と。僕は答えに窮しながらも、僅かな“未来への希望”さえあれば、と答えたい。そう、人を生かしているのは“今この瞬間”ではなく、“思い出”や“希望”だったりする。その意味で“過去の思い出”と“未来の希望”は同じものなのだ。そして“未来の希望”は言い換えると“明日の思い出”、すなわち“明日の記憶”となる。いいタイトルだ。だからこそ物語の最後は柔らかな希望に彩られる。たまらなく切なくて、ゆえに美しくて、忘れられないラストシーンだった(涙)。
稲子美砂
(本誌副編集長。主にミステリー、エンターテインメント系を担当)
絶望の中で希望を模索する
著者の意欲作
主人公・佐伯の「スーツのすべてのポケットは~未整理のメモでふくらんでいる」という描写を読んだときに、小川洋子さんの『博士の愛した数式』の博士のことを思い出した。80分で記憶を失ってしまう博士も背広にたくさんのメモをクリップで留めていた。博士にとって数学を究めていくことがある種の生きがいであったように、佐伯にとっては陶芸が自分の存在を確認させてくれる拠りどころとなっていくのだろう。著者の荻原浩さんに取材させていただいたとき、芸術的な感覚というものはアルツハイマーになっても損なわれないという説があるという話をうかがった。「頭は記憶を失っても、体には記憶が残っている。私にはまだ動く指がある」と、佐伯は土をこね、成形しながら、自分を奮い立たせる。アルツハイマーという不治の病、自分を失っていくという絶望の中で、どうにか希望を描けないか。そこに挑戦した荻原さんの意欲作だと思う。
岸本亜紀
(怪談、ミステリーを担当。『幽』2号が出ました。充実のラインナップ。真冬の怪談、なかなかいいですよ。全国の書店、ネット書店で好評発売中)
記憶を失っていく過程
残された時間を
どのように過ごすのか
ここ5年くらい、飲むと記憶を無くす。どうやら年齢に関係なく、そういう人が増えているようだ。飲み会での与太話で済ませている話だが、この本に書かれている症状を読めば読むほど、もしかしたら自分も……とそわそわさせられる。そしてもし自分があるいは家族がそうなったとき、家族の支え、社会での人間関係、自分が生きてきた意味、人間性を喪失していくという現実をどのように受け止めていけばいいのかという深刻な問題が迫ってくる。主人公は、妻や娘に弱音をはかない。それは迷惑をかけないようにとの配慮なのだろう。だからこそ物語のラストがまるで美しい絵画のように読者を感涙に誘う。大変なのは、きっとその後なのだろう。人が人でいた最後の瞬間を美しく描いてくれた作者の深い思いが伝わってくる。
関口靖彦
(先ごろ3巻が発売された『シグルイ』〈山口貴由 秋田書店チャンピオンレッドC〉が最狂。自分の中の凶暴性がうずいて、はらはらします)
人の儚さと強さの両方を
感得させるラストシーンが
深い余韻を残す
やばい、これ俺だよ。と、読みながら背筋が粟立った。毎日のように顔を合わす人の名前が出てこない。立ち上がった瞬間、何をしようとしていたか忘れる。度し難く物忘れのひどい私には、思い出らしきものも断片的にしかなく「そんなになんにも覚えてないなんて、今までのつきあいに意味がないみたいだね」と哀しそうな顔をされたことが何度もある。主人公も私もうろたえる。俺の存在が、俺の中から消えてしまう、と。ところがそうした恐怖の中ですら、人は生きるよすがを見つけ出すことをこの本は確信させてくれる。人の持つ儚さと強さの両方を、あざやかな光景に浮かび上がらせたラストシーンが印象深い。
波多野公美
(祝・角田光代さん直木賞受賞! 角田さんのWEBダ・ヴィンチ連載は本好きの胸に迫る話ばかり。単行本も準備中です!)
最終回のない物語を
私たちは生きている
病を得た夫と一緒にいられる時間(彼の中で自分が記憶されている時間)がどんどん減っていくなかで、「もう俺のことはいい。俺がいなくなってからのことを考えろ」と言われた妻が、「ドラマみたいなこと言わないで。こっちには最終回なんてないんだから」と泣くシーンが心に残った。ひたひたと満ちてくる絶望を感じ取りながら、懸命に生きる二人の姿は、時に泣きたくなるほど美しい。けれど、これは普遍の物語だ。誰の人生も彼らと同じだ。最終回は予告されない。物語の終わりを誰も知らない。どんな絶望が襲いかかっても、私たちは自分の人生を生き抜かねばならないのだ。生きることの意味を考えさせられた。
飯田久美子
(とはいっても、ボケないに越したことはないので、アルツハイマー防止に効くと本の中に書いてあったブロッコリーをいっぱい食べてます)
自分が自分でなくなっても
生きる意味はあるのか
喫煙がアルツハイマーの防止になるらしいという風説がでてくるくだりを読んで、禁煙してる人に煙草をすすめようと思ったけど、やめた。ボケてしまったとしても、自分のことを忘れてしまったとしても、長生きしてほしいと思ったから。そんなこというと、たとえば、介護する側の厳しい現実をわかってないからだとかいわれそうだけど。でも、若年性アルツハイマーを患者の一人称で綴ったこの小説は、これから待ち受ける悲惨な現実を予感させながらも、周囲の人たちにどんなに迷惑をかけたとしても、自分が自分でなくなったとしても、それでも、ただ生きている、それだけがいかに価値あることかを教えてくれる。特に、ラストは、何を忘れてしまっても、大事なことはなくならないと思えて、いい気持ちがした。
宮坂琢磨
(そろそろ豚磨に改名したほうがいいんじゃないと姉にいわれた。ブヒ)
過去の思い出が
とてつもなくいとおしく思える
今の自分を形作っているものは紛れもなく記憶である。女の子に泣かされたり、快速電車で1時間近く尿意に苦しんだりといった、心から忘れたいと思う記憶でさえも、今の自分を形成する大事な要素である(今の自分に問題があるかどうかは別にして)。その喪失は自己の死にほかならない。この主人公は、アルツハイマーを自覚しながらも、人との思い出を必死で守ろうとする。それは、こぼれ落ちる水を手で割れビンに戻すようなものだ。指の隙間からこぼれ落ちる記憶を必死でかき集める彼の姿が、失った先にも幸せの別の形が、たとえあるにせよ、僕にはあまりに悲しすぎるのだ。
 『キョウコのキョウは恐怖の恐』 諸星大二郎 講談社 1680円 |
裏路地に迷い込んだような恐怖
宮坂琢磨
|
イラスト/古屋あきさ

読者の声
連載に関しての御意見、書評を投稿いただけます。
投稿される場合は、弊社のプライバシーポリシーをご確認いただき、
同意のうえ、お問い合わせフォームにてお送りください。
プライバシーポリシーの確認