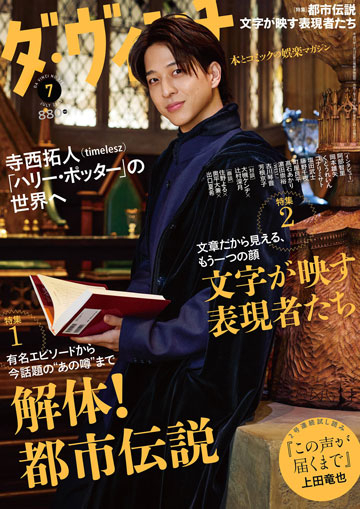発達障害の子どもが授業で困難を覚えたとき、スマホやタブレットの活用による支援を学校に相談するには?
公開日:2020/1/22
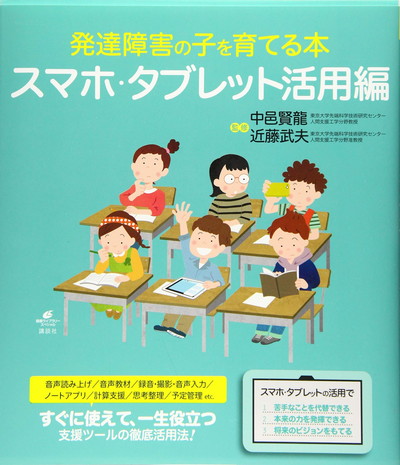
スマホやタブレットを使って、学校の授業を受ける子どもが増えているという。ハイテクな授業を受けているわけじゃない。発達障害がある、もしくは授業を受ける上で何かしら困っている子どもたちが、テクノロジーによる学習支援を受けているのだ。
発達障害がある子どものなかには、読み書きや計算などが困難なために授業についていけない子がいる。そうした子は、どれだけ努力しても困難が解消しないと、やがて自分に自信をなくし、心を閉ざしてしまうことさえある。
しかし、スマホやタブレットなどのツールを活用すれば、子どもたちの困難を減らすことができる。『発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編』(中邑賢龍、近藤武夫:監修/講談社)は、そうした学習支援の方法を、イラストや図解を交えながら分かりやすく解説する1冊だ。
■学校で活用できるツールはたくさんある
本書は、発達障害の子の学習支援のために特別な機器を購入することを求めているわけじゃない。家庭にあるごくごく普通のスマホやタブレットなどを、子どもに必要な支援に応じて活用する方法を紹介している。
例えば文字や文章を読むのが苦手な子どもには、音声読み上げソフトやアプリが活用できる。本書に登場するのは、「VoiceOver」や「TalkBack」などだ。スキャナで読み取った印刷物を音声読み上げ用のテキストデータにできるのが「Office Lens」。紙の教科書を使うのが苦手な子ども向けに、教科書を音声で聞ける音声教材もある。これらを活用すれば、学校の教科書やプリントが読めなくて苦労している子どもの学習を支援できる。
板書を書きとったり、先生の話を聞きながらメモを取ったりするのが苦手な子どももいる。そんな子どもには、スマホのカメラや録音アプリを活用する方法がある。
計算や筆算が苦手な子どもには、計算アプリや、筆算支援アプリが活用できる。会話や作文が苦手な子どもには、考えを図にまとめて整理する「マインドマップアプリ」を使う方法がある。
大切なのは、子どもが授業に困難を覚えたときに、苦手なことを無理にがんばらなくてもよい、と伝えることだ。そして、問題を解消できるような代替手段を示してあげること。それぞれの子どもにあったツールを探して、積極的に試してみよう。
本書によれば、小学校1年生からスマホやタブレットの基本的な活用ができるそうで、学習に苦手意識が出てきたら、家庭内の日常生活でツールを活用し始めることを勧めている。特に高学年になると学習の難易度が上がるので、必要と感じたらできるだけ早く検討したい。
■入試でツールの活用を認めてもらえるかもしれない
ただ、ツールの活用を検討するだけでは、子どもの支援につながらない。子ども本人の意欲や周囲の支えが不可欠だ。特にスマホやタブレットを学校の授業で活用するなら、教師をはじめとする大人たちの連携が不可欠だ。
本書では、教師に授業を受ける上での困難を相談し、実際に子どもが授業でツールを活用するまでの大まかな流れを解説している。どのような困難が生じているかの状況確認、使用する機器や場面などの環境確認、使用するためのルール作りなど、話し合うことは多岐にわたる。
「そもそも授業でスマホを活用することが許されるの?」と戸惑う人もいるだろう。それに関しては、心配ない。2016年に「障害者差別解消法」が施行され、発達障害などの障害がある人に対し、公立学校は「合理的配慮」をすることが法的な義務となった。だから親や子どもが必要だと感じたら、本人と一緒に先生に相談したい。
ただし「合理的配慮」は明確に線引きされているわけじゃない。子どもが授業で困難を覚える場合は配慮の対象となるが、参考情報として「明らかに支援が必要だと現認できる様子」が見られたり、「適切な判断基準に基づく医学診断書」が必要となったりする場合もある。
本書では、進級先での「移行支援」や入試での合理的配慮の申請例についても解説している。近年は、入試で合理的配慮を相談する子どもが増えているそうだ。例としては、高校入試の場合は、中学校から受験先の高校へ合理的配慮を申請する場合が多く、大学入試の場合、本人から受験先へ申請するケースが多い。注意点として、診断書が必要になる可能性がある上、その診断自体に数カ月かかる可能性もある。本書では、申請までのスケジュールの一例も紹介されている。
学習支援にスマホやタブレットを使うのは、視力の低い人が眼鏡を使うのと似たようなものである。ツールを活用することで、子どもたちはもっと勉強しやすくなるかもしれない。もし、子どもが授業を受ける上で困難に直面していると気づいたならば、早めに検討してみよう。
文=いのうえゆきひろ