漂白剤を飲ませるDV夫を刺殺した妻。司法心理学者が見たドラマより凄惨で悲しい「犯罪者の心」とは?
公開日:2020/6/8
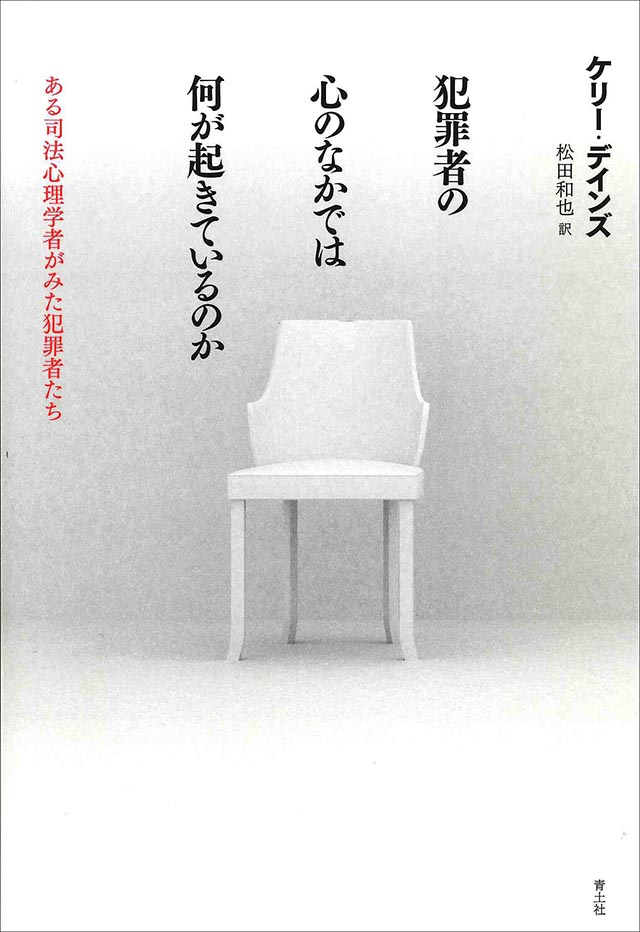
「犯罪心理学」は、海外ドラマで取り上げられることも多い。画面の中ではシリアルキラー役の俳優が凄惨な殺害現場を生み出し、視聴者はその異常性に息をのむ――だが、現実社会での犯罪者の心理はドラマよりもっと混沌としているという。
昔、大学で犯罪心理学を少しかじった時、その道に詳しい教授が私たち学生に「人はどうして殺人者になると思いますか?」と聞いた。この問いは筆者にとって衝撃的で、自分が犯罪者と私は違うのだと勝手に思い込んでいたことに初めて気づかされた。
そんな遠い記憶を呼び起こしてくれたのが、『犯罪者の心のなかでは何が起きているのか -ある司法心理学者がみた犯罪者たち-』(ケリー・デインズ:著、松田和也:訳/青土社)だ。本書は、私たちと犯罪者の間にある“壁”が、実は想像以上に脆く、曖昧な境界であることを教えてくれる。
犯罪者は「私たち」とは違う種類の人間なのだろうか?
司法心理学者である著者は本書内で自身のストーカー被害体験も交えつつ、これまでに出会ってきた犯罪者を紹介し、罪の裏に潜んでいる「犯罪者とならざるを得なかった理由」を解き明かしていく。
犯罪は許されない行為であり、罪は償わなければならない。だが、罪の責任は犯罪者だけにあるものなのだろうか。例えば、虐待や性差別などで長年心身を弄ばれた末に罪を犯してしまったのだとしたら、周囲や環境に責任はないのだろうか。
幻聴に悩まされ兄を殺害してしまった男性や、担当医をストーキングした女性など、著者が関わってきた犯罪者ははたから見ればある種の異常性を抱えているように思える。だが、犯罪者は“元被害者”であることも少なくないという。
特に印象的だったエピソードは、夫を殴って刺し殺したというアリソンの話。アリソンは常に批判的な母親に育てられ、自分は無価値な存在だと思い込んできた。そんな彼女が結婚した夫は、DV男。時には漂白剤を無理やり飲まされ、喉を火傷したこともあった。もとから自己肯定感が持てずにいたアリソンは夫から逃れることが日に日に難しく感じ、殺人によってやっと安息を手に入れたのだ。
彼女の心の傷につけられた「心的外傷後ストレス障害」「強迫性障害」「抑鬱症」といった病名は法廷で罪を采配する基準になったが、たった3つの病名だけで彼女の人生や犯罪の動機、心に抱えた苦しみを説明できるわけではない。
近年では日本でも犯罪の背景に“心の問題”が関係しているという認識が広まりつつあり、時には犯罪者の痛みに「病名」をつけ、罪に至った理由を解明し、矯正の手が伸ばされることもある。だが、アリソンのようにただ病名では表しきれない苦しみや傷を抱えている人がいたり、正しい診断がくだされなかったりする場合もあるからこそ、病名だけを重視した矯正では真の救済にならないこともあるだろう。
また、著者が見てきたという実際の矯正現場を知ると、病院や刑務所の矯正システムが、逆に新たなトラウマを植え付けてしまうのではないかと恐ろしくもなる。例えば、子どもの頃にNOと言う権利を奪われて心に傷を負ったという犯罪者に対して、矯正という名目のもと、再び従順で受け身な態度を求めることは、効果的な矯正だといえるのだろうか…。
罪に対する反省心を引き出し、悔い改めてまっとうな人生を送ってもらうには、犯罪者の「心」に目を向けた矯正が必要だ。そのためにはまず、私たち一人ひとりの意識も変えなければならないだろう。犯罪者を「私たちとは違う世界の人」と捉えるのではなく、なぜセーフティーネットからこぼれ落ちてしまったのか、何が彼らを犯罪に走らせたのかと考えることが大切なのではないだろうか。
“どの犯人も被害者も同じではない。それぞれの人が、語るべき重要な物語を抱えている。けれども、その物語を変えることは可能だ。予防はいつだって治療よりも良いのだから。”
差別的なレッテルをはがして、相手の人生と向き合う。それが一番の犯罪防止策になるはずだ。
文=古川諭香





