家族は家族を介護しなければいけないのか――認知症介護から知った「家族とは何か」のひとつの答え【読書日記23冊目】
更新日:2020/7/6
2020年4月某日
磯野真穂さんがTwitterで気になる投稿をされていた。磯野真穂さんは、宮野真生子さんとともに『急に具合が悪くなる』(晶文社)を書かれた方だ。病気とリスクの考え方について、人類学、哲学双方の視点からまさにボールを全力投球し合うような熱く愛ある“往復書簡”を拝読して以来、彼女のツイートを熟読している。
その日の気になる投稿というのは、「家族のケア」についてのものだった。
いま家族ケアについての論考を書いているのですが、家族ケアに悩む医療者・介護者は、ケアとは何かを考える前に、「家族」とは何かを考えた方がよいのではと感じます。
家族が何かわからないまま、家族をケアするのは難しくないでしょうか。
家族ほどわかりそうでわからない集団はありません。
そう書かれた投稿を見て、曲がりなりにも家族を専門領域にしていながら押し黙ってしまう私がいた。
これまで「家族とは何だろう」という問いの答えを求めてさまよってきた私だけれど、「これから家族をつくる視点」でしか考えてこなかった。最近、ご縁があって「セクシュアルマイノリティ×介護」をテーマにしたインタビュー連載を始めたものの、そんなお話をいただくまでは介護や老後についてなんて考えたことがなかったのだった。
――家族と介護
その言葉を聞いて思い出したのは、祖母に対する父の関わり方だった。

祖母は認知症でこそなかったが、足も腰も心臓も悪く、杖や押し車、ペースメーカーがないと生活できないのに、住み慣れた山奥の家から離れたくないと言って、父とヘルパーさんに週2~3回お世話されていた。
祖母の家は実家から車で1時間ほど離れたところにあった。北海道なので1時間の車移動はそう珍しいことでもないが、週に何度も買い物したものを届けに行く父の姿を見ていて「よくやるなぁ、すごいなぁ」と他人事のように思っていた。
祖母のことは嫌いではなかったけど、すごく好きだというわけでもなかった。窓際に座ってひなたぼっこする姿は猫のようでかわいいと思った。ただ、そのくらいの関わりで十分だった。だから、父がどうして祖母の“わがまま”に付き合っているのかわからなかった。
「家族だから」という“倫理観”や義務感に基づいてのものでないことは見ればわかった。だからこそ、もしも父や母に介護が必要になったときにそこまでしてあげられる自信がなく、そういう自分の薄情さや冷たさに向き合うのも嫌で、介護という話題を避けてきた。
そうしている間に、祖母は亡くなった。
葬儀のとき、父は泣いているように見えた。自分の親が亡くなったのだから泣いていてもおかしくないのだけれど、私はそれまで父が泣いたところを一度も見たことがない。以降も、父の涙を見た(かもしれない)のは、後にも先にもそのときだけで、その事実もまた、私の中の「介護」や「高齢者」にタブーの膠を塗った。死んだ祖母の気持ちも、当時の父の気持ちも、今の父の心のうちも、何もかもわからないまま触れられなくなったことが心の澱となって積もっていた。
父はどうしてあんなに祖母に手をかけていたのだろう、誰に頼まれたわけでもないのに。
そんな私への天啓かのように降ってきた、介護をテーマにしたインタビュー連載の依頼。そして、磯野真穂さんのツイート。続くツイートでは、1冊の本が紹介されていた。その本は、『家族はなぜ介護してしまうのか 認知症の社会学』(世界思想社)だった。
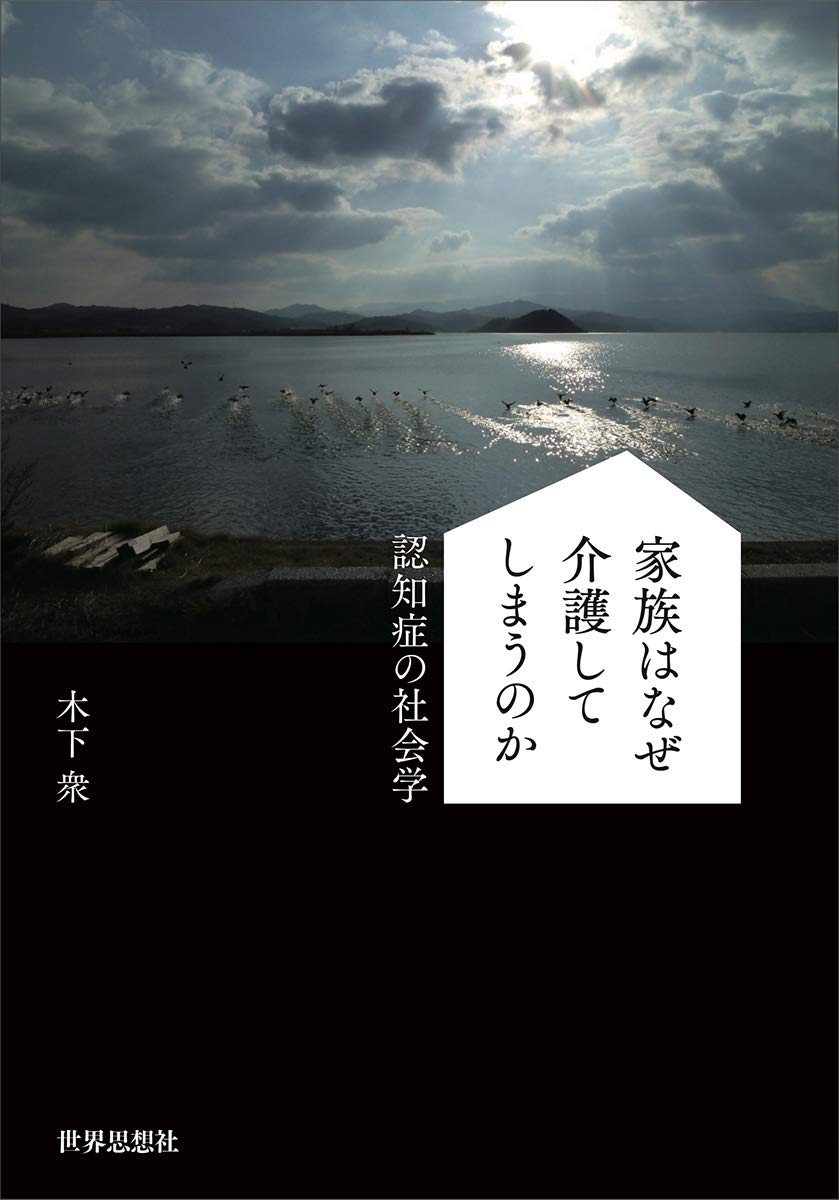
本書は社会学の専門書でありながら、認知症患者の家族介護について複数の事例をもとに書かれた本で、介護に関わる多様な立場の人たちに向けて開かれている。
分析内容も介護の進行になぞらえて「認知症に気づく」(2章)、「患者に働きかける」(3章)、「悩みを抱える/相談する」(4章)、「他の介護者に憤る」(5章)に分類しており、通して読めることはもちろん、介護者が関心に応じて拾い読みもできる構成になっている。
「はじめに」の第一声から「私は、家族が高齢者を介護すべきだとは思わない」と書いてあり、少しホッとする。公的サービスの縮小が、家族にケアの役割を押し付けるかたちになることには私もかねて違和感があった。
しかし、続く文章では「私の調査に協力してくれた介護家族たちも、家族が介護すべきだという考えはもっていなかった」としている。
じゃあどうして、と思う。
私はその先を読み進めた。
家族がなぜ介護をするのかという議論の前に、認知症の歴史に軽く触れておきたい。かつて(といってもそう古くはない1960年~1990年代にかけて)、認知症患者は、治療不可能な存在として身体拘束や投薬に偏った処遇を受けていた。
「現代の姥捨山」と専門家が厳しく批判した医療機関の処遇は徐々に社会問題化し、2000年代からは認知症患者の「その人らしさ」や個人の「人生」を大切にした「パーソンセンタードケア」が唱えられ始める。
「パーソンセンタードケア」に加え、それまでの「痴呆」という名称が「認知症」に改められ、「痴呆になると何もわからなくなってしまう」というかつてのイメージが誤りであると公言されることになり、これらが「新しい認知症ケア」と呼ばれるようになった。
家族がなぜ介護をするのかという議論に関しては、「日本では誰かが家族を『ケアしない権利』が想定されておらず、『ケアを代替・分有する資源』も乏しければ、そうした資源に『アクセス』する制度も整っていない」という「介護の社会化における問題」や、「家族介護は最善だ」という「家族介護規範」などが挙げられてきたが、本書で扱うのは、上野千鶴子氏の「ケア責任」という考え方である。
「ケア責任」とは、「介護保険制度を最大限利用している場合でも、要介護者にとって何が適切なケアか、要介護者が今何を望んでいるか判断する重要な責任が家族に付いて回ること」だ。
身体拘束や投薬など“監獄”のような従来の処置ではなく、その人らしさを大切にする「新しい認知症ケア」の時代にあるからこそ、様々な関わりの中で「ケア責任」が強化され、認知症患者にとって家族が代替不可能な存在に“なっていく”。それが本書の結論として第1章に書かれている。
「ケア責任」が強化される様々な関わりとは、認知症に気づく段階から始まる。たとえば、若いときから忘れっぽい人であれば、「いつものこと」で済まされることも、時間に対してキッチリしていた人が用事を1回でも忘れると「何かあったのかな」と心配になるように、認知症の気づきは患者のそれまでの立ち居振る舞いに参照されることが多い。
認知症に気づいた後も特定の食材を口にしない患者に対して「認知症になる前に口にしたことがない食べ物だから抵抗感があるのかもしれない」などと過去の日常生活を参照しながら憶測を立てることもある。
このように、その人らしさを重視する「新しい認知症ケア」において、患者のそれまでの人生(ライフヒストリー)を詳細に知っておく必要がある。そして、患者のそれまでの人生を知っている人とはすなわち、多くの場合は「家族」なのである。その意味で、家族とは必ずしも血縁や戸籍によるものではないことは、認知症介護においてもいえるだろう。
新しい認知症ケア時代における“良い介護家族”は、患者へのはたらきかけを常にやめない。「患者たちが、未だに心の奥では何かを感じていて、何かを意識しているのだと考え続けることは、馬鹿らしいしよくわかっていないだけ」などとは思わない。
大根を育てていた患者の食事に大根の味噌汁が出れば、大根の話を懸命にしてその人らしさを引き出そうとし、みかんを食べなければ「どうしたら食べられるようになるのか」「どうして食べないのか」など、その人が求めるものは何なのか、人生を遡及的に構築しながら考える。
こうした関わりの中で“良い介護家族”は「これが最善の関わりか」「思い込みはないか」などを常に参照し、ときに自分を責めることがある。たとえば、認知症の発見に気づくのが遅れたとき。たとえば、自分がその人の人生を基に立てた推測が間違っていたとき。
自分はその人のことをよく知らなかったのではないだろうか。
自分はその人にとって大した存在ではなかったのではないだろうか。
こうした「後悔」について、著者は「暮らしぶりや考え方をすべて共有するのが『普通』の家族ではないから早くに気づけなくても当然ですよ」とやさしく寄り添ってくれる。また、介護家族が集まる「家族会」では、「すべてを過去に紐づけるのではなく、現在の患者に対するコミュニケーション(対応)の問題に目を向けてみよう」とアドバイスされることも多いという。
しかし、こうした「後悔」や葛藤を抱いた“良い介護家族”であればあるほど、その人らしさに重点を置いた介護に関わることになるだろう。したがって、新しい認知症ケア時代において、家族の「ケア責任」が増大するのは、いわば当然の帰結なのだ。
*
ある意味で理想が高くなった現代の介護における介護家族に対して、著者は「多少失敗したとしてもあなたのせいではない。あなた個人や他の誰もがなんともできない問題だ」として徹底的に寄り添う。この本を読んで、どれだけ救われる人がいるだろうと私は思った。
その人らしさを重視する介護が、身体拘束などの処置と比較して「コスト」だと思わない。ただし、国による公助も若者の数も減っていく中で、物理的にも、「その人らしさ」を知っている点においても、家族のケアが増大していくことについてはどう受け止めていいのかわからない。その人らしさを大事にしたオルタナティブな介護の方法はないのだろうかと考えてしまう。「家族による介護が最善であり愛だ」という説に基づかず、介護家族が主体的に行っているとしても、である。
そう考えてしまう私は、やはり怖いのかもしれない。
父が祖母にしたことと同じことを自分ができるかどうかわからないことが。
自分の薄情さを突き付けられることが。
自分と親との関係は想像以上に希薄だったのではないかと思うことが。
もっと真剣に関わっておけばよかったと後悔することが。
私はまだ何もかもわからない。わからないから怖い。
介護のことも、祖母や父の気持ちも、これからのことも。
だからこそ、過去の後悔を埋めるように、将来の後悔を前借するように、今を煮詰めて向き合っていきたいのだ。
文=佐々木ののか
バナー写真=Atsutomo Hino
【筆者プロフィール】
ささき・ののか
文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。6/25に初の著書『愛と家族を探して』(亜紀書房)を上梓した。
Twitter:@sasakinonoka







