完全に封鎖された街。終わりが見えない中、人々はその日その日を生きることを受け入れていく/60分でわかる カミュの「ペスト」⑤
公開日:2020/9/5
超難解なカミュ『ペスト』のポイントを、マンガとあらすじで理解できる1冊。感染症の恐怖にさらされたとき、人間は何を考え、どう行動するべきか。解決策が見つからない中、立ち上がった人々の物語をご紹介します。
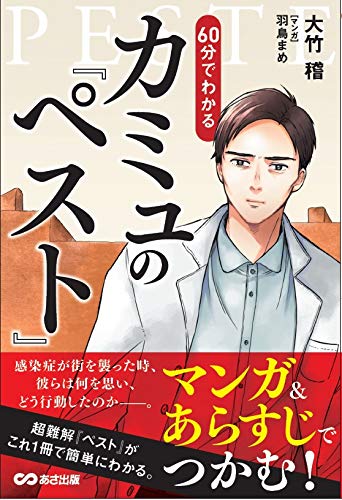
閉門
とうとうオラン市の門が閉じられた。「この瞬間から、ペストは街にいる我々全員に関わるものになった」。
封鎖された街、それも完全に! 何人たりとも、ネズミ一匹も、街から出ることを禁じられた。
さて、『ペスト』の世界観を創出するために必須の、この「封鎖」。
市民のみなさんの善意に期待し、みなさんそれぞれが空気を読んで、お互いに圧力をかけながら、恥ずべきことをしないようにお互いをけん制してくださいね、という、甘いものではない。
あるのはただ、暴力にも等しい圧力だ。
市民の善意への期待など、みじんもない。
門には衛兵たちがいて、警官が街をパトロールしている。市民の安全を守るため? 否、こんな危険な街に、安全もなにもないだろう。不心得者を引っ捕らえるために、彼らはいるのだ。
違反者には発砲が許される。さすがに、射殺ということはなかっただろうが、捕まれば即、牢獄行き。
そして、「何人たりとも……」。この御触れによって、恋人たちがバラバラになった。夫婦も、親子も、突如としてバラバラにされてしまった。街に残された側は、いつ感染し死んでしまうか、わからないのだ。
告示があって数日間は、県庁は陳情の群衆によって攻め立てられた。しかし、当然のことだが、どのような事情であれ、特例など認められるはずはなかった。外から戻ってくる選択肢だけは残されたが、むろん、一度戻ってきてしまったら、封鎖中は二度と外に出られない。
それは、死ぬことを覚悟するに等しい選択だった。
「ペストがオランの市民にもたらした最初のものは、追放状態だった」。これまで、普通に、当たり前のように過ごすことができていた日常から、オラン市民は締め出されてしまったのだ。菌を媒介しうる手紙は禁じられた。回線がパンクするため、「不要不急」の電話も禁じられた。電報だけは許されたが、使用しうる文句には限りがある。だれもが、定型句の「コチラブジ、ゲンキデイテ、アイシテイル」を定期的に送るしか術はなかった。
ただ、一件だけ、死に対する恐怖に人間的な感情が勝ったケースがあった。カステル老医とその夫人だった。カステル夫人が、封鎖の数日前に別の町に出かけていたのだ。しかし、この二人にとって、別離に比べればペストによる死の恐怖など取るに足りないことだったのだ。
カステル夫妻のようなまれなケースを除き、オランの市民は、過去を恨み、薬にもならない思い出にすがり、死とすれすれの現在に押しつぶされそうになっていた。いつ街が解放されるかわからない。だれも期限を教えてくれない。「半年で終わる?」。だが、そんな確証はだれにもない。「ひょっとしたら一年か、それ以上かもしれない……」。不安はどのようにしても解消されない。オランの市民にとって「現在はイライラさせるものになり、過去は敵となり、未来は奪われてしまった」。オランは牢獄になってしまったのだ。
オランの市民が共有している「追放感」。空間的な刑罰だけをイメージしてしまいそうだが、もう一つ、より残酷でより厳しい牢獄がある。時間的な牢獄だ。
「ペストがオランの市民にもたらした最初のものは、追放状態だった。(中略)実際、まさにこの追放感こそ、オランの日常にうがたれた虚ろであった。オランの市民が共有するはっきりとした感情だった。時間を巻き戻したいとか、時間の速度を速めたいとか、そんな理屈にもならない願いであった」
街が封鎖されてしまったのと同様に、時間も閉ざされてしまっていたのだ。今という時間の中に、希望などまったくない。もちろん、時間は意のままにならない。その点では、実際の囚人のほうがまだマシだろう。なぜなら、いつか終わりがあることを知らされているからだ。
しかし、こちらの終わりはまったく見えない。気が狂わんばかりの一分一秒と、「忍」の一字でただ付き合っていくしかないのだ。
「追放」は、フランス語の原文では「exil」である。
この「exil」は、「追放」だけでなく、親しい人や、親しんだ土地から離れてしまうことを意味する。
本来、「外へ飛ばされる」ことを意味するexil だが、人々はオランの外へ追放されたのではなく、当たり前にできていた日常から追放されてしまったのだ。「パパがもうすぐ帰ってくるよ」とか、「予定より早く恋人に会えそうだ」とか、「これからおいしい料理が待っている」などという、「楽しみ」という気持ちを封印しなければならなかった。
オランの市民は、「頼りにしようとするものが、いっそう心の痛みになることがわかってしまい、そんな頼りを可及的速やかにあきらめてしまうのであった」。
決してはい上がれない穴の底に叩き落とされたようだった。
人間が持ちうる意志や勇気など、もはや問題にすらならないほどだった。
追放された街の中で、人々はさまよう亡霊になってしまっていた。
しかし、このような追放状態は、「長い目で見れば、人々の精神をきたえるものになった」。なぜか?
追放状態の初期から、市民には二重の苦しみがあった。
まず、自分自身の苦しみが一つ。
もう一つが、子どもたちや、伴侶、恋人など、自分を待っている者たちの苦しみ。そして、幸いなるかな、ペストがもたらす不幸とは、自分が死ぬことではなく、自分を待っている者たちとの永遠の別離が来てしまうかもしれないという不幸だった。というのも、「自分が、ペストの病魔に倒れるようなことがあったとしても、それはもう、ペストは警戒できる限界を超えてくる」からだ。
有り体に言えば、どれだけ気を配っていても、感染する人は感染してしまう。
なにせ、どれほど目を皿のようにしても、ペスト菌は見えないのだ。
感染したら、ペストはあっという間に自分をこの世から連れ去ってくれるだろう。自分の苦しみは一瞬だ。
だが、その後の自分を待っている人たちの苦しみは……?
この苦しみは、「嘆き悲しみ、憤ることしかできないほどの、まったく不当な苦しみばかり」ではなかった。
「相手から好かれることはあっても、自分から好きになることはない」。異性にそのようなセリフを吐く男女が、じつは自分がとても誠実であることを知った。
「パートナーを信頼している」と公言していた者たちが、自分にも嫉妬の感情があることを知った。
親を疎ましく思い、ろくに顔を見ようともしなかった子どもたちが、親の顔のしわ一本一本に刻まれた人生に、愛おしさを感じるようになった。
こうしてペストは、「人々を苦しませることによって、人々が自ら苦しみを受け入れさせるようにした」。そして、「人々は、その日その日を生きることを受け入れていった」のだった。





