第172回芥川賞候補作『二十四五』。ロングセラー『旅する練習』の著者・乗代雄介が圧倒的な筆致で描き出す、喪失と祈りの物語【書評】
PR 更新日:2025/1/17
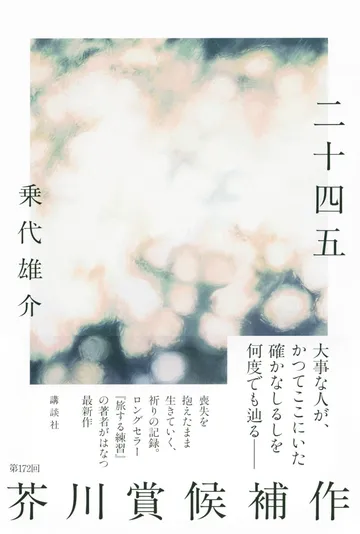
大切な人を亡くした人は、その存在を心の中で探し続けてしまう。私にもそういう人がいて、それは祖母に当たる。難しい人ではあったが、両親との関係が良好ではなかったぶん、私にとって祖母の存在は救いであった。もし祖母が生きていたら、こう言ってくれただろう。この場面では笑い、この場面では怒っただろう。そんなふうに想像しては、「もう祖母がいない」ことに打ちのめされる。それが私の日常であるからして、喪失を抱えた主人公の心情を緻密に描いた小説『二十四五』(乗代雄介/講談社)を読んだ折、私の心は静かに共鳴した。
主人公の景子は、弟の結婚式のために仙台を訪れる道中、平原夏葵と名乗る女性と出会う。景子が手にしていた漫画『違国日記』をきっかけに会話を交わす中で、景子は5年前に亡くなった叔母・ゆき江の存在を思い出していた。『違国日記』は、ゆき江が景子に貸した最後の漫画だった。よって、景子にとってそれは、「なんとなく読みづらくなったのを放り出すわけにもいかずに続きを読んで、やっと終わって正直せいせいしたところ」という代物であった。一方、夏葵はその漫画を買い損ねて落ち込んでいたため、景子は夏葵に自分の本を差し出す。夏葵とのやり取りはここで一度途切れ、弟の結婚式の場面へと物語が進む。
景子は家族との確執があり、両親や弟と顔を合わせるのは実に2年ぶり、弟の結婚相手である弥子の家族に会うのは今回がはじめてだった。飄々とした態度を貫く景子は、その裏側でさまざまな思いを巡らせる。弥子は弟の幼馴染で、昔から知っているため、弥子と話す時は気安い。だが、結婚式前夜に行われた弥子の両親を交えた食事会において、景子はたびたび喉がつかえるような感覚を味わう。それは食事会の場で、景子の職業の話になったことに端を発する。景子は、作家である。デビュー作で二つの賞を受賞し、選評でも高い評価を得た実績を持つ。弥子の両親は、身内に作家ができることを素直に喜んでおり、景子に称賛の眼差しを向ける。だが、景子はそんな空気に冷や水をかけるように、次の言葉を口にする。
“「読んでほしくなんかないんです、誰にも」”
作家として物を書くにあたり、「読まれてほしい」「売れてほしい」と願う人が大半であろう。だが、景子は「読んでほしくない」と言う。その複雑な心理の裏には、ゆき江の存在があった。
“叔母を失って以来、おびただしい数の瞼の裏に聖なる感情をしまいこみ、別なる心情として書き並べてきた。読んだところで誰一人、瞼の裏を覗けはしない。”
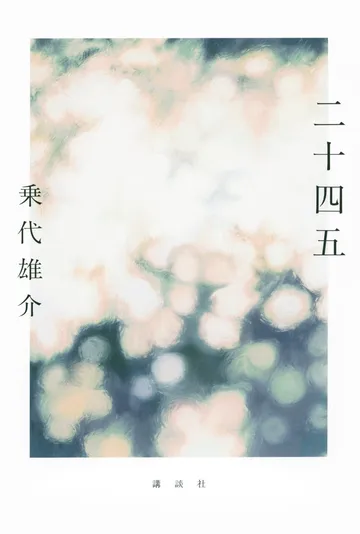
物書きとして生きる景子の心理描写は、微に入り細を穿つ表現で、読む者の心を静かに震わせる。叔母を思い、泣くのをこらえる景子の様子を綴った箇所では、知らずと喉元が痙攣した。流れ落ちることのない涙は、やがて言葉となる。物書きならば、そのような経験をした者は存外多かろう。
24〜25歳の景子が、喪失を抱えて生きる祈りの物語は、ゆき江の痕跡を求めて旅をする中で出会った夏葵との再会で幕を閉じる。
“これは、叔母がどんなに私を思ってくれていたかということを、その死後も巧妙なやり方で繰り返しほのめかされ時には泣かされたところでぴんぴんしている、根深い恨みである。”
この一節からわかる通り、景子にとってゆき江は、単純な「情愛」で説明しきれるような間柄ではなかった。それでも、生前のゆき江と計画した旅行の行き先である仙台に縁を得て、叔母と回るはずだった土地を一つずつ踏みしめる景子の足取りは、悼みと共に生きることを決意した人のそれであった。住まいのある東京と仙台を往復する時間の中で、景子が目にしたもの、出会った人、胸に幾度となく蘇った叔母の残像。そのすべてが、喪失を経験した人の心にそっと寄り添う。読みながら、自身の祖母のことを思い出しては目を閉じた。景子と同じく、涙がこぼれないように。飲み込んだそれが、いつしか言葉になるようにと、深く祈りながら。
文=碧月はる




