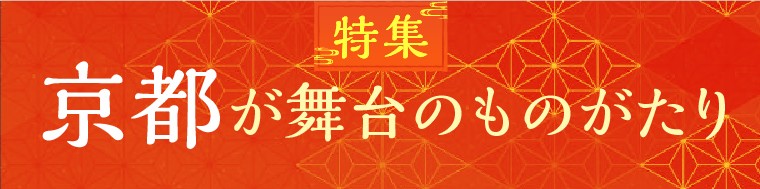直木賞作家・万城目学のデビュー作。謎の競技「ホルモー」にかける青春が尊い!? 実写映画化もされた『鴨川ホルモー』 #京都が舞台の物語【書評】
公開日:2025/1/19
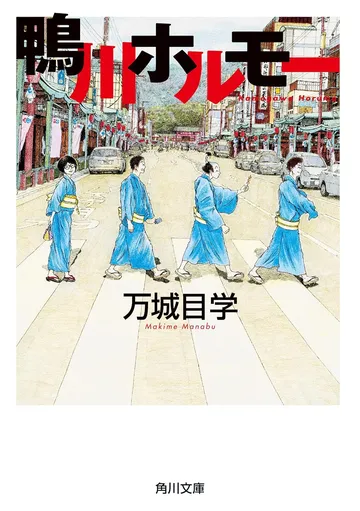
京都の大学に通っていたとき、とても変な映画を観た。直木賞受賞作家・万城目学氏のデビュー作『鴨川ホルモー』(万城目学/KADOKAWA)を実写映画化した作品だ。現代の京都を舞台に、学生たちが鬼や式神を使って戦うという不思議なお話。当時は「妖怪モノのおもしろい作品」という印象だったが、大人になった今、原作小説を読んで気付かされたことがある。これは、京都で学生生活を送った人すべてにおくる、青春部活モノなのだと。
二浪の末、ようやく京都大学に合格した主人公の安倍は、葵祭のエキストラのバイト帰りに「京大青竜会」という怪しげなサークルの新歓を受ける。タダ飯目当てで新歓コンパに参加した安倍だったが、そこで出会った早良京子に一目惚れ。彼女に近づきたい一心でサークルに入会してしまう。大文字山に登ったり、琵琶湖にキャンプに行ったりと、何の変哲もないレクリエーションサークルと思われた「京大青竜会」。しかしその実態は、謎の競技「ホルモー」を行う団体だった……!
ホルモーとは、小さな「オニ」を操って戦うチーム対抗の競技。京都の東西南北に位置する4つの大学のサークル同士で争い、相手のオニを全滅させるか、降参させれば勝ちとなる。京大青竜会と競い合うのは、京都産業大学玄武組、立命館大学白虎隊、龍谷大学フェニックスだ。
設定を見るとファンタジー小説に思えるが、物語の中心となるのはサークル活動を通じた友情や恋愛、葛藤だ。活動について他人とぶつかったり、サークル内の恋愛でいざこざが起きたり、自信を失くしたり。何かの部活動やサークル活動をしたことのある人間なら、本作の至る部分で「こういうことあったな~!」と共感できるはず。
作中では、京都大学とその周辺の百万遍を中心に、京都のさまざまな場所が登場する。ただ地名やスポットを出すだけでなく、住んでいる人にとってどんな場所なのかが伝わる自然な描写が多いのが魅力だ。たとえば、こんな一文がある。
「北野天満宮の鳥居前を過ぎたあたりから、俺は徐々に重い緊張に囚われ、ペダルを漕ぐ脚も重く感じられ始めた。もっともそれは、北野白梅町の交差点から入った、西大路通の緩やかな上り坂のせいだったのかもしれないが」
京都は南北に高低差があり、北に向かうほど少しずつ傾斜が高くなっていく。あの道を自転車で走っていて、何度泣かされたか分からない。地元民の多くが経験するだろう土地の難所と、主人公の心情を見事に絡めた文章だ。作中に登場する大学の出身者であれば、土地の描写も相まって、主人公たちの学生生活をよりリアルに感じられるはず。京都で過ごした日々を思い出して懐かしくなるだろうし、各大学特有のネタでふふっと笑えるだろう。私自身も龍谷大学出身だが、大学ゆかりの小ネタが登場したときはニヤリとしてしまった。
ホルモーでは1人につき100匹、チームで計1000匹のオニを使役して戦う。人間同士の接触は厳禁。オニ語を使ってオニたちに指示を出し、相手チームを叩きのめしていく。陰陽師や式神といったモチーフが好きな人なら、戦国絵巻のようなホルモーの合戦にワクワクするだろう。もしかしたら、こんなサークルが本当にあるかも……? と思わせてくるのも、京都という街が持つ神秘的な魅力かもしれない。
読み終わった頃には、映画版を観たくなったり、実際に京都旅行をしたくなったりすること間違いなし。続編の短編集『ホルモー六景』とあわせて、今年の読書ラインナップにいれてみては。
文=倉本菜生