「大人ってやっぱり全くどうかしてるな」。クリスマスのための子ども向けの小説なのに名言が多すぎる一冊/斉藤紳士のガチ文学レビュー㉖
公開日:2025/3/10
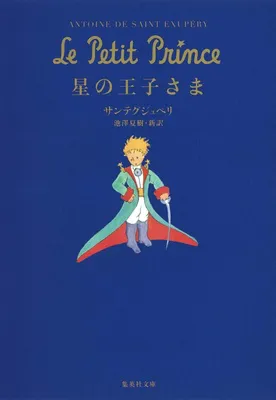
世界中の読書家が「後世に残したい小説」として挙げることが多いのが今日紹介するサン=テグジュペリの『星の王子さま』ではないだろうか。
『人間の土地』のアメリカ版『風と砂と星』がベストセラーとなり、出版社から「クリスマスのための子どもに向けた話」を書いてほしい、と依頼されたのが1942年の夏のことだった。
結局、その年のクリスマスには間に合わなかったが、翌年の春に『星の王子さま』は出版され、世界中で愛される作品となった。
子ども向けの小説なので、文章もわかりやすく設定もシンプルなのだが、いたるところにアフォリズムがあり、侮れない作品になっている。
「生きるとは?」「死ぬとは?」「人を愛するとは?」といった深いテーマについて、時に鋭く、時にユーモラスにそのヒントを与えてくれる人生の指南書のような小説でもあり、また、そういった道しるべを提示してくれる先達をヘビやキツネが担っている点も実に面白い。
作風はライトだが書かれている内容はかなり哲学的なので「笑い」の要素は少ない、と思われるかもしれないが、そんなことはない。というより、むしろこの小説の大きなテーマのひとつが「笑い」であると断言できる。なぜそう言えるのか、まずはあらすじを紹介しよう。
サハラ砂漠に不時着したパイロットの「ぼく」は、とある星から来た王子さまと出会う。王子さまは大切に世話をしていた一輪のバラと喧嘩をしたことをきっかけに他の星の世界を見るために旅に出る。六つの星を経由して地球にたどり着いた王子さまはヘビやキツネと会い、生きるために大切なことを教わる。
そして地球にやってきてからちょうど一年後、星の配置が一年前と同じ夜に王子さまはヘビに咬まれ、身体を置いて自分の星へと帰っていく。
なんとも不思議なお話だが、そこには大切な言葉がいくつも登場する。
「さようなら」王子さまは言った……
「さようなら」キツネが言った。「じゃあ秘密を教えるよ。とてもかんたんなことだ。ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。いちばんたいせつなことは、目に見えない」
「いちばんたいせつなことは、目に見えない」忘れないでいるために、王子さまは繰り返した。
この小説の大きな出来事のひとつに「王子さま」の星々への旅がある。間違いなくこの小説のハイライトであり、そのエピソードのひとつひとつが人間社会への痛烈な風刺となっていて、小話のように面白いのである。
小話とは、落語のマクラやサゲなどにも用いられる粋で洒落の効いた短いお話である。
日本では、江戸時代初期に発売された笑い話集「醒睡笑(せいすいしょう)」から広まり、江戸庶民の間で人気となったとされているが、小話の類は世界中にある。
有名なものだと、この作品でも近いエピソードが出てくるが、バーの小話などがある。
とあるバーで男が一人、淋しそうに酒を飲んでいる。
「どうしてそんなに酒を飲むんだ?」
「忘れたいことがあるのさ」
「何を忘れたいの?」
「忘れたさ」
『星の王子さま』で描かれる星々でのエピソードは一見、風変わりな人物を登場させているだけのように思えるが、距離をとって俯瞰で見てみると、実に風刺が効いていて、人間の愚かさをうまく描写していることがわかる。まさにここに「笑い」が存在しているのである。
生きるうえでの心の置き方、人との関わり方の大切さを笑いを交えて紹介しているのである。
王子さまが最初に着いた星には王様がいた。王様がいた、というより王様しかおらず、王子さまが現れると「民が来た!」と喜ぶ。人間の虚栄心や選民意識を上手に茶化している。
二番目の星にいる大物気取りも似たような人物で、とにかく「褒めろ」と迫ってくる。
三番目の星には先述した小話に出てくるような酒浸りの男がいる。次の星には実業家がずっと計算をしていて、さらに次の星にはガス灯に火を灯しては消している点灯人がいた。六番目の星には研究室から一歩も動かない地理学者がいて、この辺りは仕事に追われて生きる意味を見失いかけている人間が描かれている。王子さまは訪れた星を離れるたびに「大人ってやっぱり全くどうかしてるな」と思うのであった。
哲学的なテーマを扱うのに、時に深刻に、時にユーモラスに描き、そして何より世界中の子どもたちにも愛される名作として上梓した『星の王子さま』。大人も子どもも楽しめる珠玉の一作を是非お読みください。





