若い女性書店員を狙った卑劣なクレーム事例に驚愕! 苦情対応のプロが公開する「カスハラの正体」とは?【書評】
公開日:2025/4/17
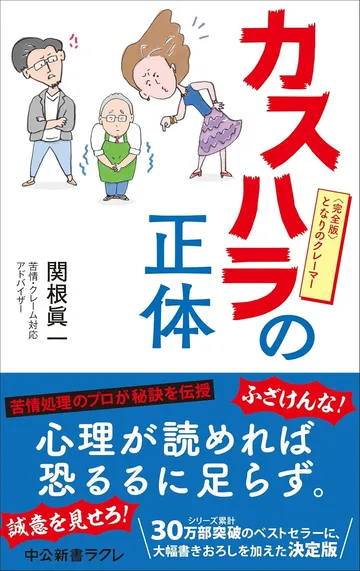
客が理不尽な要求や暴言を行うカスハラは近年、深刻な社会問題となっており、企業だけでなく行政も防止策を打ち出している。東京都、北海道、群馬県は、全国初となる「カスハラ防止条例」を2025年4月1日から施行。悪質なクレーマーをやり過ごす時代は終わりつつあるのだ。
『カスハラの正体-完全版 となりのクレーマー』(関根眞一/中央公論新社)はそんな今だからこそ、備えておきたい1冊である。本書は、シリーズ累計30万部を突破したベストセラー『となりのクレーマー』に大幅な書きおろしを加えた決定版だ。
著者の関根眞一さんは34年間、百貨店に在職し、お客様相談室で1300件以上のクレームを聞いてきた苦情処理のプロ。百貨店を退職した後は、苦情・クレーム対応アドバイザーとして活動している。本書では、関根さんが実際に遭遇した事例や令和ならではのカスハラをストーリー形式で紹介し、対処法を伝授。このたび施行された「カスハラ条例」の知識も得られる。
著者が対応してきたクレーム内容や相手は、多種多様。本書には、想像のななめ上を行く“困ったお客様たち”ばかりが登場する。
関根さんが駆け出しだった頃には、無料で眼鏡が洗浄できる超音波器具でダイヤがついたネックチェーンを洗浄し、「壊れてしまった」と言いがかりをつけるヤクザのクレームを処理。百貨店を退職する直前には、「あんたは、必ず俺の前でボロを出すよ」と話すクレーマーの“ある事情”に胸を痛め、エールを送ったこともあった。
そんなパンチの強いクレーム事例の中でも特に度肝を抜かれたのが、書店員を狙った卑劣なカスハラだ。著者が「カスハラの王様」と表現するEさん(30代前半)は書籍売り場で若い女性店員を見つけると、2冊しか在庫がない書籍に目をつけ、1冊を他の棚に移動して様子見。
その後、もう1冊を見つけにくい場所に隠し、何食わぬ顔で書店員にその書籍を探してほしいと告げるのだ。
書店員は在庫数を把握しているので書籍を探すが、Eさんの嫌がらせによって本は見つからない。こうなれば、Eさんの思うツボ。「待たされて仕事に損害が出た」と、人目のある中で書店員をつるし上げるのだ。
そんなEさんに関根さんは嫌がらせの証拠をつきつけ、丁寧かつ厳しい口調で書店への出禁を言い渡した。相手が誰であっても、クレーマーの心理状態を慎重に読みながら毅然と対応する著者の態度には多くの学びがある。
悪質なクレーマーは「家に謝罪に来い」と要求することも多いが、そうした時でも関根さんは臆さない。話す時には、「静行話法」と名づけた話し方を意識し、ひたすら丁寧なお詫びを続ける。すると、クレーマーは、ぬかに釘の状態に。どこで突っ込んでいいのか戸惑い、怒りを出すことが難しくなるのだという。
なお、話し合いの際には同行者に話の内容をメモしてもらうなど、自社や自身を守る対策も忘れない。乱暴な言葉や恐喝があった場合は、時間と言葉を繰り返して言い、同行者が正確に書き記せるようにしていたという。
絶妙な攻めと守りが入り混じる著者のクレーム対応は、まさに目からウロコ。ちなみに、金銭での解決は、その場しのぎで早く終わらせたいという弱い姿勢から出るものであると考えているため、できる限り応じないようにしてきたそうだ。
本書では一筋縄ではいかないクレーマーと直接対決する時に役立つ戦略や、実践しやすい基本的対応も詳しく紹介されているので、心身を守るお守りとして頭に入れておきたい。
ただ、クレーム対処をする中では、まともな苦情とカスハラをしっかり見分けることも大切だと関根さんは語る。まともな苦情はサービスの向上につながる貴重な意見にもなるからこそ、すべての苦情を安易にカスハラ扱いせず、相手が怒っている原因の追求を怠らないでほしい、とも著者は言う。苦情の対応後、クレーマーと挨拶を交わしたり、情報交換をしたりする間柄になることも多い著者だからこそできるこのアドバイスは、接客業に従事している人の心に深く刺さることだろう。
完璧ではないからこそ人間はミスをし、それが苦情に繋がることもある。そんな時、自分はどう顧客と向き合うか。そして、自身が顧客側の場合には相手の失敗をどう受け入れるか…。本書を手に取ると、そんな問いも浮かび、人との向き合い方を考え直したくもなる。
文=古川諭香





