「子どもの偏食」「栄養足りてる?」子どもの食事の悩みが解決! 忙しくても“できる”レシピのアイデアも【書評】
公開日:2025/7/23
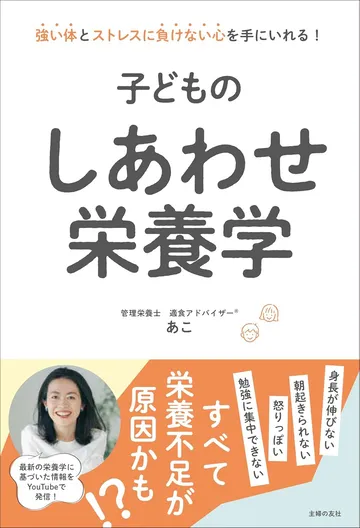
子育てをしていると、避けて通れないのが「子どもの食事」の悩み。「好き嫌いが多くて食べさせるのが大変」「身長をもっと伸ばしてやりたい」「これで栄養バランス取れてるの?」……と、親の誰もが悩みっぱなしなのではないでしょうか。私も子どもを育てる親として、日々の食事には迷いや不安が尽きない日々を送っています。そんなときに出会ったのが、管理栄養士でYouTuberとしても人気のあこさんによる『子どものしあわせ栄養学』(主婦の友社)。子どもの栄養に関する不安や疑問に対して、栄養学の知見を基礎から非常にわかりやすく教えてくれる1冊です。
栄養についての「思い込み」をほぐし、正しい順番で栄養について学べる

印象的だったのは、「まず三大栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物)を押さえることが最優先」という一貫したスタンス。子どもの身体の成長の材料になり、毎日の生活や運動のエネルギーになる、超キホン中のキホンの栄養素の話を冒頭に置き、そこからしっかり解説している点に好感を持ちました。
SNSの育児アカなどでは「無添加」「無農薬」などのキーワードが先行したり、「背を伸ばすにはカルシウム、つまり牛乳」といった単純な情報が流れたりすることもあります。しかし著者は、そうした“ありがちな思い込み”をやさしくほぐしながら、本当に大切な土台を教えてくれます。
たとえば、「野菜をたくさん食べさせる=栄養満点」というイメージに対しては、「野菜のビタミンやミネラルをしっかり働かせるには、まず三大栄養素を満たしておくことが必要」と解説してくれて深く納得。また、背を伸ばすためにはカルシウムを摂ることばかりに注目しがちですが、その前提として“体をつくる材料”であるタンパク質が欠かせない……という話も、非常に勉強になりました。
そして、ダイエット情報に日常的にさらされている大人だからこそ持ちがちな「炭水化物=悪」「脂質=悪」といった思い込みにも、本書は丁寧に向き合います。
たとえば12〜14歳の男の子が1食にご飯を220〜260g食べるのが適量という話は、体重管理に慣れた大人にとっては驚きかもしれません。しかし、それほどの栄養が日々の生活や成長には必要なのだ……と考えると、子ども用の食事の設計がまるで違って見えてくるはずです。

さらに、運動をしている中高生なら1日3000キロカロリーが必要なケースもあり、それを満たすには脂質を活用することも不可欠。むやみに控えるのではなく、「必要な量をきちんと摂る」ことが大切だという視点に、深くうなずかされました。
忙しい親でも“できる”工夫が満載
料理が得意でない人や忙しい人におすすめな、加工食品を使った簡単なレシピが紹介されているのも本書の魅力。たとえばタンパク質については、温泉卵、ちくわ、はんぺん、ツナ缶、冷凍焼き魚などを朝食に出すことも推奨されていたり、「ほうれんそうのじゃこあえ」という簡単レシピが紹介されていたりと、「これならできる!」と思えるアイデアが満載です。

また、「ごはんの量はどれくらい?」といった素朴な疑問にも、年齢別の食事例を写真付きで答えてくれており、視覚的に理解しやすい構成なのも嬉しいところ。具体的で実践的、なのに押しつけがましくない。このバランス感覚が、本書の大きな魅力のひとつです。
極端な主張に走ることなく、エビデンスに基づいた情報を提供する本書は、安心して手に取れる“栄養の教科書”のような存在。著者のあこさんは、管理栄養士として病院で勤務した経験も持つ実力派で、参考文献にも英語の論文が豊富に引用されていており、情報の裏付けもしっかりしていると感じました。
主な想定読者は3歳以上くらいの子どもを持つ親だと感じましたが、2歳児を育てる私にとってもすぐに役立つ情報ばかりでした。料理を日常的にする人にも、そうでない人にも。子どもが健やかに育つための“食”を考えるすべての親に読んでほしい、まさに「育児の迷いが晴れる1冊」です。
文=古澤誠一郎




