吉沢亮・横浜流星が共演、話題の映画『国宝』の原作小説が売り切れ続出!映画版の違いとは?見どころを紹介【書評】
公開日:2025/7/26
※本記事には若干のネタバレを含みます。映画未視聴の方は、ご了承の上お読みください。
吉沢亮・横浜流星が共演した映画『国宝』の勢いが止まらない。「伝統芸能の歌舞伎が題材」「上映時間が約3時間」といったハードルをはねのけ、6月6日に劇場公開されると大ヒット。7月21日時点で、観客動員数486万人、興行収入68.5億円を突破し、2025年公開の邦画実写No.1(興行通信社調べ)に躍り出た。
本作は『悪人』『怒り』に続く原作者・吉田修一×監督・李相日監督のタッグ作。極道一家に生まれた喜久雄、上方歌舞伎の御曹司・俊介が切磋琢磨し、芸の道を突き進んでいく姿を数十年にわたって追う壮大な一代記だ。映画のヒットに連動して、原作小説上下巻も売り切れが続出。7月18日時点で書籍・電子版合わせて累計120万部を突破するベストセラーとなっている。
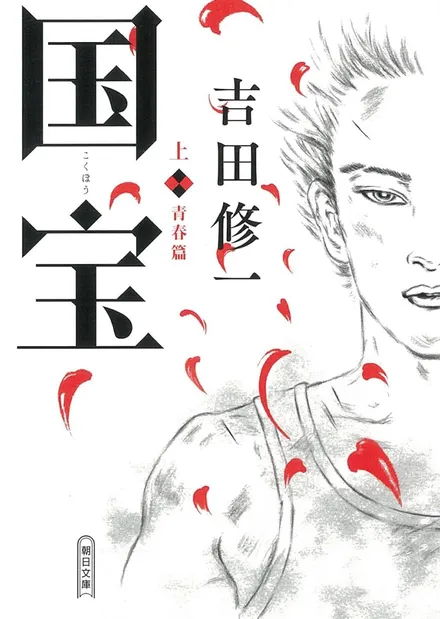
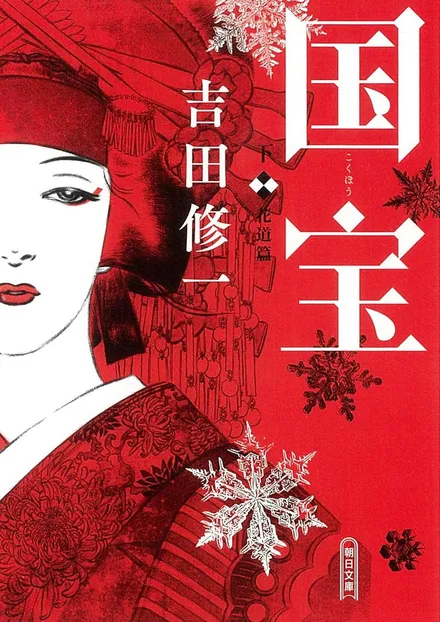
小説『国宝』は2017年から18年にかけて朝日新聞で連載され、芸術選奨文部科学大臣賞と中央公論文芸賞を受賞した一作。吉田氏がなんと3年もの間、歌舞伎の黒衣をまとって取材した経験をもとに書き上げたという。
『パレード』や『横道世之介』『湖の女たち』ほか、様々なテイストの小説を発表してきた吉田氏だが、本作の大きな特徴は従来の作風とは一線を画す文体。三人称視点なだけでなく、全編が「ございます」「まいります」に代表される「ですます調」の語り口となっており、読者というよりは観客に話しかける体で進んでいく。まさに客席で歌舞伎の演目を観ているような感覚にさせられるのだ。
映画は、どちらかといえば喜久雄や俊介の主観にきわめて近い距離感で物語が進行する“接写”のような作品だ。観客も彼らとともに舞台に立ち、波瀾万丈の生涯を追体験するような没入感とエモーションがある。一方で小説は、語り部が喜久雄や俊介、そして彼らを取り巻く人物たちを紹介していく“遠写”の構図で描かれている。芸に身も心も捧げ、修羅となってゆく人々を、第四の壁越しにただ見守るしかないという断絶感と切なさが漂っている。物語の大筋は小説・映画共にほぼ同じだが、この距離感の違いが各々の形態で魅力を醸し出しているように感じられる。
例えば(以下、ネタバレとなるため注意)、映画版では喜久雄が「悪魔に魂を売ることで覚醒する」分水嶺として歌舞伎役者の娘・彰子(森七菜)とのベッドシーンが登場するが(吉沢亮の虚ろだが狂気を感じさせる芝居が強烈だ)、小説ではそこに至るまでに相当な葛藤があり、出世のために利用したことを詫びるシーンも早めに登場する。
対して映画版では喜久雄が屋上で泣き笑いながら舞うシーンが挿入され、芸に取りつかれた役者の狂気性に注力。京都の芸者・藤駒(見上愛)との間に生まれた娘・綾乃の関係も異なっており、喜久雄の業を感じさせるラストシーンも映画オリジナルだ(その代わりに小説では、喜久雄が高みを目指した結果静かに狂っていく)。映画版では喜久雄が唯一、本音をさらけ出せる相手として俊介を置いており、「2人の物語」としての側面が強い。
その俊介の内面描写もまた、小説と映画では少々異なる。映画では父・半二郎(渡辺謙)の代役として圧倒的な才能を見せつけた喜久雄の芝居を観る→涙が止まらなくなって「本物の役者になりたい」と決意し、春江(高畑充希)を伴い失踪→甘えを捨てて地力を磨き、復活という流れだが、小説ではここに至るまでに紆余曲折ある。ボンボンとしての性根がなかなか抜けず、一時はヒモ生活になり、古書店で働くようになって歌舞伎の世界の奥深さに触れるというエピソードや、第一子を病気で失ってどん底にまで落ちそこから這い上がる壮絶な出来事、復活時の覚醒ぶりを喜久雄が目の当たりにしてのめり込むように観劇してしまう描写も登場する。
本稿で挙げた相違点はほんの一例で、小説では半二郎をはじめとする周囲の人間のエピソードや、映画版には登場しない主要キャラクターも存在する。かといって映画がダイジェスト的かと言えばそんなことは全くなく、先述した距離感の違いを含めて映画と小説というメディアに即した強みがいかんなく発揮されている。観てから読むか、読んでから観るか——。どちらも悩ましいほどに輝きを放つ2つの『国宝』、ぜひ末永く楽しんでいただきたい。
文=SYO






