人間の数が減り、絶滅の危機に…芥川賞作家の描く“人間の行く末”が絶望的でも愛おしい【書評】
公開日:2025/7/27
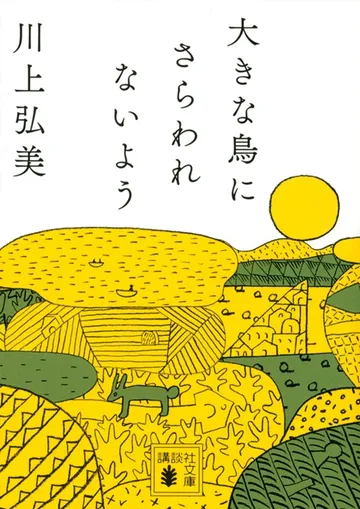
どんな生き物も、いつかは滅びる。それは人類だって同じはずだ。いつの日か人類の数が劇的に減少し、人類が万物の霊長たる地位を失った時、私たちは絶滅の危機にどう抗おうとするのだろうか。人工知能やクローンの技術を借りて生き延びようとする人間たちの姿を描き出したのが『大きな鳥にさらわれないよう』(川上弘美/講談社文庫)。2025年、世界的に権威のある英国の文学賞の翻訳部門「国際ブッカー賞」の最終候補作に選ばれた注目の作品だ。
今日は湯浴みにゆきましょう、と行子さんが言ったので、みんなでしたくをした。
そんな一文から始まるこの本は、そのすべてがまるで神話だ。おそらくページをめくり始めた時、あなたは困惑するだろう。ここはどこなのだろう。まだ世界を何も知らない、何も見えない、ただ感じることしかできない赤ん坊にでもなったような気分で、ぼんやりと薄明るい世界を眺める。どこかほのぼのとした空気に浸っていると、やがて、驚くべき事実に行き当たる。ここで描かれているのは未来の日本。子どもたちはみんな、牛やウサギ、ネズミ、イルカなど、さまざまな生き物の細胞から作られたクローンで、男たちが工場で作った子どもたちを、女たちが何十人と育てている。
やがて章が変わると、今度は別の集落の、別の物語が紡がれる。そこにいるのはクローンである3人の「私」と、人間ではない「母」たち。——そう、この本は14の物語を通して、人類の未来を描いているのだ。その世界に私たちはいつの間にかズブズブとハマり込み、溺れていく。そして、読めば読むほど、だんだんとこの世界の輪郭が見えてくる。
今にも滅びそうな人類という種。絶滅を防ぐために生まれた小さなグループごとの暮らし。異なるグループの人間との交雑によって期待される新しい遺伝子、進化。──それだけ聞くと、この未来をディストピアのように感じるかもしれないが、どうしてだろう、この世界はときにユートピアにも思える。小さな集団のなかで牧歌的に暮らす人間たちの姿はなんとも愛おしい。絶滅の危機に瀕していても、人間は変わらず、誰かを愛し、憎み、そして、争っている。人間とはなんて面白い生き物なんだろう、なんてヘンテコなんだろう。たくさんの矛盾を抱えながら生きる人間たちの姿を見ていると、そう感じずにはいられない。
と、同時に考えさせられるのは、人間とは一体何なのかということだ。この本には、今とは違う方法で生まれた人間たちがたくさん登場する。たとえば、他の動物由来の細胞でできた人間は、人間と呼べるだろうか。腹腔に人工知能を宿した人間はどうか。はたまた植物のような緑の肌を持ち、仲間に自分の体を食べさせることもある人間はどうか。どこまでが人間と呼べるのだろう。私たちは自分と異なる存在を受け入れることができるだろうか。ある人物は言う。
「にせだってなんだって、生き延びて、そして新しい人類になれば、それでいいよ」
そんな言葉に、あなたは頷けるだろうか。
人工知能、AIが何かと話題の今、私たちをこんな未来が待ち受けていたらどうしようか。恐ろしいようで、あたたかく、懐かしく、寂しい。そんななんとも不思議な読み心地のこの本を読んで、人間たちの未来に思いを馳せてみてほしい。
文=アサトーミナミ




