愛の悩みに、短歌で答える 愛をうたう歌人、初の散文集『ところで、愛ってなんですか?』【鈴木晴香 インタビュー】
公開日:2025/9/20
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

愛という言葉は、ふだん耳にするとどこか大げさにも感じてしまうけれど、感情が抜き差しならぬ状態に陥ったとき、途端に生身で迫ってくるような感覚がある。〈自分自身を愛するには?〉〈愛することが怖いときは?〉〈結婚生活における愛って?〉……。本書の章タイトルが示すように、愛の悩みは様々で、複雑で、切実だ。
「あらゆる悩みは愛に収斂していくと私は思っているんです。恋の相談や夫婦の愚痴、自分を好きになるにはどうしたらいいかなど、悩みの根元にあるのはすべて愛。さらに自分はどう生きていったらいいのか、自分は何者なのか?という問いを抱いてしまうのも、愛が掴みにくかったり、愛に傷ついたりするなかで、〈自分〉というものに向き合ってしまったからではないかと思うんです」
“そんなとき、短歌が役に立つ”。短歌を読み、つくることを通じ、愛に収斂していく悩みを解決してきたと語る鈴木さんは、愛をテーマにした短歌をずっと詠み続けてきた。
「“短歌をつくることは愛することによく似ています”というセリフを作中に入れましたが、“愛すること”は自分を知ることでもある。私はすごく明るい性格なのですが、つくる歌は非常に暗いんです(笑)。短歌をつくることで、自分はこんな風に物事を見ていたのか、本当はこんなに悲しかったのかと気づくことがあって。そしてその気づきを、自分を愛することに繋げることができた。そして、他者を愛することについても。短歌は細部のリアリティが大切です。自分や他者の世界のディテールを思い描くなかで、どのように他者を愛したらよいのかという問いを自身にも差し向けることができるはず」
入口の看板に三十一個のハートが光る愛の相談所〈BAR 愛について〉。その店には愛に悩むお客さんが毎日やってくる。持ち込まれた相談に店主が差し出すのは、カクテルではなく短歌――。連作短編の如くストーリーは流れていくけれど、小説でもエッセイでもない不思議な佇まいを、この一冊はまとっている。
「この本は、ショートストーリーのなかに短歌を編み込んだアンソロジーなんです。短歌にあまり触れたことがない方にも短歌を自分のほうへと引き寄せていただきたくて、短歌の経験者が読むオーソドックスなものとは違う形式に挑んでみました」
〈01 愛はなぜ失ってから気づくの?〉では、その問いを胸に、恋が終わった女性がやって来る。彼女の話に耳を傾けながら、店主は一首、また一首と短歌を差し出していく。
「一章にはそれぞれ五首ほどの短歌が入っていて、悩みに対し、いろいろな角度から歌を差し出すよう心がけました。いくつかの歌に囲まれて、BARのお客さんも読者の方も、自分の答えに辿り着いてもらえたらと」
穂村弘、吉川宏志、枡野浩一、雪舟えま、小島なお、寺山修司……。作風も、視点も、時代も異なる歌人たちの短歌ひとつひとつは、物語の〈その場所〉に置かれたことによって、読む人の思考を開き、心に寄り添う引力を発揮してくる。
“これは私のことだ”短歌が持つ象徴の力
「大好きな短歌を皆さんに紹介したい、というところからこの一冊は始まっているので、物語に合っているからという理由で、短歌は選んではいません。あくまで歌ありき。そして必ずしも愛の歌だけを選んではいなくて」
《北極で北を失ふのと同じ 話すことなくて微笑んでゐる 魚村晋太郎》
この一首は愛を失った人に、BARの店主がはじめに差し出す歌。“そもそも失うってどういうことでしょうか”という問いとともに。
「話すことがなくて微笑んでいる、自分だけ取り残されてしまっているような寂しい歌で、恋愛とは関係ない文脈でも読むことができる。そういう歌も敢えて入れたのは、“今の自分の文脈には、これがしっくりくる”ということをいろいろな方に感じてもらいたかったから。ずっと知っていた短歌が、ある日急に“こういう意味だったのか”と気づくことってあるんです。たとえ愛の歌でなくとも、愛に傷ついているとき沁みてくることがあるのは、短歌の持つ象徴の力なのではないでしょうか。“北極星”を愛に置き換えて読んだとき、“これは私のことだ”と思えるように読めることを伝えたかった」
《くちびるをあわせることをゆるされてはじめてしったやわらかい他者 真野陽太朗》
〈02 自分自身を愛するには?〉で、自分の嫌なところばかりに目がいってしまう男に差し出されるこの歌も、他者への愛を歌っているように思えるが、“ほかはすべてひらがななのに、「他者」だけが漢字であることが、他者の他者性を一層はっきりと浮かび上がらせている”という店主の言葉から誘われていくのは、予想もできなかった自分に対する柔らかな視点。鈴木さんにとって初の散文集である本作の散文=物語の部分は、短歌の読み方を紐解くものとして機能しつつ、短歌と構造を同じくした、驚きを秘めている。
短歌をつくらずに死なないでほしい
「散文を書いているときも、短歌同様に音とリズムを意識しました。短歌をつくるときって、書きたいことの核のようなものはあるけれど、どんな言葉でそれが出てくるかは、音とリズムに導かれるんです。自分が予想もできなかったところに着地することができる。私は常に、自分の作品に驚きたいと思っているんです。私が短歌をはじめたのは穂村弘さんの「ダ・ヴィンチ」の連載『短歌ください』に投稿するところからなんですね。短歌を投稿すれば、一方通行であっても大好きな穂村弘さんに読んでもらえるのではないかと、いわばラブレターを送るような感覚でした。初めて穂村さんの短歌に出会ったとき、こんな現代アートみたいな短歌があるのか、短歌ってこんなに自由なんだという驚きと衝撃を受けた。だから私は短歌をつくるうえでずっと驚きを大事にしているし、読むときも驚きのある短歌に魅力を感じる。この散文を書くときも、自分では制御しきれない部分に導かれながら、歌うように書いていった感があります」
〈片思いがはじまったら?〉〈好きな人に触れたくなったら?〉〈アイドルへの憧れは恋?〉……。愛の悩みは一冊のなかを彷徨っていく。そしてそこにはミステリー的な展開も。
「短歌は三十一音のなかに、伏線回収的なサスペンスを持たせながら、最後に答えを言うつくり方もあるんです。この物語も、全体のなかに三十一音を響かせるよう、緩やかにドキッとさせるように書いています」
そして最後に辿り着くのは、自分の人生のなかで、玉虫色に意味が変化していきそうなこの一首。
《またここにふたりで来ようと言うときのここというのは、時間のこと 鈴木晴香》
「この本を人生の処方箋にしていただきたくて。初恋に悩む中学生から妻を亡くした老人まで、幅広い年代、性別、境遇の人が出てきますので、誰の心にも届く一首に出会えるはずです。世界自体は変わっていないのに、ある言葉によって急に世界が明るく見えることってありますよね。短歌は、新たな価値観を得られる力を持っている。そして私がこの一冊に込めた願いは、“短歌をつくらずに死なないでほしい”ということなんです。読んだら短歌をつくりたくなる本をつくりたかった。誰にも見せなかったとしても、短歌にすることで悩みから救われることもあるし、想いを残すこともできる。自分の言葉を残せることは、ものすごく価値のあることだと私は信じています。ぜひこのBARを訪れ、短歌をつくってください」
取材・文=河村道子、写真=冨永智子
すずき・はるか●1982年、東京都生まれ。短歌結社「塔」所属。『西瓜』同人。2011年、本誌連載の『短歌ください』への投稿をきっかけに作歌を始める。歌集に『夜にあやまってくれ』『心がめあて』、木下龍也との共著『荻窪メリーゴーランド』。19年、パリ短歌イベント短歌賞にて在フランス日本国大使館賞受賞。
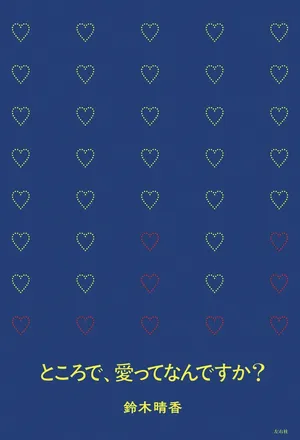
『ところで、愛ってなんですか?』
(鈴木晴香/左右社)2200円(税込)
愛に悩むお客さんが毎日やってくる〈BAR 愛について〉。 持ち込まれた愛の相談に、店主ははカウンターごしに短歌を差し出す。三十一文字という短い言葉の連なりがこんがらがってしまった愛をほどく――。片想い、失恋、自己愛、友愛、性愛、推しへの愛、恋をしないこと……。「愛」を詠み続けてきた著者がショートストーリーで紡ぐ、新感覚短歌アンソロジー。





