1時間5本のバス路線が1日4本に減便…。バスの利用者は全盛期の三分の一になった今、これからの公共交通が抱える問題とは『日本のバス問題』【書評】
PR 公開日:2025/9/30
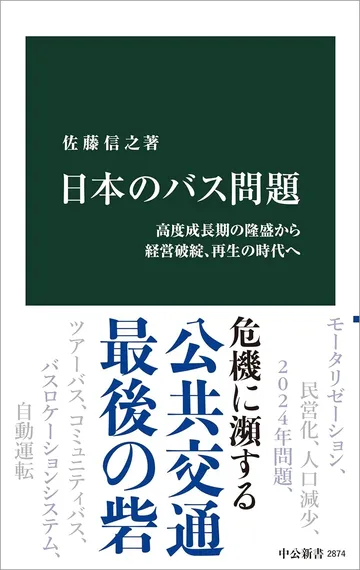
現在開催中の関西大阪万博でも話題の「空飛ぶクルマ」が2027年にも実用化され、「エアタクシー」の事業化が実現するという。従来のヘリコプターと比べて電動のため静粛性に優れる上、離着陸場の場所も小さくて済み「都市部での運航に向く」とのこと。こうした脱炭素社会に向けた新型モビリティの開発の話はなんだかワクワクする話だが、一方で私たちの足元の大事な交通システムが崩壊寸前の危機にあることをご存じだろうか。車を持たない人にとっての大切な公共交通であるはずの「バス」が、今、かなりピンチな状態にあるというのだ。
『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』(佐藤信之/中央公論新社)は、そんなバス業界に襲うクライシスを全方位的に教えてくれる貴重な一冊だ。振り返ればバスの輸送量のピークは高度成長期の1970年であり、当時は乗合バス(一般的なイメージのバス)の乗車数が100億7370万人、貸切バス1億8099万人で、現在のような高速バスはないが合計102億5469万人の利用者がいた。現在はこの1/3に縮小しており、「高齢化」「過疎化」といった日本のトピックがダイレクトに影響し、「公共交通の最後の砦」といわれたバスがあちこちで減便や路線の廃止、さらには会社の清算が相次ぎ…バスという交通網が抱える問題はどうしても局所的に、ローカルにならざるをえず、なかなか見えてこなかった現実に戦慄するかもしれない。
本書はそんな「バス」の現状に向き合い、未来を考えるための大切な一冊だ。著者の佐藤信之氏は社団法人交通環境整備ネットワーク代表理事・会長、NPO法人全国鉄道利用者会議(鉄道サポーターズネットワーク)顧問などを歴任し、現社団法人交通環境整備ネットワーク相談役として交通政策について研究・評論を続けている専門家。本書ではバスの現状はもちろん、日本でバスという交通網がどのように広がったかを歴史的側面もきっちり深掘りしていく。この本を読めば「日本のバス」についてのかなり専門的な知識を得ることができるのは間違いない。
本書で面白いのは地域に根ざしたバスだけに、情報がかなり細かいこと。たとえば千葉県千葉市の稲毛で(東京から1時間以内の都市化されたエリア)1時間に最大5本走っていたバスが赤字の影響で2024年のダイヤ改正で1日4本だけになってしまった件。さらには神奈川県川崎市ではバスは「公営」で乗務員の給与が川崎市職員に準じた額だったため、バスとしては採算が取れない高額だったことで減給&減便を余儀なくされてしまった件。そのほか横手、唐津、岐阜などなど、日本全国のさまざまなエリアの細かな情報が次々に集積され、それが問題の切迫さをリアルに伝えてくれる。
この先高齢化社会がすすめば、今後は免許返納ほか公共交通の重要性はさらに高まるに違いない。今はバスを利用していない人は関係ないと思うかもしれないが、いつ自分の問題になるかわからないわけで、その意味ではバス問題は広く共有されるべき社会課題だろう。すでにコミュニティバスやライドシェアなどの取り組みは始まっているが、本書で多くの人が問題を共有することも何かの力になるかもしれない。そんな未来に期待したい。
文=荒井理恵




