鮎川哲也賞『禁忌の子』の次の作品は? 過疎地の病院が舞台のパニックスリラーミステリー【山口未桜 インタビュー】
公開日:2025/10/20
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。
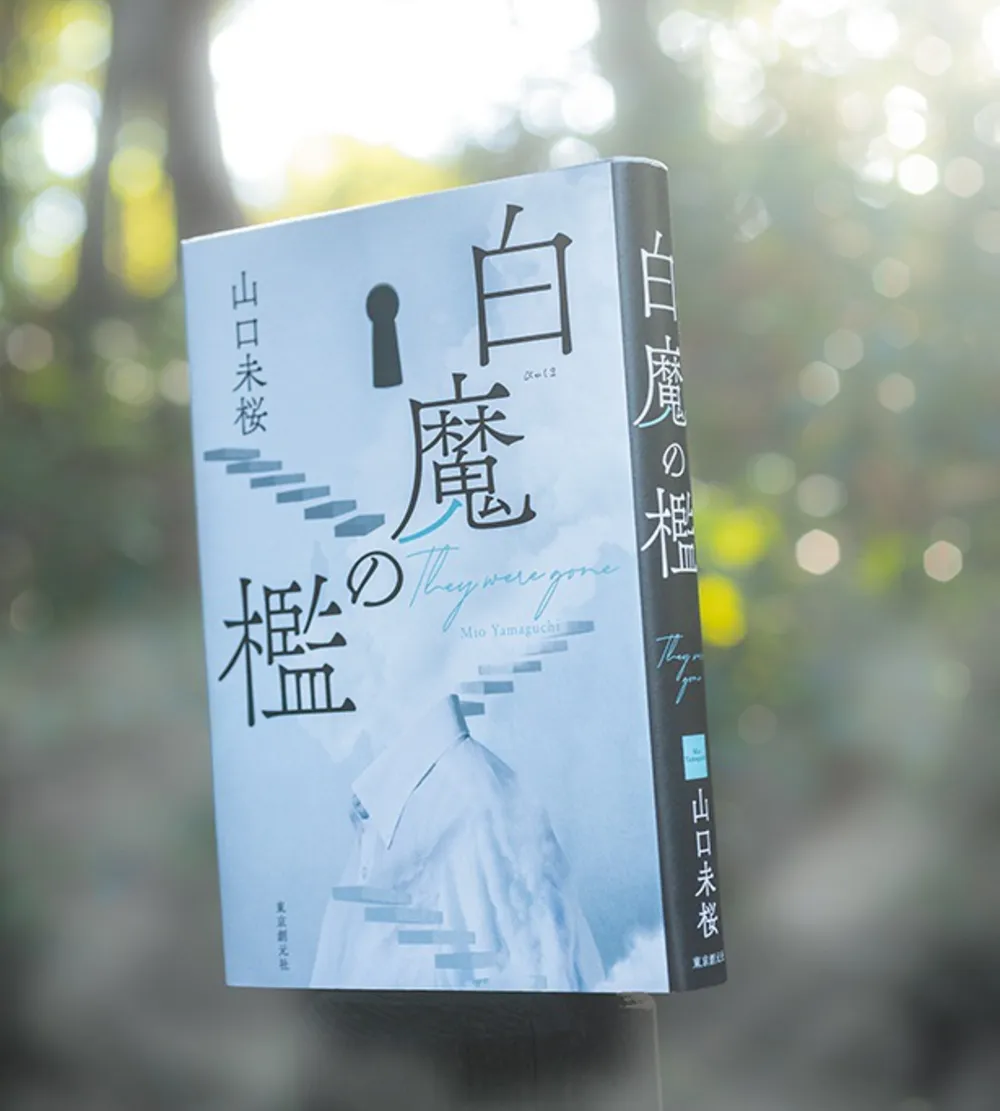
本屋大賞候補作家、待望の新作はクローズドサークルものだ。
鮎川哲也賞を受賞した山口未桜のデビュー作『禁忌の子』は2025年の本屋大賞最終候補に選ばれるなど、ミステリーというジャンルを超えたヒット作となった。その注目作家の第二作がいよいよ登場する。『白魔の檻』は北海道の過疎地にある更冠病院を舞台とする物語だ。第一作では旧友が巻き込まれた事件を解決した医師・城崎響介が、今度は濃霧と有毒ガス発生によって孤立した病院内での謎解きに挑む。
「『白魔(ルビ:びゃくま)の檻』は、『禁忌の子』を鮎川哲也賞に応募している間、それが落選したら次に出そう、と思って書き始めていた作品でした。私は北海道の病院で勤務していたことがありまして、そのときの体験を参考にした部分があります。過疎地の病院を舞台にした作品はいつか書いてみたいとずっと思っていました。そうしたところから出発したこともあって、結果として前作とはまったく違う話になったのだと思います。『禁忌の子』は、自分と瓜二つの溺死体が見つかる、というイメージが最初にあり、そこから作っていったお話です。今度はパニック的なシチュエーションが次々に起こるというのが土台にある着想で、同じことをやってもつまらない、という思いはありました」
探偵役である城崎響介の相棒役は、『禁忌の子』では旧友である医師の武田航が務めたが、本作では更冠病院にやってきた研修医の春田芽衣がその役に就く。大きな変更点だ。
「この連作では視点人物を変えながら城崎自身の謎も解いていこうと思っています。医師としては後輩なので、春田は城崎との距離が遠い、事件を通じてだんだん近づいていく過程が書けるということで、その点でも前作とは違った物語にできたかなと思います」
論理の美しさに惹かれる
外界と隔絶された状況で謎解きが行われる物語は、クローズドサークルものと呼ばれる。これまでも数多くの名作が書かれてきた形式だ。
「クローズドサークルには一度挑戦してみたいと思っていました。前作ではエラリイ・クイーンの背理法を駆使した推理法に影響を受けた側面があるんですが、自分が読んできた有栖川有栖先生『双頭の悪魔』や綾辻行人先生『十角館の殺人』に対するリスペクトを表明したいという気持ちが今回はありました。ミステリーの先行作品からはさまざまな影響を受けていると思います。内容に踏み込んでしまうことになるので詳しくは言えないのですが、ミステリーの技巧としてやってみたかったことが複数ありまして、アイディアとしてはそこを土台にして組み立てていきました」
城崎が行う推理の鮮やかさが作品の第一の魅力だ。背理法を駆使した論理展開には目を惹かれる。
「私はこじつけっぽい推理があまり好きではなくて、きれいな補助線を引くことによってすべてがスーッと解ける、という算数の美しい解法のような解決編が好きなんです。たとえば有栖川先生の『スイス時計の謎』はとても好きですね。その美しさをできる限り自分でも実現してみたい。小学生のときからロジックパズルを解くのが大好きだったんですけど、ジュヴナイル版の『Zの悲劇』に出会いまして、人生で唯一、読んで興奮で寝られなくなるという体験をしました。論理が好きなんですよ」
死の恐怖が支配する物語
同時に、スリラーとしても高く評価すべき作品だ。有毒ガスの発生によって登場人物たちは死の危険に脅かされ、さらに殺人の恐怖が加わるのだ。手に汗を握る展開が続く。
「今回は病院の中に87人もいて、その人たちを全員動かさなければいけないので大変でした(笑)。全員年齢や性別などのバックボーンを設定してありまして、病棟の何階に誰がいるかもあらかじめ決めていました。2階は年配の人が多いのでそれなりの年を感じさせる名前、3階は急性期病棟なのでもう少し下の世代に見える名前にするとか。病院経営をされている方にもシステム部分について、この規模の病院だと100床は超えないくらいで運営されているのではないか、などとご意見を伺いました。まず物語の外側ができたんです。そうやって登場人物が動くフィールドを厳密に決めたことの効果はありました。東日本大震災における病院の資料も読みまして、自分が実際その場にいたらどう対応するだろうか、という医療従事者だからこそ見えてくることも検討しています。そこをできるだけリアルに描かないとこの物語は成立しないんです。スリルが盛り上がっているとすれば、リアリティを求めた結果でしょう」
謎解きの関心と並行して、緊急事態下で医療従事者はどのように行動すべきか、ということが書かれた小説でもある。物語の膨らみはどのように生まれたのだろうか。
「東日本大震災と物語を対比して描くというテーマは比較的初期からありました。本作の初稿は2024年の3月に書き上がったんですが、その後で『禁忌の子』が受賞して、編集者の方と相談しながら改稿を重ねていきました。変化しすぎていて、元はどうだったかが思い出せない部分もあるんですよ。そもそも最初は三人称で書いていたのを一人称に改めていますし」
デビュー作の『禁忌の子』が高い評価を得て、注目を集めたことにより、小説執筆に対する態度や考え方が大きく変わったという。
「求められる偏差値が上がったと言いますか。『禁忌の子』で高くなったハードルを乗り越えることも望まれる。でもプロになって、自分ひとりではたどり着けないところの景色も見られましたし、自分の本当にやりたかったこと、書きたかったものが実現できていると思います」
山口作品の根底に流れているのは古典的なミステリーに対する憧憬の念だと思われるが、それ以外にも物語全般への広い関心が窺える。
「クラシカルかつレトロ嗜好というのは確かで、そこは若干、現代ミステリーの流行りからは外れているかもしれません(笑)。ただ、自分の幅を広げることでおもしろいミステリーを書ける筋力を鍛えたいとは思っています。毎回違うことをやるほうが好きなので、今も3つぐらいミステリーのアイディアは抱えています。これまでの作品はガチガチの本格だと思うんですけど、いろいろな自分の可能性は試してみたいですね。たとえば『白魔の檻』はテーマも含めかなり重い作品になりましたが、ライトなものにも挑戦してみたいです」
いつかは挑戦したい課題がある
「医師であるという自分の立場でしか書けないものもあるはずなんです。実生活では母親であり、かつ医師として働いていることから、その両方を兼ねた主人公を非常に解像度高く書ける。それは自分が絶対に書くべきだと思っています。医療従事者ということで言えば『白魔の檻』もそうした部分は意識していて、ラストシーンは何度も書き直しました。最後の10ページ、登場人物の心の動きはものすごく細かく手を入れていますから、そこが物語の余韻として伝わっていたら嬉しいですね」
『白魔の檻』は、山口の創作に対する真摯な姿勢が産み出した物語だ。その先があるなら、ぜひ読んでみたい。未読の方も、まずはここから作者を知ってみてはいかがだろうか。
「『白魔の檻』と『禁忌の子』は、どちらが先でも楽しんでいただける作品になっていますので、安心してお読みください。主人公である春田が最後にたどり着く景色を一緒に見届けていただけたらと思います」
やまぐち・みお●1987年、兵庫県生まれ。神戸大学卒。医師として働く傍ら小説執筆に挑戦、2024年に『禁忌の子』で第34回鮎川哲也賞を受賞し、デビューを果たした。同作は医師・武田航の出生にまつわる謎を、彼の旧友で、変人だが怜悧な頭脳の持ち主である同僚の城崎響介が解き明かすという内容で、衝撃の結末が話題を呼んだ。2025年本屋大賞の第4位に選出される。
取材・文:杉江松恋 写真:首藤幹夫
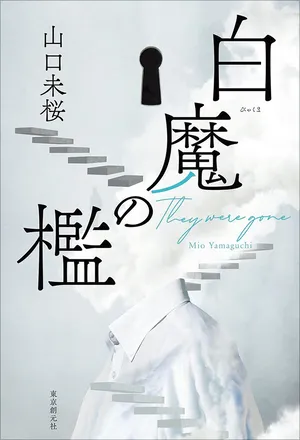
『白魔の檻』
(山口未桜/東京創元社)1980円(税込)
研修医・春田芽衣は、地域医療実習のため北海道の更冠病院に派遣されることになった。先輩医師の城崎響介もへき地医療支援のため同行する。現地に到着した二人は、病院が濃霧のために周囲から孤立していることを知る。さらに建物の中では、一人の職員が変死を遂げていた。殺人の可能性に加え、さらなる危機が迫る。大地震の影響で建物に硫化水素ガスが流れ込んできたのだ。緊迫の物語。
東京創元社 1980円(税込)





