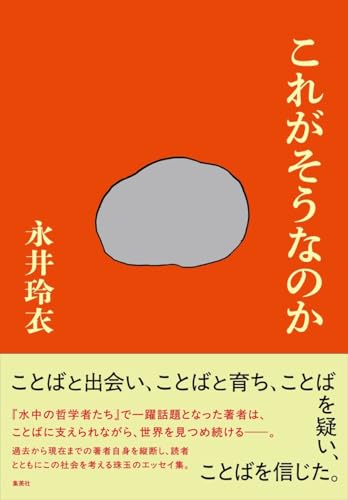対話から生まれる信頼が、社会への信頼を育てる。「本に育てられた」永井玲衣が、他者の言葉を通して見る景色とは【『これがそうなのか』刊行記念インタビュー前編】
公開日:2025/11/6

2024年に第17回「わたくし、つまりNobody賞」を受賞した、作家・哲学者の永井玲衣さん。各地で行われる哲学対話をはじめとして、表現を通して戦争について対話する写真家・八木咲さんとのユニット「せんそうってプロジェクト」、Podcast「夜ふかしの読み明かし」など、数々の対話の場を作る永井さんが、このたび新著『これがそうなのか』(永井玲衣/集英社)を上梓した。
本書の第1部では、日々生まれる「新語」から生まれる問いに向き合い、「なぜ、その言葉が作られたのか」をひもとく。第2部では、“本を育て親とし、師とした”永井さんの読書体験に基づき、“言葉を適切に保存する”試みを通して、世界との対話を望む。
本書執筆の経緯、永井さんにとっての哲学対話の原風景、読書体験から生まれた衝撃についてうかがった。
「本と世界が手をつないだ」日、この世界で生きていこうと思えた

――新著『これがそうなのか』は、さまざまな言葉から生まれる問いを軸にして、世界との対話を望む姿が印象的な作品でした。本書を執筆したきっかけ、経緯について教えてください。
永井玲衣(以下、永井):本書は、『青春と読書』に掲載された連載エッセイ「問いはかくれている」が元になっています。この連載を担当してくださった集英社の担当編集さんに、「私たちが新語として出会う〈推し〉や〈あーね〉などの言葉に隠れている問いを見出していく連載を執筆しませんか」とご提案いただき、連載がはじまりました。
私は対話の場を持つ活動を12〜13年ほど続けているのですが、いろんな場で、いろんな人の言葉に出会います。そこで出会う言葉のひとつひとつに、切実さみたいなものを感じるんです。それがぽろっと出てしまった言葉だったり、あるいは新語と呼ばれ、「ああ、なんか新しい言葉ね」「軽い言葉だよね」と思われるような言葉だとしても、絶対にその人の温度みたいなものがあって。その言葉を大切に受けとりながら、その奥に何があるのかを一緒に考えることができたらいいなと思いながら書いたのが、本書の第1部です。
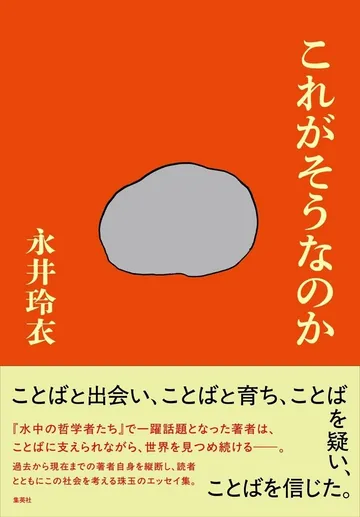
――第2部では、永井さんのこれまでの読書体験を中心として、言葉への問いが続きます。第2部につながる流れは、どのようにして生まれたのでしょうか?
永井:日頃、私が言葉についてよく考えているので、「そんな“私の言葉”を育ててきたものが何なのか、どんな読書体験があったのかを書いてみるのはどうですか」と言っていただいたのがきっかけです。
第2部冒頭の「恥辱だけが」に書いたのですが、私は本に閉じこもっていて、本に育てられてきた子どもだったんです。でも、本が私をちゃんと現実に突き飛ばしてくれて、はじめて現実に触れた時、「これがそうなのか」とため息をつくような衝撃を受けながら、この世界で生きていこうと思えた瞬間がありました。その体験を丁寧にひもといていきたいと考え、本書の第2部につながりました。
――「恥辱だけが」の部分にある、「本と世界が手をつないだ」という表現が強く印象に残っています。17歳の頃にフランツ・カフカに出会い、そのように感じた日を境に、読書に対する向き合い方に変化はありましたか?
永井:私は、自分の変化を言葉にするのが本当にゆっくりなので、書きながら考えるんですよね。なので、書いていく中で気づいていったというのが一番大きいと思います。『水中の哲学者たち』を執筆した頃には、こんなにも本に閉じこもった人間なのに、なぜ毎日のように対話の場を持つことになったのか、自分でもよくわからなかったんです。でも、今回の連載を通して、“そういうことだったんだ”と腑に落ちた景色を、ゆっくり言葉にしているのかもしれません。