恩田陸「いまだに『小説家になりたい』と思っている」 傑作バレエ小説『spring』のスピンオフ誕生秘話と、創作を続ける理由【インタビュー】
公開日:2025/12/10

構想・執筆に10年を費やした、恩田陸氏の渾身のバレエ小説『spring』(恩田陸/筑摩書房)。その舞台裏を描くスピンオフ短編小説集『spring another season』(同)が刊行された。続編の制作が決定する前から、著者自ら書きためていたという本作は、どのように誕生したのか? 創作の裏側から、バレエを通じてだからこそ描けたもの、そして、作家自身が抱く「小説家」への尽きない“憧れ”について聞いた。
――長編バレエ小説『spring』のスピンオフ短編小説集となる『spring another season』。『蜜蜂と遠雷』同様、やはり舞台にはアンコールが必須だよな、と心が躍りました。
恩田陸(以下、恩田) アンコールといいますか、ボーナストラックといいますか。続編を書こうというつもりはなかったのですが、連載中からいろいろ書いておきたいことが湧き出てしまって、頼まれもしないのにスピンオフをいくつか書きはじめていたんですよ。とくに本編の第四章……当初は語り手にするはずではなかった春を主軸に据えたことで、それまで私自身もとらえきれていなかった彼の実像が浮かび上がってきて。
――そもそも『spring』は、周囲を魅了してやまない振付師・萬春をめぐる人々の物語。第一章は同期とも呼べるダンサー、第二章は彼を見守る叔父、第三章は幼なじみの作曲家の視点で語られていきますが、どこかとらえどころのない人物として描かれますよね。
恩田 私自身も、三章までは春がどういう人なのか、あんまりよくわかっていなかったんです。だから、師匠であるジャン・ジャメを語り手にするか、俯瞰して三人称視点で描くつもりだったのをやめて、本人に語ってもらいましょうとできあがったのが第四章。そうしたら、思っていた以上に春は単純で、いい加減な人だったんですよね(笑)。
――あたりまえに感情の起伏がある、どちらかといえば人間くさい人なんだな、というのは読んでいても意外でした。
恩田 意外と受け身で、流されがちなところもありますよね。だからこそ、スピンオフが書けたんだと思います。天才というと、なにもかもパーフェクトにこなすことができる、超人的な存在を思い浮かべがちだけど、現実にそう呼ばれる人たちだって、そんなことはありえない。あたりまえに間違えるし、悩むし、多面的な性格を持ち合わせているんだということも、ちゃんと書いておきたいなと思いました。
――個人的には、思った以上にダンサーの恋人・フランツとのエピソードが多くて、驚きました。〈惚れたのは確かだけれど、俺はフランツのことを本来の意味では「好き」にはならなかったように思う〉と本編で書かれていたけれど、めちゃくちゃ好きだったんじゃないか……と。
恩田 でも、バレエを介して結ばれている二人だから、フランツが退団してしまえばもう、二人を繋ぐものはなくなってしまうんですよね。情だけで結びつくことができなかった、という意味で「好き」ではなかったのだろうと思います。フランツのことは、実はあんまり興味がなかったのですが、春と付き合っているならしかたない、と書いていたらけっこう好きになりましたね(笑)。意外と典型的なツンデレでかわいらしい人でした。
――貴族出身の家系に生まれ、背負うものの大きいフランツが、何を抱えているかが描かれているところにもぐっときました。幼少期に受けた傷を、春と共有するところも……。
恩田 美しいというのは、ある種の災難でもあるんですよね。まったく望まないかたちで誰かの欲望に晒され、結果、ひどい事件に巻き込まれてしまうことが、世界のあちこちで起きている。バレエを題材に書く以上は、その一面についても触れないわけにはいかないなと思いました。自分を守るために沈黙を選択したことで、自分ではない誰かを守ることができなかった。そういう罪悪感を背負っている子どもたちもきっとたくさんいるだろうな、と。
――そういう意味で、本編以上に「天才」とひとくくりにされてしまう人たちの裏側にあるものが、『another season』では描かれていましたね。どのエピソードも短く、読み心地は軽やかなのに、ずんと胸にくるものがありました。
恩田 ありがとうございます。個人的には、初版のノベルティ・ペーパーの内容を考えているときがいちばん楽しかったんですよ。作中で開催されることになる「萬春スペシャル・ガラ」の四部構成プログラム、我ながらけっこうイケていると思っています(笑)。曲とダンサーの組み合わせも、かなりいいと思うので、ぜひ誰かにつくっていただきたいという野望も抱いております。

――どこで、このプログラムを見られるんだ!? と前のめりになりました(笑)。春の自作解説コメントもいいですよね。
恩田 ありがとうございます。『another season』に収録されている12編のうち、いくつかは、そのプログラムの裏側で何が起きていたかという物語なので、ぜひあわせて楽しんでいただきたいです。個人的には「 DANCE in Matisse」……ヴァネッサ、ハッサン、純にフランツ、そして春が大集結した裏側を書けたのが、楽しかったですね。なかなか、このメンツが一堂に会することはないので。バレエとしても、いちばん、観てみたい演目でもあります。
――『蜜蜂と遠雷』と違ってさすがに実写化は難しいだろうというのが悔しいですが……。『spring』は、人は他者との関わりあいによって育つのだということが、これまでの作品以上に深く描かれていましたよね。一人でも天才として立つことのできる人たちが、出会うことによってさらに才能を開花させていく姿が。
恩田 そうですね。私が『spring』で描きたかったのは、バレエそのものなんですよ。ダンサーの成長物語ではなく、バレエというジャンルをまるごと描くことで「才能とは何か」を浮かび上がらせたかった。才能というのはいろんな場所に芽吹いていて、誰かとの関係性で発揮されることもあれば、批評やサポートという表には目立たないかたちで紡がれていくものもある。個人の才能だけでなく、さまざまな才能が出会い、重なりあうことで生まれるものをすべて、書いてみたかったんです。もともと、触媒めいた人が好きで、受け身だけれど働きかけもする、双方向的な存在を通じて、人がどう変わっていくかを描きたいと思っていることにも重なりました。
――バレエを通じてだからこそ描けた、と感じるものはありますか。
恩田 『チョコレートコスモス』では演劇を、『蜜蜂と遠雷』では音楽を通じて、才能というものを描いてきましたが、バレエはとくに身体性が必要とされる芸術だと思うんです。いまだに、公演を観るたび、肉体的な動きを積み重ねて築きあげられてきた「型」の強さを思い知ります。もちろん、演劇にもメソッドはあるし、音楽にも基礎とされる型はあり、解釈によって表現が変わる、という意味では同じなのだけど……型の強度が違うんですよ。たとえばバレエって、動き自体はけっこう不自然でしょう?
――ふつうの人が、日常ではしない動きの連続ですね。
恩田 そう。でも、舞台を観ているとふと、その不自然な動きが自然に見える瞬間がある。そう見せるために身体を矯正し続けているのがすばらしいんだ、というようなことを、本で読んだことがあります。いわれてみれば、歌舞伎もそうですよね。ある程度誇張することで、何かに見立てて、動きを記号化しているはずなのに、それがあたりまえのように見える瞬間が訪れる。だから、舞台に呑みこまれる。
――考えてみれば、矛盾していますね。記号化しているものが、自然に見えるというのは。
恩田 そうなんですよ。でもそれこそが、芸能というものなのかもしれない、と思いました。民族舞踊も、きっと同じ。不自然に誇張された動きを、自然なものに変えてしまう。そのために、厳密な型がある。そして、その型があるからこそ逸脱することも壊すこともできるのだ、と。
――神社で奉納されるお神楽にも通じるものがありますね。守られるべき型をみんなしっかり踏襲しているのに、たとえ面をつけていても舞い手が誰だかわかってしまう。型があるからこそ、生まれる個性がある。
恩田 踊りとはすべて、そういうものであり、優劣のない等価なものかもしれない、と思います。以前、パリのオペラ座バレエのDVDを観たあと、続けてすぐにTVで郡上八幡の盆踊りを観たんです。たしかにバレエのほうが動きの難易度は高く、選ばれた人しかできないものだけど、それに比べても盆踊りはまったく見劣りしなかったし、踊りとしての必然性が感じられて、ものすごく美しかったんですよね。
――踊りには、個性が出る。それはすなわち、生き方が出るということなのかもしれないなと、『another season』を読んでいて改めて思いました。
恩田 肉体の限界と向き合わざるを得ないバレエは、とても刹那的な芸術でもある。でも、だからいいんだと、お話しをうかがったダンサーの方がおっしゃっていました。年をとればどうしても引退せざるを得ない、全盛期と呼ばれるときも、ほんのわずか。短い時間のなかに凝縮せざるを得ないものがあるからこそ、感じることのできる永遠があるのかもしれないと思います。それを、感じさせてくれるのがバレエの素晴らしさなのだとも。
――そうした踊りをテーマに描く小説で、春がダンサーである以上に振付師であるというのが、本作の魅力だったと思います。
恩田 先ほども言ったように、バレエというものをまるごと描いてみたかったというのもありますし、才能のかたちはひとつじゃないんだということも表現してみたかった。たとえば、『another season』に登場する美潮は、本編三章の語り手である七瀬の姉。あなたのバレエは正しすぎる、と言われてしまった彼女のことが、本編を書いたときから気になっていたのですが、努力して努力して、さらに努力して、逸脱することなく型を徹底的に守り続けることができるのもまた、ひとつの才能だと思うんですよ。
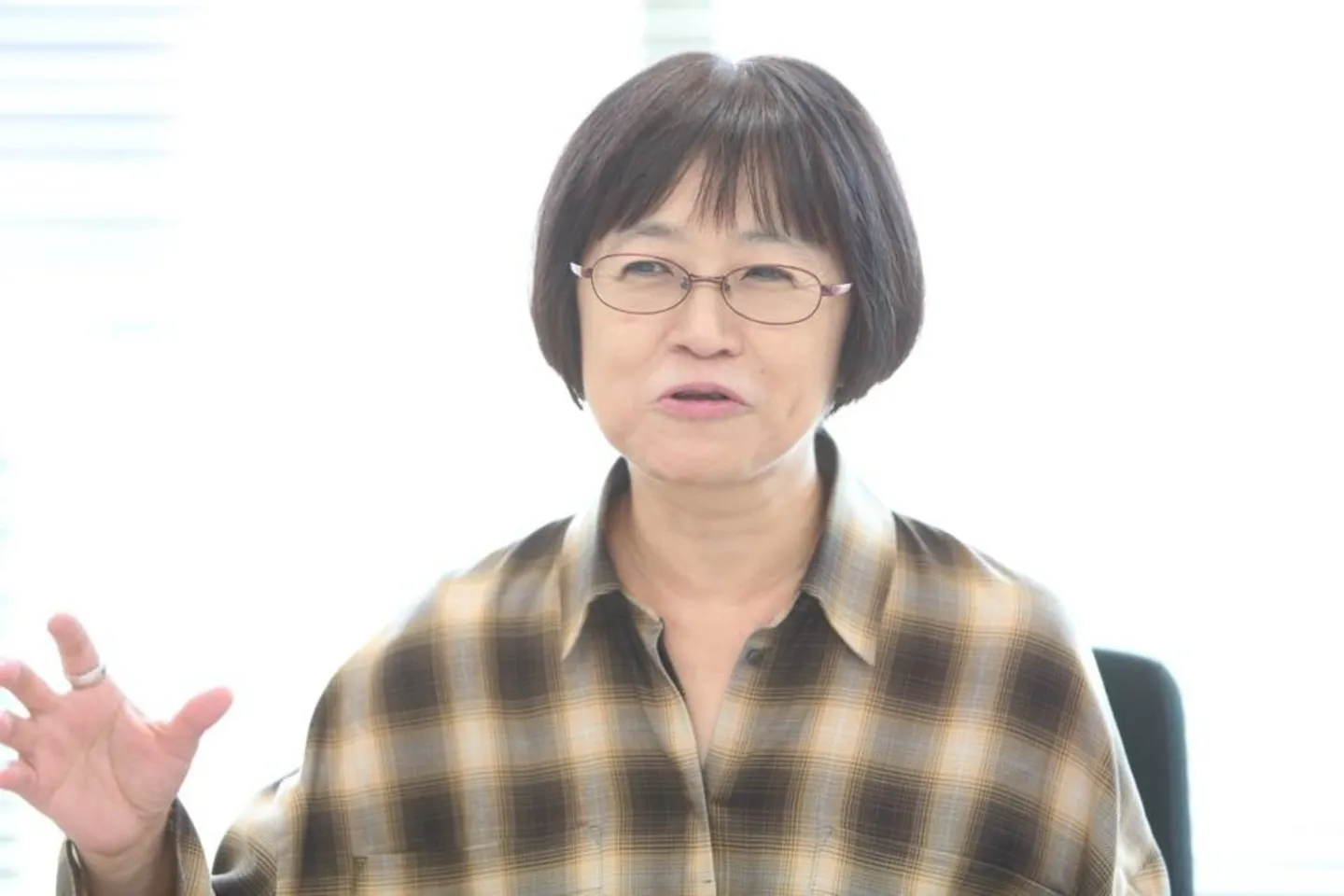
――自由奔放な才能に囲まれながら、ひたすら自分にできる努力を重ねる彼女が、その後どうしたのかは気になっていたので、読めて嬉しかったです。
恩田 私も彼女のことはとても好き、というか、こういう人がいてほしい、という願いを託しています。まっしぐらに努力で道を切り開き、めざすものを実現させていく。いわゆる天才型とは違う、まじめな彼女に共感してくれる読者も多かったので、書けてよかったなと思います。本当に、才能の表出は人によって異なるから、面白いですよね。私が才能を描くことに惹かれるのは、「こんなこともできるのか!」と驚く瞬間を求めているからかもしれないな、と思います。
――今後も、才能についてまた描かれるご予定はありますか?
恩田 いいかげん『チョコレートコスモス』の続編を出さないといけないなとは思っています(笑)。『蜜蜂と遠雷』と『spring』を経て、またお芝居を観る感覚は変わっていますし、ミュージカルを観るときにもやっぱり、以前より、音楽や踊りに目が向くようになっているんですよ。まわりまわって経験してきたことを、投影できればいいなと思っています。
――個人的には、評価とか勝敗とかを超えてただ「バレエってこんなにも美しくて楽しいものなんだ」と教えてくれる春に、恩田さんが重なるんです。「小説ってこんなにも面白くて楽しいものなんだ」という根源的な喜びを、いつも、思いださせてくれる。変わらずにそうした物語を生み出し続けていらっしゃることに、圧倒されます。
恩田 書いているときは、いろいろ苦しみがあるんですけど(笑)。たぶん、意地なんだと思います。昔好きだった作家さんの本を、なん十冊と追い続けるうち、面白くなくなっちゃったなあとがっかりした経験があるからこそ、自分の読者には同じ思いをさせたくない。あとは、30年も作家を続けながら、ずっと小説家という商売に憧れ続けていることも大きいかもしれませんね。いまだに「小説家になりたい」と思っているふしがあるので。
――いまだに!?
恩田 書店に入るときは今もただの一読者なので、素敵な装丁の本を見かけると「いいなあ」ってデビュー前と同じように憧れるし、小説家になったという実感をいつ得られるんだろうか、とときどき思います(笑)。だから、憧れの職業に恥じない小説を、これからも書いていきたいですね。

取材・文=立花もも、撮影=川口宗道







