自由に休んでいい小学生の休暇「トクベツキューカ」はいつ使う? ほっこりする物語の名手・清水晴木さんに聞いてみた
PR 公開日:2024/5/15
一年で一日だけ、自分の好きな日に学校を休んでもいい日――通称トクベツキューカ。習千葉小学校の五年生の生徒たちは、どんな日にトクベツキューカを使うのでしょう?
心あたたまる作風が人気の清水晴木さんの新作『トクベツキューカ、はじめました!』(岩崎書店)は、子どもたちの友情や悩みを四季の変化とともに描いた作品。トクベツキューカというアイディアはどこから生まれたのか? 作品に反映されたご自身の少年時代の体験などをうかがいました。
――自由に休んでもいい日があるなんて、なんて素晴らしい小学校だろうと思いました。
清水晴木(以下、清水):大人の会社員に有給休暇があるように、子どもにだって堂々と休んでいい日があってもいいのに……そんな考えが最初に浮かびました。というのも、自分が子どもだった頃、どうしても学校に行きたくない日がときどきあったんですよ。学校が嫌いなわけではなかったんですけど、単に今日はだるいなとか、もうちょっと寝ていたいな、とか。そういうときに自由に休める権利が一日だけでもあればなあ、と思っていて。現在は「休むこと」についての考え方が、昔と比べてだいぶ柔軟になりました。皆勤賞を廃止した学校も多いと聞きますし、作中にも書いているラーケーション(社会学習を目的として学校を休むこと)を取り入れている県もあります。ならば、子どものための特別休暇を組み込んでいる学校があってもいいんじゃないか、と。
――登場人物たちのトクベツキューカの使い方は様々ですね。第一話の凛は、朝起きたら雪が降っていて寒いからという理由で使っています。その気持ち、とてもよく分かります(笑)。同じく休んだ妹と雪遊びをしていたら、謎めいた少女の有希と出会って……。
清水:第一話から第三話までは、対照的な者同士の掛け合わせになっています。ちょっと幼さの残る凛と、大人っぽい有希。第二話では、友だちグループの板挟みにあっているさくらと、人からどう思われようとも気にしない志保。凛もさくらも、自分と正反対の相手と出会ったことで物を見る目が変わったり、新しい関係をつくったりしていきます。

――第三話は親友同士の悠馬と和人の話です。2人はトクベツキューカを利用して、国道十四号を自転車で旅します。習志野から出発して幕張本郷駅、船橋駅と、自転車を漕ぐ目線で景色が移り変わる様子がこまやかに描かれているのが印象に残りました。
清水:これは自分の体験を基にしてるんです。僕も小学校時代に友人と、線路沿いに東京までの道をずーっと自転車で漕いで行ったことがあって。次第に日が落ちてきて、そろそろ戻らないとやばいな、と思いながらもなかなか引き返す気持ちになれなくて、夕暮れのなか進み続けたことを今でもよく憶えています。自転車での日帰り旅って、小学生男子なら高確率でやっていると思うんですよ。見本誌を読んでくださった男性の書店員さんたちからも、同じような体験をした、という反応をけっこういただきました。また、僕は千葉を舞台にすることをこよなく大切にしているので、千葉の街それぞれのカラーも感じとっていただけましたら。
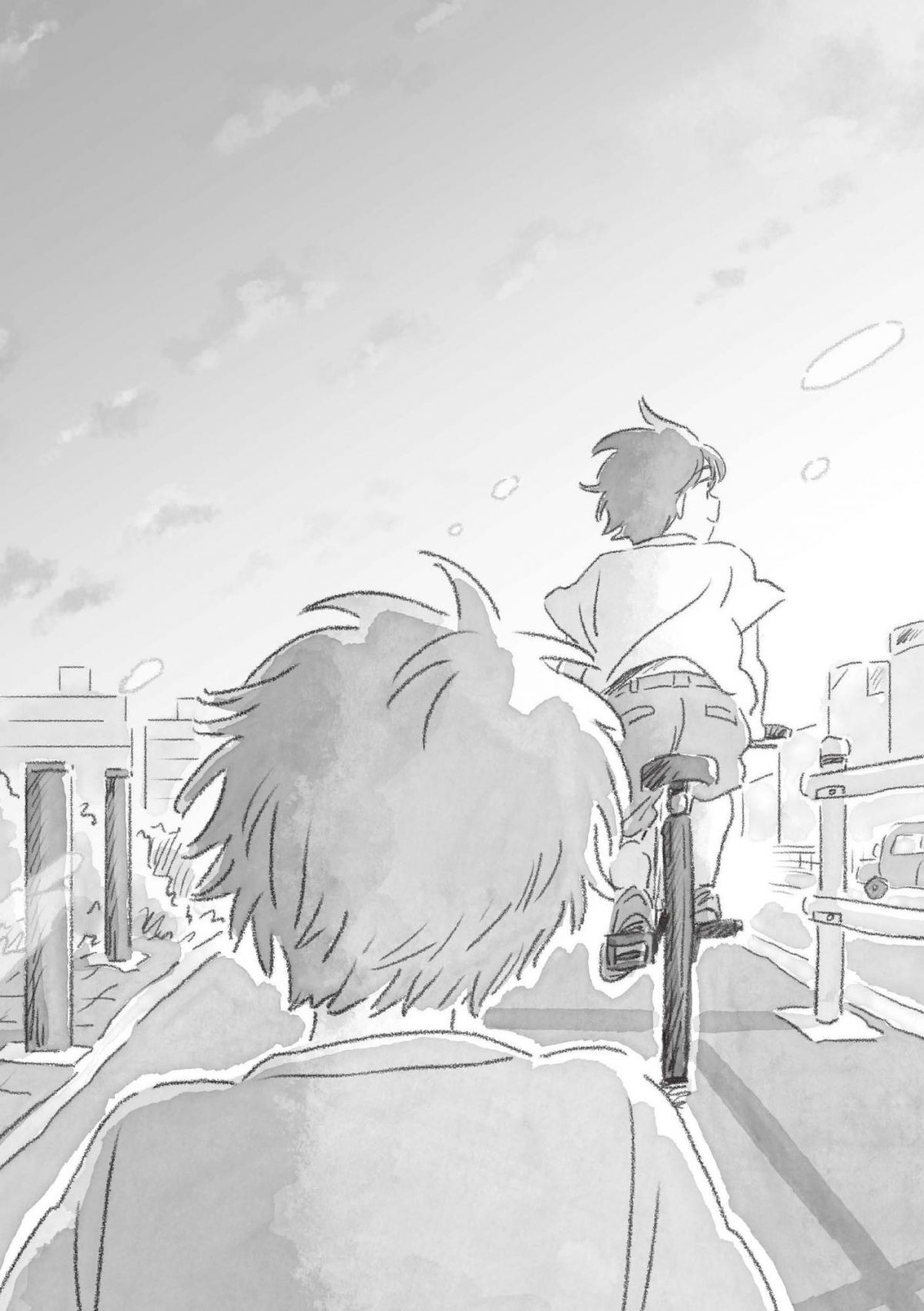
――悠馬と和人は親友同士ですが、悠馬はひそかに和人をうらやんでいます。自分の家とちがって仲のいい両親に、裕福な環境。そんな自分にもやもやする悠馬の心情が、読んでいて刺さります。
清水:小学生の悩みの多くは友人か、家族関係なのではないでしょうか。この2つが子どもの世界を構成しているので。この本を読んでくれる読者のなかにも、家庭に悩みを抱いている子はきっといると思う。そういう子たちの悩みを掬いあげたくて第三話を書きました。
――悠馬はこの一日旅をとおして、自分とちがって恵まれていると思っていた和人にも悩みがあるということに気がつきます。
清水:そうですね。そもそも悠馬が憧れていた「普通の家族」なんてものは存在しないかもしれない。どんな家族にだって悩みはあるし、問題もある。そのことに悠馬が気づけることが大事なんです。この第三話のあたりから、作品全体のテーマがだんだん浮き彫りになってくるようにしました。僕は小説を書く際、予め読者への問いかけを用意しておくのですが、今回のそれは「特別の休みがあったら、あなたはどう使いますか?」。そこにしのばせたテーマが「普通」と「特別」なんです。
――第四話以降は明確にそのテーマを打ちだしています。第四話の主人公は、習千葉小学校に転校してくるまで学校を休みがちだった浩。最終話となる第五話では、学校をほとんど休んでいる状態の有希に焦点を当てています。第一話にも登場した有希の背景が明かされるのと同時に、他の生徒のようには“普通”に学校へ行けない彼女の心情が切々と展開されます。
清水:小学生の頃って、みんなと同じようにしないといけない、とか、みんなに合わせなければならない、といったことをすごく求められませんでしたか? ほとんどの人は大人になったら忘れてしまうかもしれないけれど、僕はけっこうそういうのを憶えている方で。ふしぎなことに、成長していくにつれ個性を出すことを良しとされるのに、子どものうちはみんなと同じであることを暗に強制されがち。考えてみたら、すごいプレッシャーですよね。四、五話ではトクベツキューカの必要性を僕なりに考えています。
――担任の西方先生と有希の対話は、本作の核となるシーンですね。自分もかつて学校へ行けない時期があったと先生は打ち明けてくれて、有希の気持ちに寄り添ってくれる人物であることが、言葉の端々からも伝わってきます。
清水:あの場面はこの作品のテーマの語りあいみたいな部分なので、一番気をつけて書きました。テーマにふれるシーンなだけに、説教くさくならないように。
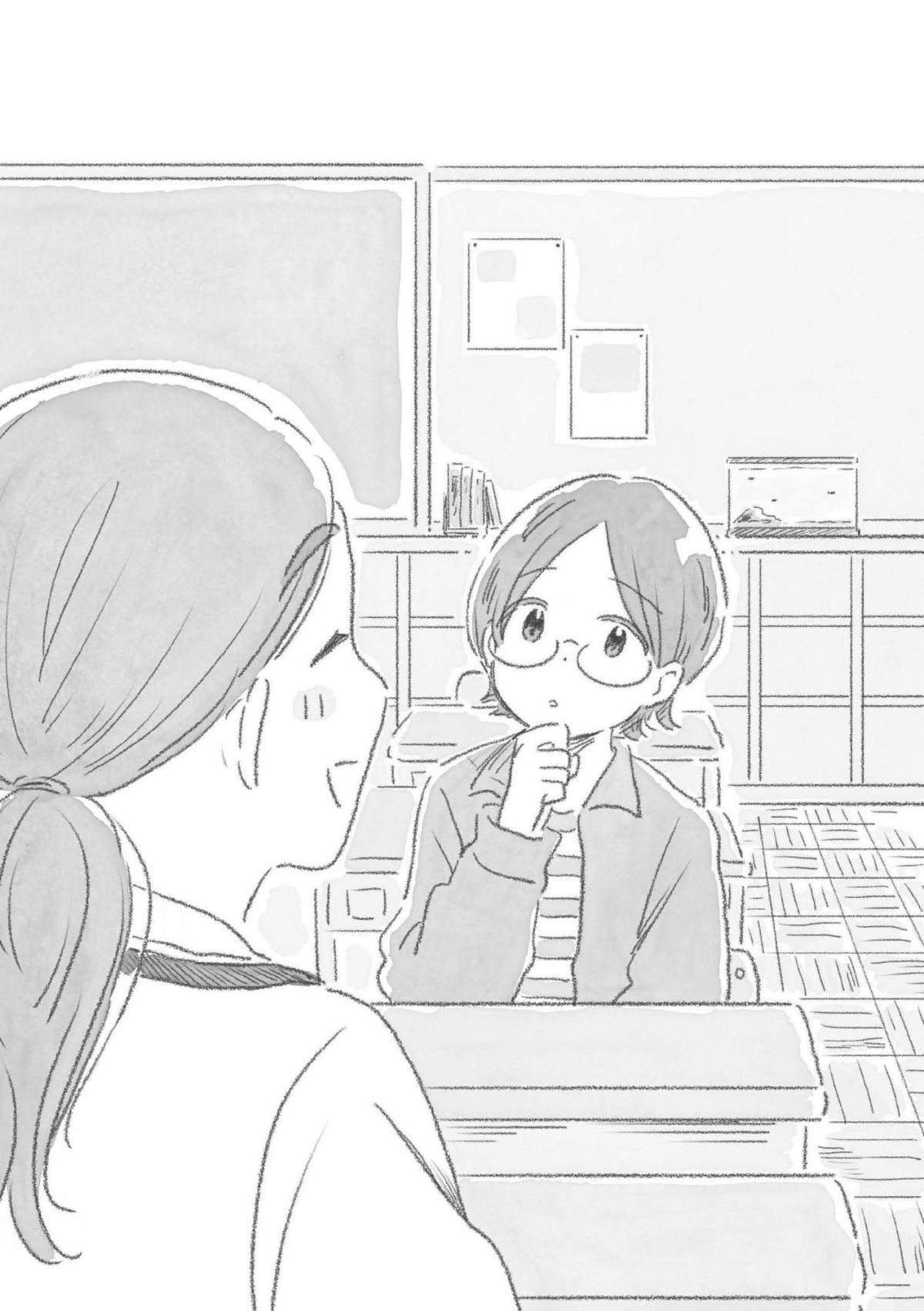
――説教くささを出さないでテーマを伝えるって、すごく難しいと思います。どんな点に心を配りましたか?
清水:「何を言うか」はもちろん大事なのですが、「誰が言うか」はもっと大事なことであって。あそこでは西方先生という、ちゃんとした大人がちゃんとしたことを言うからこそ、有希にも読者にも伝わる――というふうに書かなければならないと思いました。それまでにときどき出てくる西方先生が、生徒に対して真摯に向きあい、彼らを子ども扱いせずに人間として対等に接する人物であることをきちんと描くよう心がけました。登場場面はけっして多くありませんが、とても重要なキャラクターです。
――先生との対話によって有希は大きな気づきを得ます。“普通”の人なんてこの世界のどこにもいないんだ、と。雪が静かに降り積もるなかを歩きながら、そのことに気がつく有希の姿は感動的でした。
清水:あの場面は、雪が降っているイメージがまず初めに浮かびました。雪がしんしんと降るなかで有希が一歩一歩、歩いていく様子を想像して書いていきました。一文一文を短くして、静かに緊張感を高めながら。物語の時間軸と、読んでいる人の時間軸が重なるようなリズムとテンポをつけて。第三話の自転車旅行のくだりでもそうなのですが、僕は書くときにその場面の映像を思い描くんです。映像的なイメージがあることで、時間の流れや風景もあらわすことができる。
――本書は初の児童書ですが、どんな人たちに読んでもらいたいですか。
清水:たくさんの人に読んでもらいたいのはもちろんなのですが、一番届けたいのは、有希のように今現在学校へ行くことのできない子や、学校へ行くことに辛さを感じている子たちですね。最後で有希が気がついたこと――自分は普通にはなれないかもしれないけど、特別にはなれる。このメッセージを届けるためにこの作品を書きました。
――もしも清水さんが習千葉小学校の生徒だったら、どんなときにトクベツキューカを使いたいですか?
清水:凛ちゃんみたいに「今日は雪が降ってるから」という具合にそのときの気分で使うか。あるいは浩のように、いざというときのためにずっと大事にとっておくか……このどちらかだと思います。自分だったらどんな日に使いたいか、想像しながら読んでもらえたら嬉しいです。
取材・文=皆川ちか





