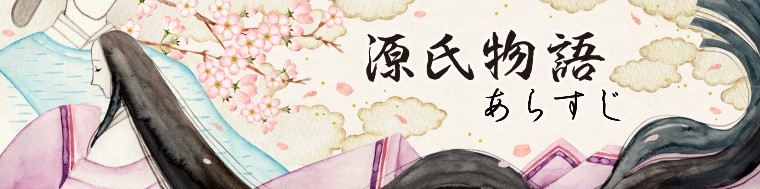紫式部『源氏物語 四十帖 御法(みのり)』あらすじ紹介。波乱に満ちた源氏物語のヒロイン・紫の上の死。源氏に最も愛された女性の最期とは…?
更新日:2025/3/11
平安時代の恋愛小説『源氏物語』を読んだことはありますか。国語や歴史の教科書に掲載されていたり、作者・紫式部の人生がドラマ化されたりして、興味がある方も多いかもしれません。どんな物語なのかを知ることができるよう、1章ずつ簡潔にあらすじをまとめました。今回は、第40章『御法(みのり)』をご紹介します。

『源氏物語 御法』の作品解説
『源氏物語』とは1000年以上前に紫式部によって書かれた長編小説です。作品の魅力は、なんといっても光源氏の数々のロマンス。年の近い継母や人妻、恋焦がれる人に似た少女など、様々な女性を相手に時に切なく、時に色っぽく物語が展開されます。ですが、そこにあるのは単なる男女の恋の情事にとどまらず、登場人物の複雑な心の葛藤や因果応報の戒め、人生の儚さです。それらが美しい文章で紡がれていることが、『源氏物語』が時代を超えて今なお世界中で読まれる所以なのでしょう。
「御法」とは仏事のことで、紫の上が最後に営んだ法事で花散里と詠み交わした和歌に因んだ章名です。紫の上の死に臨む姿は、凛として、美しく清らかで、並ぶもののない圧倒的なヒロインであったことを改めて感じさせます。それに対し、紫の上亡き後の源氏は落胆し出家への思いを強くしますが、世間に何と思われるかを気にして決断できずぐずぐずと悩み続けます。「妻を失って俗世に未練はないけれど、住み慣れた我が家を離れ、地位や財産も捨てて籠るのも嫌だなあ」なんて考えているのかもしれないと想像すると、1000年前の読者も完全無欠ではない源氏に人間的な魅力を感じていたのかもしれません。
これまでのあらすじ
源氏が40歳の時に、朱雀院の娘・女三の宮が降嫁した。正妻の立場を譲ることになった紫の上は心労で病に倒れた。紫の上の看病に暮れる源氏の不在を狙って、以前から女三の宮を慕っていた柏木が強引に女三の宮と契り、女三の宮は間もなく男児を出産する。密通の罪の意識に苛まれた女三の宮は出家をし、柏木は若くして亡くなった。源氏の愛情は紫の上に注がれていたが、紫の上の病状はよくなることはなく月日が経っていった。
『源氏物語 御法』の主な登場人物
光源氏:51歳。
紫の上:43歳。数年前から体調を崩し、療養を続けている。
明石の中宮:23歳。源氏と明石の君の子。今上帝(きんじょうてい・冷泉帝譲位後の帝)の中宮となる。
夕霧:30歳。源氏と故葵の上の息子。
花散里:六条院に住む源氏の妻のひとり。夕霧の養母。
匂宮:5歳。明石の中宮の子。紫の上に育てられ、母のように慕っている。
薫:4歳。源氏と女三の宮の子として生まれたが、実の父は故柏木。
『源氏物語 御法』のあらすじ
数年前に大病を患ってから、紫の上の体調は回復することがなかった。出家を切に願う紫の上だったが、源氏はひとり残される寂しさからそれを許さなかった。
3月、紫の上が主催する法事が花の盛りの二条院で盛大に営まれた。宮中や六条院の人々が訪れ、紫の上は花散里や明石の君と歌を詠み交わした。紫の上は、命が残りわずかであることを覚悟し、長年連れ添った源氏を悲しませることを心苦しく思っていた。
夏になると、紫の上はさらに衰弱していった。これといって悪いところもないが、日に日に弱っていく紫の上を、明石の中宮が見舞った。中宮の部屋に出向く力すら残っていない紫の上であったが、その顔は華やかで美しく、自分の亡き後に残される女房たちのことをそれとなく託し、気丈に振る舞っていた。紫の上を母のように慕う匂宮(明石の中宮の子)の成長が見届けられないことに涙した。
過ごしやすい秋が来ても、紫の上の病状はよくなる気配がなかった。8月14日、源氏と明石の中宮が最後の見舞いに訪れ語り合った後、中宮に手を取られながら夜が明ける頃に静かに息を引き取った。源氏と夕霧は、紫の上の清らかで美しい死に顔を見つめ涙を流して悲しみ、翌日には源氏の指示で夕霧が葬儀を執り行った。源氏は悲しみに打ちひしがれ威厳を保つこともできず、周りに支えられながら最愛の妻を見送った。
その後、帝や前太政大臣、秋好中宮などの弔問が続いたが、源氏の悲しみは癒えることがなかった。前々から決めていた出家への思いを強くしていたが、世間の外聞を憚り決断しかねていた。
<第41回に続く>